
異業種連携を取り巻く企業の共通の「悩み」とPwCの「強み」
2025-01-22
社会・経営環境が激変するなか、企業は従来とは全く異なる次元の経営課題に直面しています。より複雑化する課題を克服し、企業価値を創造するための手段のひとつとして、M&Aにより外部のケイパビリティを取り込むこと、またはアライアンスやビジネス・エコシステムの形成により相互のケイパビリティを利活用することの重要性が高まっています。
PwCコンサルティングのX-Value&Strategy(以下、XVS)では、クライアントの皆様が抱える課題の解決や企業価値向上のため、目指すべき将来像の再定義や、その実現に向けた機能や遂行能力の再設計、必要なM&A・戦略的提携・異業種連携に関する戦略策定・実行などを支援しています。
XVSのサービスラインナップのひとつである異業種連携ソリューションについてご紹介します。
登場者
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
石本 雄一
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
浅野 泰史
PwCコンサルティング合同会社 アソシエイト
熊野 えいみ
※法人名、役職、インタビューの内容などは掲載当時のものです。

(左から)石本 雄一、浅野 泰史、熊野 えいみ
時代の変化とともに欠かせない選択肢となった異業種連携
熊野:
今回はXVSのサービスラインナップのひとつである異業種連携ソリューションにフォーカスしてお話を伺いたいと思います。まず概要について教えていただけますか。
石本:
近年、同業種間の経営統合のみならず、異業種間のアライアンスを通じた新たな事業創出を目指す動きが強まっています。M&Aや組織統合・再編を支援してきたXVSではこの潮流に応えるべく、培ってきた幅広いネットワークや知見・ノウハウをフル活用し、異業種連携による価値実現を全フェーズで支援しています。
熊野:
近年、異業種連携の動きが活性化している背景についてはどう分析されていますか。
石本:
人口減少や少子高齢化、産業構造の変化、デジタル化やテクノロジーの進化により、ビジネスを取り巻く環境は大きく変化しています。近年ではコロナ禍がその変化のスピードを大幅に速めるドライバーになりました。急激な速さで変化する世の中の動きに対応しながら事業の強化・進化を推進するためには、社内の組織変革や同業種企業の統合だけでは間に合わない。異業種間で保有しているケイパビリティを掛け合わせてこそ、新たな価値を創出できる。そう感じている企業や経営者が増えているということが活性化の背景にあると思います。
熊野:
XVSの異業種連携ソリューションは、具体的にどのようなサービスを提供するのでしょうか。
石本:
異業種連携ソリューションはふたつのアプローチを取っています。ひとつはクライアントニーズドリブン型。もうひとつはPwCビジョンドリブン型です。
クライアントニーズ型の場合、メガトレンドや関連業界の将来予測に基づいた新ビジネスのアイデア出しに始まり、具体的なビジネスモデルの検討、連携可能性がある企業の探索、候補企業へのアプローチ、連携のための交渉やコミュニケーションまで支援します。また連携後のサービス立ち上げの際には、PoC(概念実証)の計画から実行支援、サービスローンチまで伴走しています。
一方、PwCビジョンドリブン型は当社が社会課題の解決にトライするなかで、各業種の可能性を分析しながら構想を練り、趣旨に賛同いただけるクライアントの皆様にお声がけさせていただくモデルです。クライアントニーズ型よりも中長期的な取り組みであり、そのなかでビジネスモデルを描いて各社に提案し、プロジェクト全体をリード・調整する役割を担っています。
熊野:
これまで実際に取り組まれたプロジェクト事例について教えてください。
浅野:
直近では大手の不動産会社の事例があります。同社は、少子高齢化が進み将来的に市場環境が厳しくなることを想定し、新たな収益の柱として住民向けサービスプラットフォーム創出を検討しており、私たちにご相談下さいました。いわば、不動産業から生活インフラビジネスへのトランスフォーメーションをサポートした事例となります。
同案件ではアイディエーションや事業性の検証、入退去・生活に必要な商品・サービスの購入と不動産管理機能を利用可能なアプリ開発、蓄積データの利活用、ローンチ後のサービス改善までの実行を支援しています。
熊野:
本事例で価値を実現するにあたり最も難しかったのはどのような側面でしょうか。
浅野:
クライアントは業界内では知名度が高く、かつ顧客を相当数抱えている企業でした。新サービスで提携することに賛同してくれる企業も比較的多く、構想段階から首を横にふる提携先はあまりいませんでした。ただ、実際にプロジェクトを進めるなかで、各ステークホルダーの収益性、新しいオペレーションの在り方などについて折り合いをつけていくことに苦労しました。
異業種連携を実行する際には、そもそも提携先がビジネスとして儲かる業態なのか、もしくはシナジーを生めるのかなど、ビジネス構造を理解していないと交渉を着地に結びつけることができません。本プロジェクトの場合、その部分を明らかにし、ビジネス面・運用面双方で押さえるべきポイントを可視化できたことがブレイクスルーの契機になりました。議論の枠組みを用意することで、クライアント・提携先が互いに歩み寄るための意思決定スピードが高まり、最終的にサービスローンチまで漕ぎつけることができました。
熊野:
本プロジェクトの議論を発展させ、新しいビジネス展開を可能にしていく上でXVSやPwC Japanグループが発揮した価値についてはどう捉えていますか。
浅野:
プロジェクトにおいて、私たちのチームはビジネス構想やアライアンス領域を担当しました。その際、テクノロジーチーム、ブランドチーム、データアナリティクスチームなど、PwC Japanグループ全体の力を掛け合わせて、お客様のビジョンを実現する上で最適なメンバーを構成できたことが大きな価値提供に繋がったと自負しています。XVSがビジネス視点、アライアンス視点でシステムチームにアドバイスしたり、また逆にシステム目線でアドバイスをもらったりすることを繰り返して、新ビジネスの蓋然性を高めることに寄与できたと考えています。
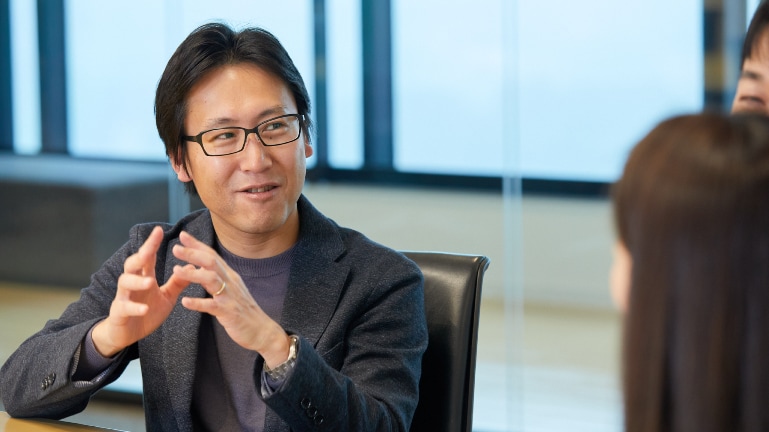
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 石本 雄一

PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 浅野 泰史
異業種連携とエコシステム創生でビジネスと課題解決の両輪を回す
熊野:
PwCビジョンドリブン型では、どのようなプロジェクトを展開していますか。
浅野:
直近ではヘルスツーリズムの実現を構想中です。コロナ禍の影響で運動しづらくなり、生活習慣病患者の増加が懸念されています。そこで旅行会社、ホテル運営会社、福利厚生事業者、運動・サプリ・睡眠関連などのヘルスケア商品・サービス提供企業、健康経営企業にお声掛けをして、エコシステムを創生する形で連携し、実現を目指しています。
熊野:
1社だけでは解決できない規模や複雑性を持った社会課題が数多く存在します。異業種連携はそうした課題解決に対してどのような強みを発揮すると思いますか。
石本:
異業種連携に連なるエコシステムの創成は、社会課題の解決に繋がる試金石になると考えています。例えば、ヘルスツーリズムのプロジェクトは、社員の健康を守ることで生産性を高めるという、日本経済の活性化という大きな課題を解決するための打ち手のひとつ。ただ単一事業者だけではマネタイズが難しく持続可能性を担保できません。異業種と組むことでビジネスとして成立する可能性がはるかに高まります。
私たちはこれ以外にも、日本経済を直撃している人材不足の問題に取り組もうとしています。リカレント教育やリスキリングが大きな課題として浮上していますが、人材系企業とともに新たなサービスを通じて解決を図っていく計画です。
本事例では、人材系企業は人材と仕事を最適にマッチングする役割を担っていますが、リカレント教育やリスキリングを実行するとなると教育事業者とも組まなければなりません。また、ワークプレイスを提供する事業者、また働く人たちの心身の健康を担保して生産性を高めるヘルスケア企業などにも参加してもらってこそ、プロジェクトの本来の意義を達成できると考えています。
浅野:
エコシステムによる社会課題解決を目指す際には、ビジネスと課題解決の両輪を意識する必要があります。政府や自治体の補助金があれば一度は何かを試みることはできるかもしれません。しかし、そこでビジネスとして回る仕組みがなければ事業が維持できず、結果的に社会課題の解決も果たせない。異業種連携によるエコシステム創生においては、ビジネスとして成立する仕組みを生み出せることが私たちの強みだと考えています。
異業種連携を取り巻く各社共通の悩みとXVSの強み
熊野:
異業種連携を実現していく上でクライアントの皆様が特に困っている悩み、円滑な連携を阻む共通要因にはどのようなものがあると分析していますか。
石本:
業界によって商習慣が大きく全く異なることは、提携を目指す上で障壁になることが多いです。また、同じ言葉や単語を使っているものの業種によって意味合いが違う、もしくは意味は一緒だが重さが違うというようなケースが往々にしてあります。
例えば、安全性・信頼性という言葉に対する業種間の意識の重さには違いがあります。医療・ヘルスケア業界では安全性・信頼性は何よりも重要なものですが、一方でBtoCサービスを提供するデジタル企業だと優先順位はそれほど高くない。言葉のギャップが埋まらないと上手くタッグを組めないので、支援する際にはコミュニケーションを促すための“翻訳”に細心の注意を払っています。
業種によって意識が異なるということに加えて、そもそも論として、互いの事業をそれほど知らないというケースも少なくありません。同業だと提携先がすぐ頭に浮かぶのですが、異業種だと全く見当がつかないというものです。その点において、XVSやPwC Japanグループには各業種の精鋭チームが揃っており、連携時に生まれるシナジーを精密に推測することができるため、クライアントの皆様からお声がけをいただける理由のひとつになっていると思います。
浅野:
実は連携に期待する効果・目的が違うことも多々あります。ひとえにビジネスのためといえども、「顧客とのタッチポイントを得たい」「データを得たい」、あるいは「エコシステムの中で他のプレイヤーと繋がりたい」など、企業によって求めるゴールが異なります。各社が期待する目的や効果を汲み取ってアプローチを組み立てたり、新たなモデルを構想・実行したりするのが私たちの役割となります。
また異業種連携はM&Aと違って強制力が弱いがゆえの苦労があります。スケジュールの制限がないため、始めやすいが実現まで至りにくいという傾向があるのです。そのような特徴があっても、プロジェクトを前に進めつつ、コストとパフォーマンスを見極めながら適宜アドバイスや実行支援ができるのがXVSのソリューションの価値です。
熊野:
クライアントの皆様を支援する過程で、ソリューションのどのような側面を評価いただいていますか。
浅野:
XVSでは各社の戦略を描く段階からご一緒させていただいているケースが多いです。そのため異業種連携の際にもケイパビリティの活かし方や、効果的な連携を発想できるところが強みだと考えています。提携先を探す際、両社のケイパビリティを理解しているからこそ、精度の高い提案が可能です。なお、経営層の方々は時代や競合の変化を敏感に感じていらっしゃいますし、早く動かなければならないという危機感も抱いています。各クライアントの意思決定者と直接会話できることもXVSの強みであり、提案や事業推進のスピード感も評価いただいていると感じます。

PwCコンサルティング合同会社 アソシエイト 熊野 えいみ

当事者意識の洗練と視野の広がりがXVSで働く魅力
熊野:
皆さんはXVSで異業種連携ソリューションに携わりながら、どのような刺激とやりがいを感じますか。またどのようなスキルが磨かれたと考えていますか。
浅野:
私は前身となるPMI(Post Merger Integration)チームから参画していますが、異なる企業を結びつけることに以前から魅力を感じており、異業種連携やエコシステムソリューションにおいても適性が生きていると感じています。
また、クライアント同士はもちろんのこと、社内のさまざまな専門家を繋げて大きな価値にしていくというスキルも磨かれました。XVS以外にも、PwCにはさまざまな事業領域に精通したメンバーが集まっています。新しいアイデアを考える際や専門的な検討時にディスカッションに入ってもらうことも多く、自分の視野・視座が広がることにいつも大きな刺激を受けています。
熊野:
クライアントの皆様に異業種連携の真価をデリバリーする立場でありながら、社内外を問わず異なるバッググラウンドの有識者とのディスカッションが多いため、自身の成長を感じられたということですね。今後、異業種連携ソリューションの展望についてはどうお考えですか。
浅野:
異業種連携やエコシステムソリューションは、日本企業にとって可能性のあるソリューションになると思います。さまざまなクライアント企業の経営層の方々と話をすると、いずれも異業種連携に取り組みたい、取り組まなければならないと前向きに捉えられているタイミングだと感じます。クライアントの皆様と一緒に、ワクワクできるアイデアをさらに実現できるソリューションにしていきたいです。
また異業種連携で価値を実現する際には、いろいろな立場の人の目線や意見を闘わせることが欠かせません。業種を気にせず、チームに新しい風と視点をもたらしてくれる方々の参加に期待しています。
石本:
異業種連携は産業構造の変化を直接的にリードするソリューションです。世の中に大きな波を起こすために、今後も力を入れていきたい。そのためにも、「自分はこう思う」というしっかりとした意見と、それを貫く責任感を持ったメンバーにどんどん集まってほしいです。XVSのなかでの波の活性化が、ひいては日本経済の活性化に繋がる。そう信じてソリューションの充実に励みたいと考えています。



