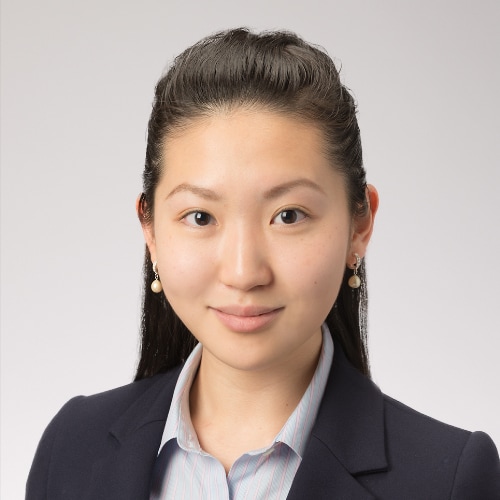{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2023-04-12
医師や看護師などの医療従事者、最新の知見や技術を持つ研究者、医療政策に携わるプロフェッショナルなどを招き、その方のPassion、Transformation、Innovationに迫るシリーズ「医彩」。第12回は石川県立看護大学学長で東京大学名誉教授の真田弘美先生をお迎えしました。
真田先生は褥瘡(じょくそう:床ずれ)医療・看護研究の第一人者としてご活躍です。また、東京大学大学院医学系研究科に「グローバルナーシングリサーチセンター」を設立し、次世代の看護を担う若手看護学研究者の育成と同時に、同センターの「ケアイノベーション創生部門」では産学連携での研究開発に取り組んでいらっしゃいます。「治す医療」から「支える医療」への大転換が求められる中、これからの産学連携医療には何が必要なのでしょうか。お話を伺いました。(本文敬称略)
真田 弘美 先生
石川県立看護大学 学長
東京大学 名誉教授
PwCコンサルティング合同会社
パートナー 大森 健
PwCコンサルティング合同会社
マネージャー 中谷 彩乃
PwCコンサルティング合同会社
シニアアソシエイト 田中 志保
※所属法人名や肩書き、各自の在籍状況については掲載当時の情報です。
田中:
最初に私自身の紹介となりますが、私は大学院生時代の2年間、真田先生の老年看護学/創傷看護学研究室に在籍していました。先生の下で学んだ経験は、私にとって仕事の礎となっています。
先生のこれまでの御活躍内容をご紹介いただくだけで紙幅が埋まってしまうのですが、活動の原動力となる「パッション」を教えてください。
真田:
看護とは患者さんに寄り添い、健康増進療養や症状緩和を支援することです。そして看護は社会の要請に応じて変化します。新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延した際、最も患者さんに寄り添ったのは看護師でした。多くの患者さんの命を救えたのは、医師だけではなく、看護師の力によるところも大きいのです。私は看護師であることを誇りに思っています。
患者さんの体に接する看護に何が必要かを考えると、それは「新技術」です。医師はMRIやさまざまな検査器具を使用して診断し、ある程度の時間をかけて治療方針を立案します。一方、看護師は患者さんに接すると同時に、リアルタイムに症状緩和をしなければいけません。新しい方法など考える時間はありません。そのような立場でできることは、今まで使ってきている技術を応用するといった補足的なものでした。
ですから「苦しむ患者さんをお楽にできる器具を作るしかない。そのためには研究者になって開発しなければいけない」と思ったのです。もちろん、器具の開発には看護の知識だけでなく、生理学や工学の知識が必要です。ですから産学連携で研究開発を進め、新たな学問を作りたいと考えました。こうした研究開発はアカデミアの仕事だと考えており、これが私のパッションかもしれません。
田中:
先生は褥瘡の研究で、褥瘡部評価のための客観指標「DESIGN」を開発されました。そのほかにも褥瘡治療を支援する器具や皮膚保護剤などを開発されています。また、「2020年東京パラリンピック」の車いすバスケットボール選手のために、車いすクッションを開発したと伺っています。
真田:
褥瘡は、長時間の座位姿勢で圧迫された部分に血が流れなくなることが原因です。ですから、車いすクッションの開発は、選手の褥瘡予防とケアの観点からも非常に重要でした。なぜなら、褥瘡部位から細菌感染が全身に広がると発熱することがあり、発熱した選手は試合に出場できないからです。
田中:
車いすクッションの開発にはどのような方々が携わっていたのでしょうか。
真田:
東京大学(東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター)と日本車いすバスケットボール連盟、そして健康・介護用品の開発販売を手掛けるメーカーに参画していただきました。また複数の工学の先生の力もお借りしました。
車いすを自分の足のように操る選手にとって、クッションを変える(座面を変える)のはすごく難しいことでした。しかし、プロジェクトメンバーは実態調査からコンセプトの抽出、褥瘡予防技術の開発評価など、日本代表選手が国際大会でベストパフォーマンスを発揮してメダルを取ることを目標に、一段ずつ階段を上がっていきました。ちなみに、同プロジェクトは試合が終わるまで隠し通す必要がありました。ライバルチームに真似をされないためです。
私は本プロジェクトで1つの「レガシー」が残せると考えていました。それは車いすバスケットボールが社会的に認知されることで、車いすの方々が当たり前のように社会で活躍する国になることです。余談ですが、車いすバスケットボールの男子日本代表がこの大会で銀メダルを獲得するまでの軌跡を描いた書籍には、褥瘡予防が非常に重要だったことが書かれています。
田中:
実は、車いすバスケットボール男子日本代表の監督をされていた及川晋平さんはPwCのメンバーでもあり、ご本人から「大きな課題であった褥瘡を真田先生に解決していただいたことが、選手の成長と結果につながりました」とのコメントを預かっています。優れたサポートだったのですね。
真田:
それは、嬉しいですね。ただ私は、サポートではなく学んだのだと思っています。彼らは150%の努力をすることを目指していました。その結果、真価を発揮することができたのだと。
中谷:
すばらしい産学連携プロジェクトですね。
真田:
とはいえ、過去にはたくさん失敗もしています。ただし、当時は気が付かなくても、振り返ってみたら失敗していた経験が1つにつながり、成功の礎になっていたと気付かされることも多いです。どんなに失敗しても諦めずに頑張ってきたことが、今の人生につながっていると考えています。
中谷:
先ほど「産学連携で研究開発を進め、新たな学問を作り出すことはアカデミアの仕事」とのお話がありました。これは具体的にどのようなことでしょうか。
真田:
私は産学連携を基盤とした「看護理工学」を確立したいと思っていました。従来の看護研究は患者さんのニーズを疫学的な研究手法で行われてきました。しかし、この方法ではニーズが浮き彫りになるだけで、解決の術までは示されません。これでは患者さんの問題は解決されず、幸せになれるはずがありません。私はその状況にジレンマを感じていました。
そこで、療養生活の支援を目的として「看護理工学」の研究に取り組み、「看護理工学会」を立ち上げました。看護理工学は「看護」「医学」「理学」「工学」「産業」を融合させ、患者さんに対してよりよいケアができる方法を追究する学問です。患者さんと長時間接している看護師の視点を取り入れ、学問領域だけでなく産業界とも協働しながら“モノ作り”をしていく取り組みです。
現在、看護理工学会には約700名の会員がおり、半数が看護師です。そのほかの会員は工学・医学の専門家、機器開発に従事する企業の研究者・開発者の方々です。看護理工学会を立ち上げたことで、バイオ(生命化学)の専門家とも仕事をする機会ができました。
そして、こうした方々と仕事をする中で感じたのは、「ナースサイエンティスト」を育てる場所がどこにもなかったことです。(看護師の)博士研究員を育成する機会も、働ける場所もなかったのですね。ですから次世代の看護を担う若手看護学研究者のため、看護学を基盤にした異分野融合型の、世界のどこにもない研究所「グローバルナーシングリサーチセンター」を東京大学に設立しました。
中谷:
グローバルナーシングリサーチセンターではどのような研究をされているのでしょうか。
真田:
同センターの「ケアイノベーション創生部門」では、ロボティックスやバイオロジカルナーシング、イメージナーシングなど、新技術を活用した看護のあり方を研究しています。AI(人工知能)やロボットが当たり前になる「Society 5.0」時代に対応できる看護師を育成するという意味において、ケアイノベーション創生部門が果たす役割は大きいと考えています。「治す医療から支える医療」への転換で看護師として何ができるかを考えながら、研究に取り組んでいます。なお、ケアイノベーション創生部門の取り組みは、全てが産学連携です。
中谷:
その1つが携帯型のエコー(超音波画像診断装置)の開発ですよね。
真田:
はい。ケアイノベーション創生部門ではイメージングテクノロジーを活用した看護技術支援の開発研究をしており、「可視化」という技術を看護師のフィジカルアセスメントに取り入れたいと考えていました。
実は、エコーを開発した動機も褥瘡のケアでした。褥瘡は外部からアセスメントをしても、どの程度の深達度かを判断することが難しいのです。患部を検査するには検査技師に依頼して画像を撮影してもらうのですが、それには時間がかかりますし、在宅の患者さんに対しては実施できません。
しかし、簡単に持ち運べるエコーがあれば、「Point Of Care Testing(臨床現場即時検査)」がその場でできます。皮下の症状が可視化されれば、診断とアセスメントとケアが同時にできるのです。技術の進化で超音波装置は小型化していますから、不可能ではありません。
ただし、開発にこぎつけるには大きな壁がありました。2014年ごろから取り組みを開始し、さまざまな企業に呼びかけたのですが「ノー」と言われ続けました。
中谷:
なぜでしょう。
真田:
「エコーは医師が使うもので、看護師が使うものではない。看護師用のエコーを開発したら医師に嫌われて病院に出入り禁止になる。そうはなりたくない」という理由です。こんなおかしな話はありません。「看護師がエコーを使ってはいけない」という決まりはないにもかかわらず、「エコーは医師の道具」という概念が定着し、それに企業側が縛られているのです。私は看護師がリスペクトされていないことにショックを受けました。
そのような状況下で、あるメーカーに出会いました。彼らは私たちのプレゼンテーションを聞いて、「10年後の日本(の医療)は、看護師がキーパーソンになります。2025年を目途に構築が進んでいる『地域包括ケアシステム』を中心となって回すのは看護師です。その看護師に投資することで日本の医療も変わるし、企業として自分たちにも益になります」と言ってくれました。私はこの言葉を聞き、「看護にリスペクトを持ち、同じビジョンで患者さんに向き合える会社と出会えた」と嬉しくなりました。
中谷:
「携帯型エコー」は看護の現場でどのように活用されているのでしょうか。
真田:
いちばん力を入れたのが便秘症状の評価です。特に認知症の患者さんは便秘の症状を正しく訴えられず、ケアをする看護師もアセスメントに難しさを感じていました。さらに、在宅では便を直接観察できないこともあり、評価が困難でした。これに対して携帯型エコーが使えれば、大腸の中に貯留している便を可視化し、AIで便貯留部分をカラー表示できます。これにより、トイレ誘導、下剤投与や坐薬挿入、摘便実施など適切なケアができるのです。
大森:
現在はさまざまな領域で産学連携を推進する動きが高まっています。それらを成功に導き、イノベーションを継続的に定着させるにはさまざまな課題を克服しなければならないですよね。その“極意”はあるのでしょうか。
真田:
「魔の川・死の谷・ダーウィンの海」という比喩があります。これは技術経営の分野で、研究開発から事業化までのプロセスで乗り越えなければならない3つの障壁を例えたものです。研究してもそれが開発につながらない「魔の川」、開発にこぎつけたものの事業として成立しない「死の谷」、そして事業が一般の人に届かない「ダーウィンの海」です。私は53の特許を取得していますが、魔の川を越えられたのは10分の1しかありません。
大森:
「携帯型エコー」が「死の谷」を越えられた理由は何だとお考えですか。
真田:
私たちをサポートしてくれたメーカーの「哲学」と「理念」による部分が大きかったと思います。
エコー開発の連携が決まった時、同社の若い方が「(連携プロジェクトは)東大に弊社のサテライトを作るんですよね」と言われたんです。私が「違います」と申し上げたところ、同社の部長職の方が「真田先生は『イメージング看護学』という学問領域を確立し、世の中の看護師に広めたいんですよね」と仰ったのです。その方がアカデミアの世界と役割をよくご存じだったのかもしれませんが、「このメーカーには社会に役立つには何をすべきかを考える企業文化がある」と感激したことを覚えています。
大森:
産学連携で企業側に求められるのは、「世の中の役に立ちたい」というマインドですね。
真田:
当然、アカデミアと企業は立場が異なりますから、議論を戦わせることもあります。例えば開発製品を事業化する際、企業側は「今年度の売上目標は300台」というような短期間での結果を求めがちです。しかし医療の世界はマーケティングしてもわかるようにどんな戦略を考えても「口コミ」による部分が勝ちます。よい製品を開発したとしてもすぐには売上につながりません。こちらは「本当によい製品は必ず残ります。だから口コミが広がるまでの3年から5年間は耐えてください」とお願いします。実際、こうしたやり取りは少なくありません。
もっとも大事なのは企業が「患者さんファースト」を原点として考えているかです。最新の技術を備えていても患者さんにとってよいものでなければ意味がありません。“産”と“学”で意見の齟齬があった時には、必ず両者が原点に立ち返るようにしています。
大森:
“産”と“学”はその立場の違いやさまざまな事情から妥協を余儀なくされることもあります。しかし患者さんファーストという軸があれば、「妥協するか、しないか」を判断できます。
真田:
そのとおりです。携帯型エコーの開発では一度だけ意見が対立したことがあります。当初、備えるAIの的中率は70%だったのです。メーカー側はこれでリリースし、学習データを蓄積しながら的中率を向上させたいと主張しました。しかし70%の的中率では、怖くて患者さんに使用できません。私たちは「少なくても90%(の的中率)にしてほしい」とお伝えし、ここは妥協しませんでした。最終的にメーカー側も「患者さんファーストで考えれば70%ではダメだ」ということを理解してくれました。
中谷:
次世代の看護では、デジタルソリューションも重要なツールになると考えます。患者さんファーストで看護をするうえで、どのようなデジタルツールが求められるとお考えですか。
真田:
今後、日本が直面する課題は「地域格差」です。限界集落に住む方々が都市在住者と同水準の看護が受けられるためには、ICTの活用は欠かせません。例えば、通信機能が備わっているエコーであれば、病院側で画像データをリアルタイムに確認できます。また、IoTセンサーを備える電動ベッドは患者さんの体の動きを感知して遠隔操作し、寝起きを支援することも可能です。Vital signsはあたり前のこと、こうした技術を現場で当たり前に活用できるよう、今から準備をしておく必要があると思います。
もう1つはコミュニケーションロボットです。今後、一人暮らしの高齢者の増加に比例し、認知症になる方も増加しますから、ニーズは増加するでしょう。しかし、デジタルツールだけで課題が解決するわけではありません。例えば訪問看護師は、患者さんとのコミュニケーションで体や心の状態を読み取っています。皮膚の色を見て「血管が拡張しているから今日は血圧が高い」という判断をしています。看護師が大事にしなければいけないのは、患者さんとのコミュニケーションです。それを第一に考え、ICTで補える部分は補う姿勢が大切だと思います。
田中:
コンサルティングもさまざまな視点を取り入れながら課題解決をしていくことが重要です。私たちもクライアントにとって何が最善なのかを考える「クライアントファースト」が求められていると感じました。最後に、先生がコンサルタントに期待することを教えてください。
真田:
コンサルタントの方々にはさまざまな情報を社会に拡散していただきたいです。理学療法士や臨床栄養士などが日々どのような仕事をしているのかを、コンサルタントの情報発信力を活かして多くの方々に知ってほしい。専門職としての彼らのプロフェッショナル性を理解して情報発信すると同時に、彼らを会社と結び付ける役割を担っていただくことを期待しています。
大森:
本日お話いただいた「ないものは作っていく」というマインドを持つことは、私たちにも必須であると強く実感しました。患者さんファーストを軸にすることは、患者さんを支援する看護師にも寄り添っていくことだと思います。そのためには看護師の視点に立脚し、連携を深めていくことも重要だと気付かされました。本日はありがとうございました。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}