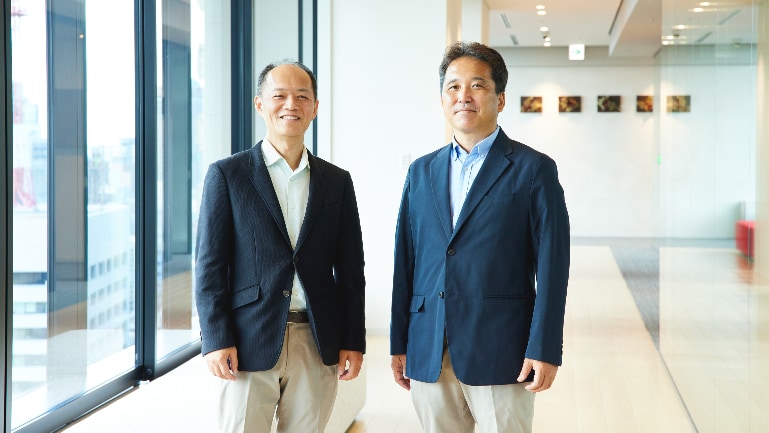{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
ネットゼロ(Net Zero)とは、温室効果ガスの排出と吸収の均衡を追求し、全体の排出を“正味”ゼロとする取り組みを指します。世界の国々が実現に向けて結束している中にあって、日本政府も2050年までにカーボンニュートラルの達成を公言しています。
第一生命グループ(以下、第一生命)は、このネットゼロの実現を目指す国際的な金融機関の連合、グラスゴー金融同盟(GFANZ)に初期段階から参画し、主要な役割を担ってきました。直近ではアジア太平洋(APAC)エリアの拠点、日本支部の設立にも主導的に取り組んでいます。
今回、GFANZのステアリンググループのメンバーとして取り組みを牽引する第一生命の太田浩氏を迎え、ネットゼロ達成に向けて金融機関が担うべき役割や、そのビジョンについて深く探る機会を得ました。インタビュアーを務めるPwC Japanグループのサステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスの牧内秀直は、過去、第一生命での勤務経験を持ち、太田氏の前任者としてGFANZのステアリンググループでの活動に携わっていました。その経験を生かし、より深い視点でGFANZについて迫ります。
太田浩氏
第一生命ホールディングス株式会社
第一生命保険株式会社
経営企画ユニット サステナビリティ推進室 フェロー
牧内秀直
PwC Japanグループ
サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス 執行役員
※法人名、役職、インタビューの内容などは掲載当時のものです。
(左から)太田浩氏、牧内秀直
牧内:
改めてということになりますが、最初に第一生命のネットゼロに向けての取り組みをお伺いさせてください。
太田:
第一生命は、将来にわたって、すべての人々が安心に満ち、豊康な人生を送り、幸せな状態であること、すなわちwell-beingに貢献し続けられる存在でありたいと願っています。また、私たちの事業は、持続的社会があってこそ実現するものですから、そのことに貢献していくことは“一丁目一番地”の重要課題という認識でネットゼロに取り組んでいます。生命保険事業の性質上、今現在ご契約いただいている世代はもとより、将来世代に生きる人々も私たちのステークホルダーということになります。未来にわたって安心して暮らせる環境を作るのは、第一生命の本来事業における最大の関心事なのです。具体的に言えば、第一生命グループ全体の事業活動から排出される温室効果ガスを2040年までにネットゼロにし、第一生命保険として関与するサプライチェーン――主に投融資先、投融資ポートフォリオは2050年までに達成するとしています。
牧内:
GFANZ(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)に関しても、第一生命は当初から参画しました。まずは“GFANZ”について教えてください。
太田:
グラスゴー金融同盟、つまりGFANZは、地球・経済活動全体の温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を掲げた、世界の金融機関による有志連合です。2021年、英国のグラスゴーで開催された気候変動枠組条約締約国会議「COP26」において、金融業界として気候変動に関する提言を行っていくために設立されました。
牧内:
GFANZの傘下には業態別のさまざまなアライアンスが存在しているんですよね。
太田:
機関投資家らアセットオーナーで構成される「NZAOA(Net Zero Asset Owner Alliance)」、銀行が集まる「Net Zero Banking Alliance(NZBA)」など、業態別に合計8つのアライアンスが存在しています。これらを束ねて金融業界全体としての取り組みをまとめているのがGFANZというわけです。各アライアンスに参加している金融機関まで全部含めると、GFANZは50カ国以上、約550の金融機関が参加する巨大組織となりました。
第一生命ホールディングス株式会社 第一生命保険株式会社 経営企画ユニット サステナビリティ推進室 フェロー 太田浩氏
牧内:
GFANZを構成するいくつかのグループの中で、第一生命の稲垣精二取締役会長が「プリンシパルズグループ」、太田さんが「ステアリンググループ」に所属しています。それぞれの役割について教えてください。
太田:
プリンシパルズグループはGFANZの意志決定や方針策定などを行っており、前イングランド銀行総裁のマーク・カーニー氏ら3人のGFANZのリーダーに加え、22のグローバルな金融機関のCEO、約4名のオブザーバーによって形成されています。ここに弊社の会長の稲垣が、設立当初からのメンバーとして加わっています。最初はアジアで唯一のメンバーでしたが、現在はシンガポール取引所(SGX)のCEOも名を連ねています。
牧内:
太田さんが参加しているステアリンググループは、プリンシパルズグループとどのようなつながりがあるのでしょうか。
太田:
GFANZでは、例えば昨年11月に公表した金融機関のネットゼロ移行計画提言書のようにさまざまな提言を行ったり、ペーパーを作ったりしていますが、実作業は専門家や実務家で構成されるワーキンググループ(ワークストリーム)が担っています。私たちステアリンググループでは、プリンシパルズグループで議論した事柄と、ワーキンググループが実務としてまとめていく内容をつなげる役割を担っています。
牧内:
GFANZ内でアジアはマイノリティに位置付けられてしまう面があるのは否めません。私自身、第一生命時代に太田さんの立場にいたとき、GFANZの他の国々にアジアの立ち位置を理解してもらうのに苦労した覚えがあります。太田さんは今、どのような課題や悩みを抱えていらっしゃいますか。
PwC Japanグループ サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス 執行役員 牧内秀直
太田:
地域ごとのネットゼロを達成していく上での課題は、地域の金融機関にしかビビッドに理解できません。例えば、アジアでネットゼロを達成するには、石炭火力発電の問題が重くのしかかっていますが、スイッチをオフにするように簡単にやめるわけにはいかないのも事実。しかし、欧州の金融機関にそのあたりの事情を肌身で感じてもらえていないのは悩みの種です。
牧内:
私がGFANZ担当だったときも、まさにアジアの石炭火力発電がホットトピックとなっていました。当時、痛感させられたのは、欧米中心で物事がどんどん進んでしまうということ。私の役目はアジアからの声を届けることなのに、意見を発信するにも実力が足りず、歯がゆい思いをさせられました。これを打破するには、日本で仲間を増やさなければならないと強く感じましたが、今、日本の金融業界においてGFANZやアライアンスへの取り組みが加速している感覚はありますか。
太田:
そこはありますね。プリンシパルズグループにいるのは弊社だけですが、ワーキンググループレベルでは日本のメガバンク、弊社以外の大手生命保険会社も参加してくださっています。また、金融庁や経済産業省、環境省の方たちもGFANZについてよく知ってくれるようになるなど、認識は確かに広がっています。
牧内:
そうしたアジア特有の課題を解決するためにも、アジアパシフィックネットワークである「GFANZアジア太平洋(APAC)ネットワーク(以下、APACハブ)」が立ち上がったのですね。
太田:
地域の金融機関が地域の課題を解決する場を作るべきだと、シンガポールの証券取引所SGXのロー・ブンチャイCEOや通貨当局Monetary Authority of Singapore(MAS)の長官であるラビ・メノン氏が中心となって、APACハブを作る動きが生まれ、シンガポールを拠点とする形で2022年6月に誕生しています。
牧内:
私がGFANZに関わっていたときは、シンガポールのMASやSGXが主導してAPACハブづくりを進めていたので、シンガポールの国家戦略的な側面があるのかと思って見ていました。ただ、APACハブの代表には、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)などで活躍された安井友紀氏が就任されました。これは日本にとって大きかったのではないでしょうか。
太田:
安井さんの肩書はマネージングダイレクターで、実質的な責任者として位置づけられます。日本の事情をよく理解し、日本の各金融機関に対してもアプローチをかけられる安井さんが責任者になったのは、非常に大きかったと思います。
牧内:
このAPACハブに関しては金融業界でも具体的な機能を知らない人も少なくありません。その活動内容についても教えてください。
太田:
大きく2つの方向が存在しています。1つはGFANZの活動をアジアで広めていくこと。GFANZは成り立ちからいって欧州、米国の金融機関が多く、アジアでは「GFANZなんて聞いたこともない」という金融機関が相当数に上っています。アジアでの参加金融機関を増やしていくべく、GFANZそのものを知ってもらうためにさまざまな取り組みを展開しています。
もう1つはアジア特有の問題への対応。石炭火力発電は最たる例で、こうした問題をどう乗り越えるかというアプローチ方法を議論していくのはもちろん、世界に対してアジアでの取り組み方をメッセージとして発信していこうとしています。加えて言えば、各国政府への提言も大きな役割の1つです。
牧内:
2023年6月にはGFANZの日本支部が立ち上がりました。その背景や狙いなどを教えてください。
太田:
日本はアジアの中でも、極めて大きな経済・金融の規模を持った国です。そうした国の金融セクターが、ネットゼロ達成に向けてさらに力を結集していくためのプラットフォームがあるといいねという話がAPACハブ設立後に出るようになりました。ちょうど2023年に、日本はG7広島サミットの議長国になりました。これを受け、政府が日本の金融機関の力を結集してネットゼロの取り組みを発信していきたいとの方針を打ち立てたことが推進力となって、日本支部が設立される運びになりました。
今年6月9日に各金融機関のCEOやNGOの方々、学識経験者らに集まっていただいて、日本支部に対する期待、発言すべき内容について議論しました。これが実質的なスタートでしたね。
牧内:
日本からやっていくべきことに関して具体的な中身が知りたいのですが、いくつかお話いただけますか。
太田:
日本は他のアジアの国々のように大規模な製造業――自動車や製鉄、化学などを抱えているだけに、アジア全体の課題である石炭火力発電の問題は日本も無関係ではありません。日本支部では製造業に大きな制約を与えることなく、ネットゼロをいかにして達成していくかを考え、その取り組み内容を世界に発信していこうとしています。
牧内:
日本支部が立ち上がるという話を聞いたとき、金融業界が集まって情報交換していくプラットフォームのような側面があるのだろうと勝手に想像していました。ただ、太田さんの話を聞くと、金融業界として具体的な課題解決を進めていくイメージですね。
太田:
はい。ここでもAPACハブのように2つの方向性があると思います。1つはGFANZのグローバルな活動を日本の金融機関に周知していくこと。これを「GFANZ to Japan」と呼んでいます。もう1つは日本固有の課題・日本固有のアプローチを世界に対して発信していく「Japan to GFANZ」。大変さを伴うのは後者の方ですね。世界中にいる金融機関のステークホルダーの信頼を裏切ることなく、日本の産業界に対して金融を提供してきた金融機関の役割も踏まえ、ちょうどいいバランスを見つけていかねばなりません。
牧内:
2022年11月、COP27がエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催されました。太田さんも参加されたそうですが、GFANZとしての手応えはいかがでしたか。
太田:
COP27で顕著になったのは、金融機関が現実的な認識を持つようになった点だと思います。ロシアによるウクライナ侵攻によってエネルギー供給が断たれ、ドイツなどでも一時的に石炭火力を立ち上げる必要性に迫られ、さらにエネルギー安全保障という概念が大きく取り上げられました。その中では「高排出の石炭火力を直ちに全面停止し、安い天然ガスなどに切り替えればいい」という単純な問題ではないとの認識が広まってきました。各国それぞれでエネルギー調達ルートが異なっており、産業を支える具体的なエネルギー源も石炭、天然ガス、原子力、再生エネルギーと出発点が違っているだけに、簡単に再生エネルギーだけに一気にシフトすればいい話ではないということをようやく理解してもらえている気がします。
牧内:
海外の金融機関が、話を聞いてくれるようになったと。
太田:
さらに移行ファイナンス(トランジションファイナンス)という言葉がよく登場するようになりました。単純に再生エネルギープラントだけを応援するのではなく、現状ではCO2を大量に排出しているけれども、「これではダメだ」と思っている企業、脱炭素に真剣に取り組みたいと思っている企業を、金融を通じて支援していくトランジションファイナンスが大事なのだとの認識が生まれています。
牧内:
新興国へのファイナンスという文脈でいえば、政府系と民間でリスクを分かち合うブレンデッドファイナンスに関してはいかがでしたか。
太田:
そこは半歩進んだという感覚です。民間金融機関だけ集まって新興国に融資しようとしても、リスクを全部取れるわけではありません。リスクをシェアしてもらえる公的セクターにも入ってもらう必要があるということで、世界銀行や各種開発銀行と一緒になってファイナンスをつけていくのは総論では全員が賛成しています。しかしながら、各国政府からの出資金で成り立つ公的セクターも、そう簡単にリスクが取れるわけではないので、どこまで公的セクターに入り込んでもらうのか、今まさに議論の真っ只中です。
牧内:
今、太田さんはどのような思いでGFANZの活動に向き合っていますか。
太田:
以前、日本銀行に勤務していた時期があるのですが、パリ支店にいたときにCOP21が開催され、いわゆる“パリ協定”が策定されました。ただ、当時は「社会貢献の延長でしょ?」といった感想を持った程度でした。第一生命に移った後、牧内さんからGFANZ担当を引き継ぎましたが、最初はネットゼロ実現に向けて金融業界が果たせる役割もよくわからないという状態でした。しかし、気候変動に初めて関わった人はほぼ同様の感想を持つと思うのですが、本格的に向き合っていくと「今のペースでは危険だぞ」と気付きました。現在は私の中では相当、切迫感がある状況になっていて、この先数年の私たちの取り組みが、地球全体の数十年後の未来を左右するという認識でいます。
牧内:
未来への思いをモチベーションにされているのですね。この活動はハードなので、自分でも気持ちが入らないとなかなか大変ですよね。
太田:
モチベーションという意味では、目線をどこに置くか、というのが難しいですね。本当に脱炭素を進めていくのであれば、高いコストをかけてでも炭素除去装置のようなものが必須ということかも知れませんし、電力も今と同じような価格では供給できなくなるかもしれません。となると、短期的には経済に下押しの影響をもたらす可能性も発生するでしょう。それでも中長期的な目線で考えて、敢えて今やらなくてはいけないこともあると思うのです。目線をどこに置いて事業を進めていくべきか。そこのところは日々、私も悩みながら取り組んでいます。
牧内:
私がGFANZ担当だったときは、グローバルな目線、日本の金融業界からの目線、そして第一生命という企業の目線を持っていました。企業人である自分が、どこを大事にするかというのは、本当に悩ましい問題でした。自分の所属している組織だけを考えているわけにもいかないですからね。
太田:
ただ、第一生命という会社だけに絞って考えると、そんなに悩ましいところはないかなと思っています。会社が言っている「well-being of all 全ての人に幸せを」というスローガンは気候変動対応に対して完全に合致していますから。ただ、海外子会社まで含めて考えると難しい。米国などは環境に関する意見が二分されている部分があるので、簡単に答えは出せません。上から目線で私たちが決めてしまうのではなく、多様なステークホルダーの理解や共感を得ながら少しずつ進めていくべきだと思います。
牧内:
最後に日本の金融業界の方々に伝えたいことはありますか。
太田:
ぜひGFANZというプラットフォームに参加していただいて、この先の未来を見据えて事業をともに考えていきましょう。数十年後も社会的に意味ある会社であり続けるきっかけとして、GFANZのプラットフォームを活用してください。
GFANZの日本支部では弊社の稲垣が議長となってコンサルテーティブグループ諮問会議を立ち上げる予定です。金融機関の枠を超えた多彩なメンバーを入れて議論を重ね、日本の金融機関自体の認識をアップグレードしていきたいと思っています。
牧内:
本日はありがとうございました。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}