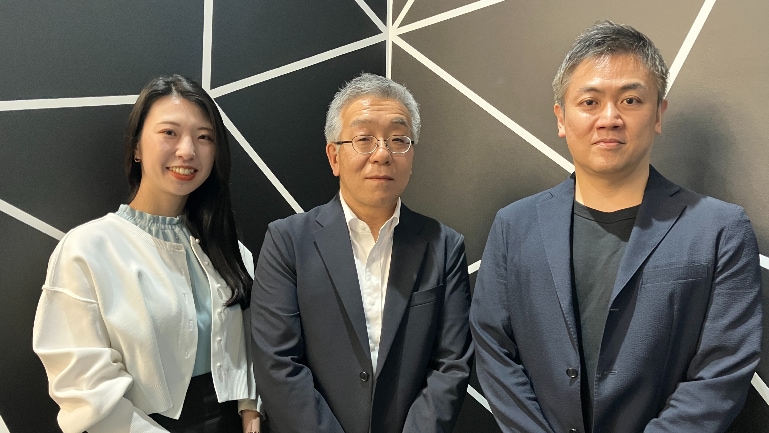{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
劇的な変化と不確実性に満ちた現代社会において、未来を切り拓いてきたトップランナーは何を見据えているのか。本連載では、PwCコンサルティングのプロフェッショナルとさまざまな領域の第一人者との対話を通じて、私たちの進むべき道を探っていきます。
第9回は、東北福祉大学総合マネジメント学部准教授でPwCコンサルティングの顧問も務める品田誠司氏と、PwCコンサルティングのパートナーで地域共創推進室をリードする金行良一、マネージャーの籾山幸子が、地域の実態に即した災害復興の在り方を議論しました。
※対談者の肩書、所属法人などは掲載当時のものです。本文中敬称略。
参加者
東北福祉大学総合マネジメント学部 准教授
PwCコンサルティング合同会社 顧問
品田 誠司氏
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 上席執行役員
金行 良一
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー
籾山 幸子
(左から)籾山幸子、品田誠司氏、金行良一
金行:地域共創推進室は、地域課題の解決、持続可能な実行体制の構築、それらを担う人材の育成を目指して活動しています。解決すべき地域課題にはさまざまなものがありますが、日本では特に避けて通れないのが、自然災害とそこからの復興という問題です。
品田さんは仙台市役所の職員として2011年に発生した東日本大震災を経験され、その後の経済復興に向けた取り組みで中核的な役割を果たされました。あらためて、発災当時の被災地はどのような状況で、どのような対応をされたのでしょうか。
品田:当日は通常の業務を行っていて、大きな揺れがあったため外出先から市役所に戻ったのですが、建物の損壊度が分からず中に入れない状況でした。その後は24時間体制で復旧に取り組むことになります。まずはどのように命を守るかから始まり、徐々に普段の暮らしができるようになっていったのですが、水道、ガス、電気などの社会インフラが元に戻るまでにはかなりの時間がかかりました。
私は主に食料を中心とした備蓄・物資の管理を担当し、仙台市の復旧が進むと特に被害の大きい他の自治体の支援にも対応しました。物資を必要なところに無駄なく分配するために苦心したことを覚えています。また、住居に関しては県との調整も必要になってきます。権限が県や市町村のどこにあるのかがまだ整理されていない問題も多々あり、各所とやりとりしながら何とかその場その場をしのいでいったというのが実態です。
東北福祉大学総合マネジメント学部 准教授 品田 誠司氏
金行:被災後の対応としては、発災直後、ある程度時間が経った後の復旧を行う時期、復興を行う時期といったように、フェーズごとに求められる活動が変わってくるのではないかと思います(図表1)。品田さんのご経験からは、それぞれのタイミングでどういった対応が必要になるとお考えですか。
図表:災害発生から復興にかけてのフェーズとアクティビティ
品田:やはり最初の段階では命を守る、安全を確保することが最優先になります。そのためには、災害の状況を的確に把握することが重要です。
同時に、大規模な災害の場合は避難所の設営も考えなければなりません。これは非常に難しい問題で、危機管理の観点では「避難所というものは立ち上げた瞬間からどのように閉鎖するかまで考えて行動しなければならない」と言われています。住民の避難状況は刻々と変わっていくため、それを把握した上で適切に物資を分配するといったオペレーションは、時間が経つにつれてどんどん難しくなっていきます。
その後、徐々に日常を取り戻していく段階になると、物資の適切な分配に加えて、水道、ガス、電気、道路などの社会インフラをどのように素早く復旧できるのかが課題になります。また、仮設住宅や恒久的な住宅の供給も並行して進める必要があります。
ここで重要になるのが、コミュニティをどうしていくのかという問題です。例えば津波などで面的に大きな被害を受けた場合は、住民全員に移転してもらわなければならない状況が発生します。そうなったときに、コミュニティをどのように維持するのか。若い方には若い方なりの考えもあるでしょうが、地域で支え合って生きてこられた高齢の方々は既存のコミュニティを破壊しないように集団で移転してもらう方法を考えなければなりません。
さらには、被災地の企業も当然大きなショックを受けていますから、復旧から復興へと進むにつれ、企業をどう支援していくのかも重要になってきます。
金行:復旧から復興へという段階になると、まちをどういう形で戻していくのか、震災前と同じ状態に戻すことを目指すべきなのか、あるいは新しくまちをデザインしなおすことが求められるのかといった議論も必要になりますね。
品田:おっしゃるとおりです。10年ほど前、多くの自治体が消滅可能性都市となることが話題になったように、地方の人口は減少しています。人口というのは一度減少し始めると、元に戻ることはなかなか難しい。そこに災害が起きると、若い世代や生産年齢人口の中核を占める方々が「危ないかもしれない」とその地を離れ、元々高齢化率が高かった地方で高齢化と人口減少がさらに進む可能性もあります。
そうした状況で、震災前と同じ形に戻すことが現実的に可能なのかという問題は、冷静に考えていく必要があるのではないでしょうか。
籾山:私も東日本大震災の被災地支援に半年ほど携わったのですが、その際にも震災後にまちをどうしていきたいかを地域の方々と一緒に考えて進めていくことが非常に重要だと実感しました。
品田:もちろん、災害がなければ普通に暮らしていた人たちの営みを元に戻すことが大前提であるのは間違いありません。しかし、神戸のような都市でさえも、阪神淡路大震災後は一時的に10万人の方が他の自治体に流出しました。10万人減った人口が毎年1万人ずつ戻って、元の人口に戻るには10年かかりました。神戸は震災前の時点で人口が伸びていたので最終的に元に戻りましたが、すでに人口減少と高齢化が進んでいるまちであればそうはいかないでしょう。
震災前にそのまちの人口動態や産業がどうだったのかを踏まえて、それをどのように戻すのが住民の方々にとって最も適切かということを十分に議論するべきではないかと思います。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 金行良一
金行:少し角度を変えますが、震災への対応においては、最新のテクノロジーを活用してできることも多くあるのではないかと考えています。復興支援の経験を踏まえ、テクノロジー活用についてはどのような留意点があると思われますか。
品田:テクノロジーの導入とその後に対して、どこまで責任を持てるのかが重要ではないかと思います。やはり被災地の現場は混乱していますし、そうした現場で動き続けている自治体職員は自身も被災者であり、非常に疲弊しています。そこに新しいテクノロジーを持ってきて「さあ使いましょう」と言ったとしても、自力では難しい。そこで民間企業の方々が「構築から住民への説明まで、全部引き受けます」と覚悟を持って言ってくれるのであれば、導入は可能かもしれません。
もう一つはマネタイズの問題です。復興の段階では無償で提供してもらえたとしても、その後維持していくための資金を自治体の予算として確保できるのかは大きなハードルになります。また、これは地域の産業をどう復興させるかを考える際にも重要です。例えば、震災後に被災地の地場産業や伝統工芸などを支援するクラウドファンディングが立ち上がることが多くあります。みんなの善意で、応援消費で復興を支援しようということ自体は間違いではないのですが、応援消費というものは基本的には時間とともに減少します。そうなった場合に売れ続けるにはどうすればいいのかというと、結局のところやはりイノベーションが必要という話に帰着するのではないでしょうか。
ですから、復興にあたっては身の丈にあったことができるのかを十分に考えなければなりません。伝統工芸を復興するにしても、以前のやり方でいいのか、付加価値の高い製品にシフトしていくべきなのか、あるいは今までの工程も含めて全般的な見直しを行った上で新たな産業として再生するのか、といった議論が求められると思います。
籾山:まずは被災前がどんな状態だったのか、現状はどうなのかを理解し、それを踏まえてどういった形に復興するのかを考えることが重要なのですね。
品田:被災地外から支援するにあたっては、経済学者マーシャルの言葉として知られる「Cool head but warm heart」のように、助けたいという強い思いと同時に、一歩引いて冷静に考えてもらうことも大切です。震災前と同じ状態に戻すだけでよいのか、あるいはそんな大きな冒険をしても大丈夫なのかなど、さまざまな角度からの冷静な議論が、その後の持続的な産業や生活につながっていくのではないかと思います。
金行:私たちコンサルタントは普段からロジカルに分析をするcool headは持ち合わせています。一方で、当然ながら被災地の現状を目の当たりにするとやはり心を揺さぶられてしまう。そうした状況でも、cool headを維持して冷静に現状を捉え、何をすべきかを相手の立場に立って考えながら、なおかつwarm heartで熱量を持って取り組む。この2つは、私たちが地域共創推進室を推進していく上でも非常に重要な要素だと感じました。本日はどうもありがとうございました。
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー 籾山幸子
{{item.text}}

{{item.text}}