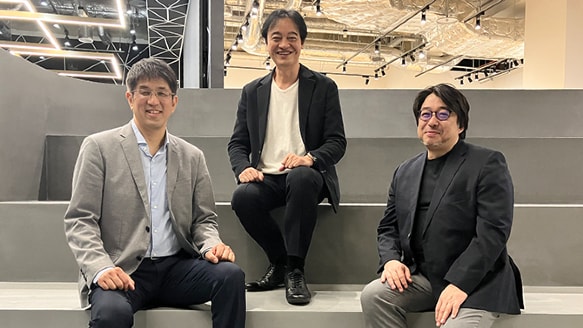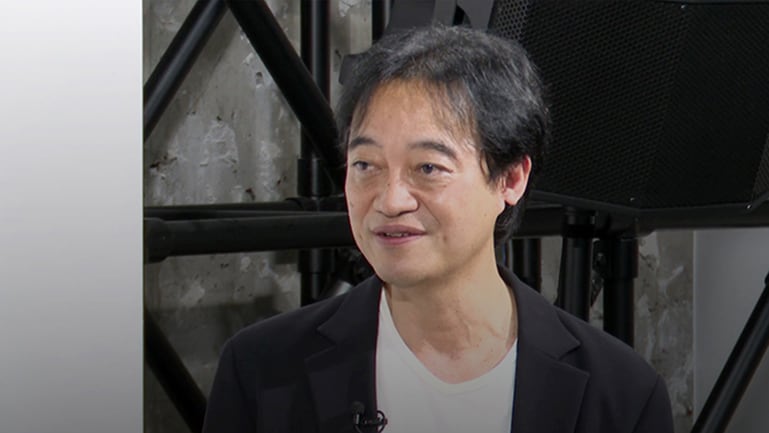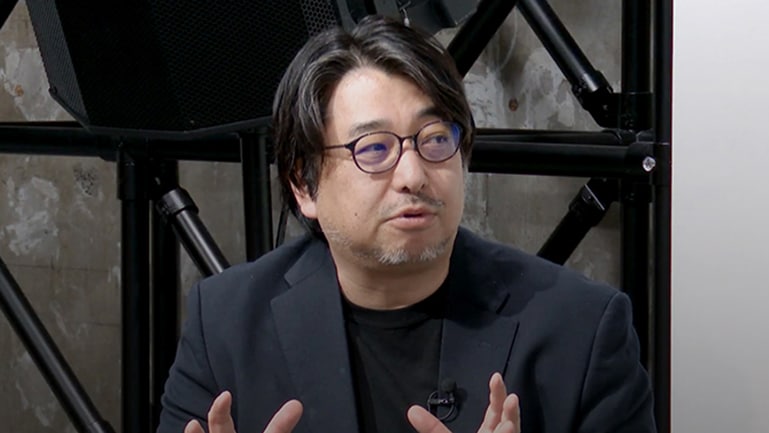{{item.title}}
{{item.text}}

Download PDF - {{item.damSize}}
{{item.text}}
劇的な変化と不確実性に満ちた現代社会において、未来を切り拓いてきたトップランナーは何を見据えているのか。本連載では、PwCコンサルティングのプロフェッショナルとさまざまな領域の第一人者との対話を通じて、私たちの進むべき道を探っていきます。
第10回は、宇宙工学を起点に社会システムにも工学の考え方を適用するシステムズエンジニアリングを専門とする慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 白坂成功氏を迎え、PwCコンサルティング合同会社で宇宙・海洋・新エネルギーなどの産業成長テーマを推進するパートナーの渡邊敏康、サイバーフィジカルシステムを活用したビジネス支援に携わるシニアマネージャーの南政樹が、システムズエンジニアリングの発想に基づいた価値創出と課題解決の方法について議論しました。
※対談者の肩書、所属法人などは掲載当時のものです。本文中敬称略。
参加者
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
白坂成功氏
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
渡邊敏康
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー
南政樹
(左から)渡邊敏康、白坂成功氏、南政樹
渡邊:本日のテーマはシステムズエンジニアリングですが、まず私が理解するシステムの考え方を示させてください(図表1)。情報システム、マネジメントシステム、機械システムなどさまざまなシステムがありますが、いずれも「インプット」「プロセス」「アウトプット」「フィードバック」からなり、アウトプットとして何らかの付加価値を生み出すものがシステムであると考えます。
図表1:「システム」における「インプット」「プロセス」「アウトプット」「フィードバック」のサイクル
例えば地上から宇宙までを眺めてみると、信号機やカメラ、ドローン、衛星などからのデータがインプットとしてあり、それらのデータが3次元空間情報基盤と連携するところがプロセス、サービスとしてユーザーに価値を提供するのがアウトプット、というサイクルを回すシステムと捉えることができます。
近年、こうしたシステムは多層化、多様化し、それぞれのサイクルが複合的に関わりあうようになってきています。このように複合的なシステムを構築していく際に、システムズエンジニアリングという方法論が必要になってきますね。
白坂:はい。システムの本来の定義は、複数のものが相互に作用して1つのかたまりをなすもの、ということです。すなわち、ビジネスもシステムであり、組織もシステムであり、あるいはスマートシティのような街そのものもシステムであるということになります。システムズエンジニアリングは、こうした複数の要素で構成されるシステムを実現するために複数の専門分野を束ねるアプローチ・手段です。
このようなアプローチは、トランスフォーメーションを起こす上で重要になってきます。図表2に示すように、目的と手段、その間をつなぐ仕組みというシステムがあるとき、デジタル技術の進化によって手段が増えていけば、いままでにない仕組みが可能になり、いままでにない目的が実現できるようになります。これがトランスフォーメーションです。その実現の仕組みを構築する際に、システムズエンジニアリングが必要になります。
図表2:デジタル技術を活用したトランスフォーメーション
渡邊:システムが複合的になってくると、どこまでを対象とするのかが問題になりますね。
白坂:そのとおりです。対象を俯瞰的に見てどの範囲で捉えるのかによって、最適な設計が変わってきます。Society5.0では、「サイバー空間とフィジカル空間を融合させたシステム」で「人間中心の社会」を実現することを目指しています。これはすなわち、複数のシステムからなるSystem of Systemsと言えます。
こうしたシステムの設計においては、これまでのように個々のシステムごとの個別最適ではなく、システムを横断する人間のジャーニーに沿った全体最適が必要になります。病院のシステムを例にとれば、現在は病院、薬局、そこへの移動に利用する交通手段と、3つのシステムが別々にデザインされているわけですが、「人間中心の社会」ではこれらを横断的に利用するユーザーのジャーニーに沿って3つのシステムを接続して運用する必要があります。病院での診察を予約すると、予約時間に間に合うように車が迎えに来る、その間に渋滞に遭ってしまったら自動的に予約時間が調整される、診察が終わったら車で薬局へ向かい待ち時間なしで薬を受け取れる、といった具合です。
このように複数のシステムが連動することで、社会構造のレイヤー化が進みます。そうなると、産業をどのようなレイヤー構造にするのか、何を競争領域とし、何を協調領域とするのかもシステムズエンジニアリングの設計対象になってきます。既存産業のうち競争せず共通化できるところはプラットフォーム化し、それをテクノロジーに任せる部分と人がカバーする部分に分ける。例えばフードデリバリーなら、「注文を受ける」「料理を作る」「配達する」というタスクに分けた上で、飲食店にとって競争領域ではない「注文を受ける」「配達する」部分はプラットフォーム化し、注文はテクノロジーに任せ、配達は人がカバーする、といった形です。
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 白坂成功氏
こうしたレイヤー化が進むとともに、設計対象範囲の変化ということも起きています。マサチューセッツ工科大学のヴェック教授らの説明を用いると(ヴェック他(2014)『エンジニアリングシステムズ:複雑な技術社会において人間のニーズを満たす』慶應義塾大学出版会)、電気自動車を社会に実装していくには、電気自動車自体の技術的な設計だけでなく、発電や充電の仕組みといったインフラ、さらには法制度や税制、政策なども含めてシステムの対象とし、俯瞰的に設計する必要があります。これまではハードウェア・ソフトウェアのデザインと法律や税制の策定は別々に行われていたわけですが、それをトータルで最適な形に設計するために、システムズエンジニアリングが求められることになります。
渡邊:そういった観点からさまざまなシステムを「地球のシステム」「宇宙のシステム」として俯瞰して捉えると、相互の関係性や目的、ものの見方が変わってくるように思います。
自動車で言えば、インプット、プロセス、アウトプットとして俯瞰して整理しなおすと、「目的地まで移動したい」というインプットが、「自動車」という個別システムの「走る、曲がる、止まる」というプロセスを経て、「目的地に近づく」というアウトプットに至る。さらに俯瞰すれば、「モノを運びたい」「人が移動したい」「安全な交通社会でありたい」というインプットが、自動車を含む広範なプロセスを経て、「荷物を届ける」「目的地に向かう」「事故をなくす」というアウトプットが出てきます。
地球上のいろいろなシステムについて、このように俯瞰と具体化をすることで、新たな価値が見えてくるのではないでしょうか。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 渡邊敏康
南:先ほどの電気自動車の話であれば、技術や法制度に加え、「何をしたいか」というユーザーの意思や目的まで含めて考えると、さらにアウトプットが変わってきますね。そう考えると、地球のシステムであろうと、宇宙のシステムであろうと、人が作ったものがつながりあって、人の役に立つ価値を生み出すという原理は共通なのではないかと思います。
地球や宇宙といった観点で新しいシステムを作り出すという取り組みは、進んできているのでしょうか。
白坂:そこまで視野を広げてシステムを設計しているケースはまだ非常に少ないです。どこをオープンにし、どこを競争領域にするかといった産業の設計は一企業ができることではなく、政府規模で取り組まなければなりません。米国ではNIST(国立標準技術研究所)がスマートグリッドや宇宙防衛などのアーキテクチャの設計に関与してはいますが、まだまだこれからです。
渡邊:システムを俯瞰したり具体化したりする視点を養うには、どのようなことが必要でしょうか。
白坂:私はよく自転車の漕ぎ方に例えるのですが、漕ぎ方の説明を聞いただけでは漕げるようにはなりません。システムの分析や設計も方法論はありますが、実際には経験して慣れていかないと身に付かない。
とはいえ、いくつかコツはあります。1つはコンテクスト分析と呼ばれるもので、対象とするシステムの範囲と外部との関係性を考えることです。どこまでを自分たちの設計対象の範囲にして、どこからを外部との関係性(=コンテクスト)にするかが、俯瞰するときの重要な要素になります。もう1つは、ユースケースをどう捉えるかです。使用後に廃棄するのか、リユースするのかといったユースケースの違いによって、製品の設計は変わりますし、それが生み出す価値も変わります。そして最後は意味俯瞰、すなわち、何のためにそれを作るのか、です。
何のために、何を、どう実現するのか。この3軸でシステムを捉えて設計していくことを何度も繰り返して体験すれば、システムズエンジニアリングの視点を実装できるようになると思います。
渡邊:私たちがコンサルティングワークでWhy・What・Howを設定することと共通しますね。
白坂:加えて、前提となる環境条件が変わる、ということも考慮しなければなりません。コロナ禍は大きく環境を変えましたし、ウクライナやイスラエルの情勢も同様です。変化が起きる前と後では環境条件がまったく異なるので、設計計画も変わるはずです。いかに変化に対応しやすい設計をしておくか、あるいは変化に対応できる仕組みを設計の中に入れておくか。それによって、そのシステムを活用できる期間や提供できる価値のレベルが変わってくると思います。
渡邊:全体を俯瞰すべきところとボトムアップで見るべきところを行き来することが重要だとあらためて感じます。地球規模で捉えたシステムや、デジタルとフィジカルの融合を設計する上でも、そうした両軸で考えていくことに引き続きトライしていこうと思います。
本日はありがとうございました。
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 南政樹