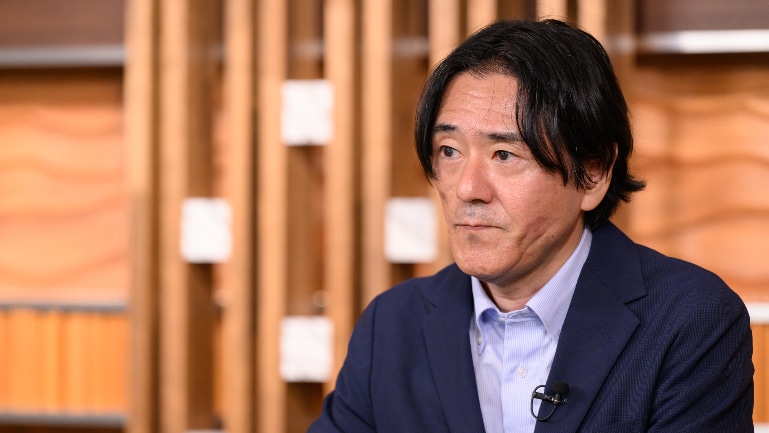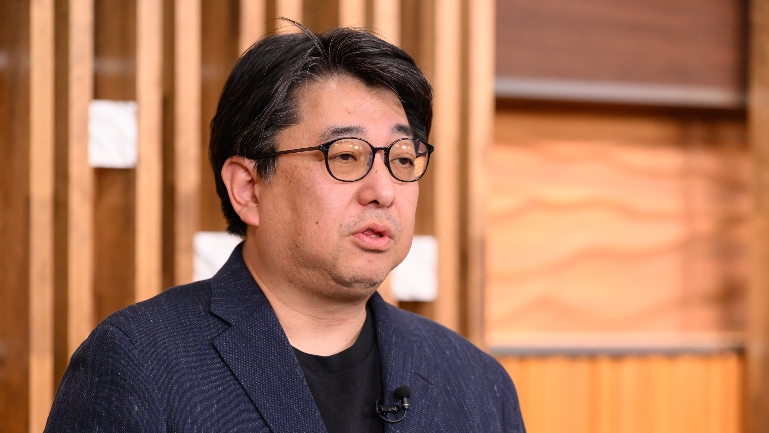{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
PwCコンサルティング合同会社のTechnology Laboratoryは最先端テクノロジーを社会実装し、実現したい未来をつくっていく組織です。宇宙・空間産業の創造といった活動もその1つです。Technology Laboratoryの概要や、宇宙・空間産業を支える最先端テクノロジーの動向を解説します。
登壇者
PwCコンサルティング合同会社
Space Industry Forum
PwCコンサルティング合同会社
パートナー 執行役員
岩花 修平
PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー
井上 陽介
PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー
南 政樹
岩花:Technology Laboratoryでは何を目指しているのか。今、注目されているロボティクスや生成AIといった先端テクノロジーは、将来の人々の生活や社会を大きく変えていくポテンシャルがあります。ただ、待ち構えていれば達成できるものではありません。実現したい未来を見通すところから始め、解決すべき社会課題を定義し、それらに対応するテクノロジーを明らかにした上で、技術開発のシナリオを描くといったアプローチが必要です。
そのためには政府や地方公共団体、先端技術を開発・保有する研究機関、事業化の知見を持つ企業が連携することでテクノロジーをより有効に活用でき、実現したい未来に近づくことができます。さまざまな分野で活躍する人々を結び付け、議論を活性化する役割を担うことを目的として、2020年7月にTechnology Laboratoryを設立しました。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 岩花 修平
特徴は、PwCのグローバルなプロフェッショナルサービスネットワーク、各法人が有するさまざまなラボ(研究組織)と連携しながら、先端テクノロジーに関する幅広い知見を活用できることです。また、製造や通信、インフラ、ヘルスケアなどの各産業・ビジネスに関する豊富なインサイトを有しており、これらの知見と未来予測・アジェンダ設定を組み合わせ、企業の事業変革や大学・研究機関の技術イノベーション、政府の産業政策を総合的に支援しています。
Technology Laboratoryの活動の一例として高速サービス開発があります。さまざまな知見を活用したアイディエーションから、ビジネス戦略の策定、デモやPoCによる仮説検証、社会実装に必要なチーム形成/実行まで一連の流れを一貫で実施するものです。こうしたプロセスを高速に回しながら何度も繰り返すことで、高精度でより確実なサービス、ビジネスづくりを支援します。
そして、Technology Laboratoryではマーケットへのインパクトが大きく重要度が高いと推測したテクノロジーに注力。例えばビジネスへの影響や実現性を分析し、最も重要なテクノロジーとして、AIやドローン、ロボティクスなどに取り組んでいます。
今後のビジネスインパクトが大きくなると推測しているテクノロジーの1つが宇宙・空間情報です。空間情報、モビリティの2つの軸でチームのメンバーが最新トレンドを解説します。
井上:「宇宙×空間ID」の動向についてお話しします。まず、宇宙から得られる空間情報にはどのようなものがあるのか。衛星データで得られる気象(降水量、気温など)や大気(CO2、気流など)といった情報や、地形、土地被覆、地殻変動、植生活性度、海面(水温、海流など)、位置情報、時刻情報も宇宙から得られる空間情報です。
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 井上 陽介
今後の衛星打ち上げの計画については、温室効果ガス・水循環観測技術衛星や先進データ衛星、準天頂衛星の7基体制が予定されています。衛星の打ち上げ、小型衛星コンステレーションなどにより、データ取得頻度の向上や高度化が見込まれます。そして、AIを活用したデータ解析技術も進展しており、宇宙から得られる空間情報の充実により未来が変わろうとしています。
衛星データを活用したユースケースでは、農業、森林・林業、エネルギー、環境、防災・災害対応、インフラ監視、金融・保険といったさまざまな領域で活用が進んでいます。例えば農業では農地面積の把握や発育・収穫高の推定などで活用。森林・林業は森林の伐採や森林火災の検知、エネルギーでは太陽光発電や洋上風力発電の最適化、環境ではCO2排出量の算出にも衛星データが使われています。
井上:衛星データ以外にも3次元都市モデルや人流データなど、地上で取得する地理空間情報を組み合わせて使っていくことが重要です。その際、必要な空間情報がどこにあるのか効率的に検索・活用できる仕組みが欠かせません。
その仕組みの1つとなるのが空間IDです。空間IDとは3次元の空間を一意の参照点として立方体(ボクセル)型の各領域に対してIDを付与するための共通ルールとなるものです。地理空間情報はさまざまな規格があるので、共通ルール化された空間IDを使うことにより、このエリアにはどんな空間情報があるのか、検索・統合が簡易に行えるようになります。空間情報や衛星データを活用する基盤として空間IDの普及・促進を図っていきたいと考えています。
空間情報の活用に向け、政策や課題の意思決定のための情報を提供するGEO-Intelligence(GEOINT)が注目されています。GEOINTは元々米国における軍事の政策決定で使われてきましたが、空間IDとさまざまな空間情報を紐づける基盤になると考えています。日本におけるGEOINTはこれから検討されますが、防衛以外にも、防災などの公共や民間の活用を中心とした展開が見込まれています。衛星データと空間情報を組み合わせた活用法が増える一方、情報を取捨選択して分析することが重要になります。
そうした取り組みに向け、GEOINTの全体ビジョンとアーキテクチャの設計や、空間IDなどによる連携技術と基盤構築、空間価値の分析・データ化、ビジネスにつながるユースケース構築といったところにPwCコンサルティングの提供価値があると考えています。
南:2025年の大阪万博では空飛ぶクルマが注目されそうですが、ドローンや空飛ぶクルマなどの次世代空モビリティがいよいよ社会実装されるフェーズを迎えています。街中の上空をドローンや空飛ぶクルマが飛行するレベル4の実現により、物流や点検をはじめ各分野でドローンの利活用拡大が期待されています。
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 南 政樹
空モビリティの利点はさまざまあります。まず、空を飛ぶことで地上の渋滞・混雑を回避できます。また、山間部や離島など地形的に移動が難しい場所でも、地形や地物の状態に依らない柔軟な経路の選択が可能です。
空モビリティは電動のため人の移動に伴う環境負荷の低減や、シンプルな構造のためメンテナンス性が高いという利点もあります。さらに垂直離着陸が可能なため、離着陸場所の制約が少なく、街中のコインパーキングなどのスペースを活用できる可能性もあります。そして自動・自律飛行によるパイロットの省人化と業務効率化が可能です。
次世代空モビリティには多くの利点がある一方、実は解決しなければならない課題があります。例えば、地上の通信インフラをベースに飛行を制御する現在のやり方に起因するさまざまな制約がその一つです。現在の5Gなどのモバイル通信は地上に電波を送受信する基地局があり、その基地局から上空のドローンや空飛ぶクルマと通信しています。残念ながら現在のモバイル通信のインフラは人口カバー率、人口の割合に応じて整備されています。問題は、空飛ぶクルマが飛行する経路とモバイル通信インフラの整備状況のミスマッチにあります。通常、航空機は地上リスクを避ける観点で、あまり人がいない場所を飛ぶことが検討されます。また山間や海上をショートカットして移動できることが地上の交通インフラに依存しない利点でした。にもかかわらず、こうした場所は通信インフラが整備されておらず、結果として飛ばせないといった事態を招く恐れがあります。そのため、空モビリティのための空の通信インフラを整備する必要があるといった議論が始まっています。
NASA(米国航空宇宙局)では、大型・小型の航空機、ヘリコプター、空飛ぶクルマ、ドローンなどの種別に応じた空域をスペースとして割り当てるトラフィックマネージメントの研究を行っています。こうした仕組みを実現するためには、どの空域をどんなモビリティが飛んでいるのかといった情報を把握し、適切な状態を維持する必要があり、宇宙・空間産業のインフラになる可能性があると見ています。
非地上系ネットワークや空間ID、空間情報の解説がありましたが、将来はこれらの先端テクノロジーが統合され、空モビリティの運航支援環境が構築されるようになります。システムは別々のものではなく、システムが相互につながるSystem of Systemという形で全体像が作られ、宇宙・空間産業として新しいエコシステムが創出されるのです。空モビリティによるビジネスの広がり、それを支える空のインフラに向けた取り組みを進めてまいります。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}