
PwCコンサルティング合同会社は2025年2月からセミナーシリーズ「人的資本経営の新たな潮流を紐解く」を開催。第1回目は「人的資本経営」をテーマに、株式会社みずほフィナンシャルグループのグループCHRO人見誠氏をお招きし、PwCコンサルティングのパートナー出崎弘史とディレクター土橋隼人がそれぞれの知見を共有しました。
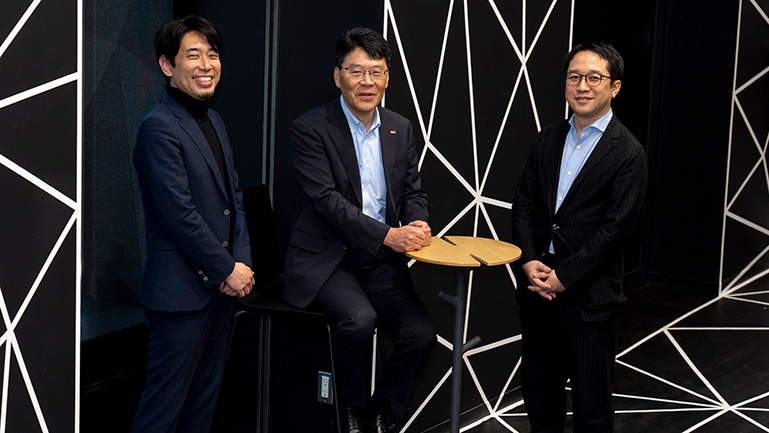
(左から)出崎 弘史、人見 誠氏、土橋 隼人
日本企業の人的資本情報開示の現状と課題
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 土橋 隼人
国内における人的資本経営の動きは大きく二つに分けられます。一つは経営戦略と連動した人材マネジメント・人的資本投資を行うこと、もう一つはその取り組みの内容や効果・課題を広くステークホルダーに開示していくことです。国内外でCSRD(企業サステナビリティ報告指令)/ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)などの規制やガイドラインが整備されつつあり、そのなかには外部保証が必要になるものもあるなど、各社は対応を迫られている状況です。
人的資本開示への関心が高まっているのは良い状況ではあるものの、ことさらに独自性のある指標の開示を追求することなどにより、ややもすると「開示のための開示」になってしまっていたり、経営文脈での議論が不在で人事の中だけに閉じた「人事のための開示」になってしまっていたりしないでしょうか。本来行うべきことから手段と目的が混同されている懸念があります。
実際、私たちがご支援をする中で、CHRO(最高人事責任者)の皆さんから、機関投資家からさまざまな指摘を受けているという声を聞きます。例えば「御社は非常に多くの施策を実施されていますが、施策の羅列感があります。人的資本のページにはビジネスの言葉があまりでてきていないので、何を実現するために行っているのか分かりません」といった声や、「多様性を拡大すると御社のビジネスにとってどういう効果があるのですか。取り組まないことでどんなリスクがあるのですか」といった具体的な質問を投げかけられるケースも増えています。
私たちが日本企業の統合報告書を分析したところ、2023年時点で人的資本領域の開示内容は「施策紹介型」が依然として多数を占めていることが分かりました。この類型は、施策は幅広く紹介されているものの、ビジネスとのつながりが十分に語られていない状況です。加えて、注目すべきは「パス明示型」の開示を行っている企業がわずか2.4%に留まっていることです。「パス明示型」とは、人的資本の注力テーマ・施策とアウトカムの関係性を、間の経路も含めて明示するアプローチであり、私たちがより目指すべき形だと考えている類型となります。
また、テーマ別の開示率を見ると、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)や人材育成、健康経営、エンゲージメントといった従業員全体の状態を高める取り組みの開示率は高い一方で、リーダーシップのパイプライン(38%)、人材ポートフォリオ(30%)、組織文化(24%)といった事業戦略実現において重要なテーマと考えられる開示率は低い傾向にあります。
私たちは日本企業の開示における課題を以下のように整理しています。
- 経営・事業戦略と人事施策の関係性が示されていない
- 経営・事業戦略実現のキーとなる人材の定義や充足状況の開示が不足している
- 組織文化や関係性に関する開示が不十分である
- 会社側からの視点中心での開示になっている
- 施策のアクティビティの状況紹介が中心で、効果に関する開示が少ない
こうした課題に対して、私たちPwCコンサルティングでは「人的資本インパクトパス」のフレームワークを活用し、人事施策が経営・事業戦略のどのテーマの実現のために行われているのか、人事施策→人材・組織の変化→企業活動→財務価値というつながりを通じて可視化することを提案しています。これによって「経営目線」で「未来起点」の開示が可能になるのです。
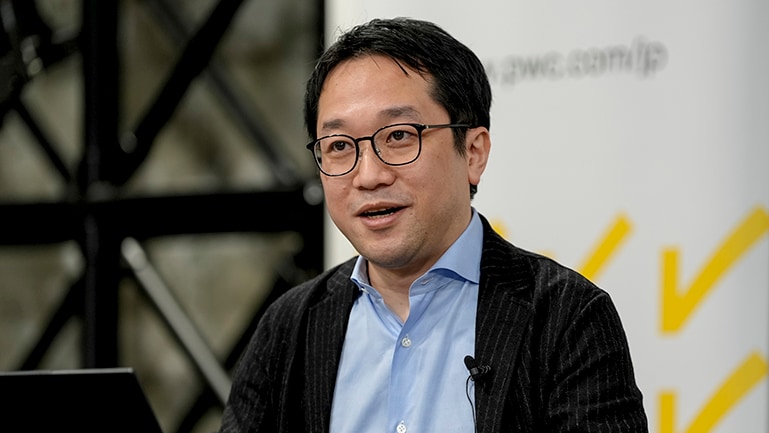
PwCコンサルティング合同会社 土橋 隼人
みずほの人的資本強化・開示の取り組み
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCHRO 人見 誠氏
みずほフィナンシャルグループは、150年の歴史を持つ総合金融グループとして、約6万5000人の社員を抱えています。人見氏は、社内の人事施策と情報開示の取り組みを紹介しました。
みずほでは2年前に中期経営計画を策定する際、企業理念を再構築し、将来のあるべき姿と現在取り組むべきことを明確にしました。この計画では、フォーカスすべきビジネス領域と、それを支える経営基盤(人的資本を含む)を定め、パーパス(企業の存在意義)を土台としています。
人的資本に関しては、<かなで>という人事の新しい枠組みを導入しました。<かなで>は社員との対話を通じて策定され、社員と会社が共に成長できる人事を目指しています。特に重要な変革として、①グループベースでの人事制度の統一、②年功序列から役割・成果に基づく処遇への転換、③人事部主導からビジネス部門や社員の自律を促す方向への転換を実施しました。
人的資本の情報開示については、3年間で段階的にアップデートを行ってきました。初年度はストーリー性を持たせた開示、2年目は<かなで>を中心とした人的資本KPIの設定、そして3年目には人的資本インパクトパスの導入により全体のつながりを体系化しています。
人的資本KPIでは、エンゲージメントスコアとインクルージョンスコアを重視し、中期経営計画の主要目標として設定しました。現在はこれらのスコアが60を超え、取り組みの成果が出始めていると感じています。また、注力領域ごとにKPIを設定し、その進捗を定期的に追跡しています。
人的資本インパクトパスでは、足元の取り組みがパーパスにどうつながるかを示すとともに、中間のマイルストーンを置いて、ビジネスサイドから見た目指す姿と社員から見た目指す姿を言語化しています。
さらに、70ページに及ぶ人的資本レポートを発行し、統合報告書では語りきれない詳細なデータや取り組みを紹介しています。外部からは「詳細で分かりやすい」という評価がある一方、「情報量が多い」という声もあり、いかに分かりやすく伝えるかが今後の課題だと考えています。
人見氏は、情報開示の進化には機関投資家との対話が重要な役割を果たしたと述べています。例えば、「戦略とのアラインメントが弱い」「社員がどう受け止めているのか見えない」「課題とその対応策も示すべき」といった指摘を受けて改善を重ねてきました。
今後の展望としては、「ビジネスとのアラインメントをさらに明確にすること」と「わかりやすく伝えること」の両立に取り組むとしています。

株式会社みずほフィナンシャルグループ 人見 誠氏
人的資本経営を実現する統合型情報基盤
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 出崎 弘史
人的資本経営を実現するための統合型情報基盤について、テクノロジーの実装ステップをお話しします。情報統合基盤の構築にはIT投資や作業負荷、費用がかかりますので、まずは各企業のHRIS(Human Resource Information System)全体像を把握することから始めるケースが多いです。
HRISは大きく4つの領域に分けられます。これはシステムが4つあるという意味ではなく、コンセプトとして4つのエリアに分類できるということです。
- EX(Employee Experience)プラットフォーム:従業員のエンゲージメント向上に寄与するもの
- タレントマネジメントプラットフォーム:人材育成・配置に関わる機能
- HRオペレーションプラットフォーム:人事・給与・勤怠など基幹業務をサポートするシステム
- データドリブンHRプラットフォーム:人的資本経営を実現するための情報統合基盤
情報統合基盤を構築する前に、各領域のIT特性をしっかり理解することが重要です。メインユーザーは誰なのか、どのようなベネフィットを享受するのかといった点を整理した上で、情報統合基盤を考えていく必要があります。
実際に、情報統合基盤を構築する際には、誰のビジネスに寄与するのかを考え、最終的なベネフィットとそれを導くための人事施策を組み合わせながら要件を決めていきます。具体的には、機能やデータの持ち方(個人データか集計データか)、カバー範囲(グループ会社全体か)、データの種類(構造化データか非構造化データか)といった要件を定めていきます。
さらには、量的マテリアリティと質的マテリアリティの解消に分け、テクノロジープラットフォームを検討することが有益です。人的資本経営を実現する情報統合基盤は、主に量的マテリアリティに対応するデータドリブン型HRプラットフォームになる傾向があります。
実際の情報統合基盤の事例としては、(1)パブリッククラウドベースで非構造化データの分析に特化したもの、(2)パブリッククラウドベースで構造化データの分析に特化したもの、(3)SaaS形式で情報統合とアプリケーション機能を兼ね備えたものなど、さまざまなアプローチがあります。
情報統合基盤の要件が決まった後も、その効果を確実に出すために考慮すべき点があります。
- 将来像・テーマの設定:どの領域にターゲットを絞り、今後どこに展開させるか
- ゴール状態の定義:定量的なゴールを設定し、ステップバイステップでプランニングする
- 展開プランの策定:利用ユーザーの拡大と業務適用(データ活用度)の両軸で段階的に進める
最後に、情報統合基盤構築の成功要因として以下の4点を挙げたいと思います。
- トップダウンとボトムアップのバランスを取った推進
- テーマの選択と集中
- 従業員のデータリテラシー向上と推進体制の確立
- 目的に応じた情報プラットフォームの整備
人的資本経営を実践する上で、HRIS全体を棚卸し、要件を決め、システムの周辺環境も考慮しながら、ストーリー性を持たせて実装していくことが重要です。

PwCコンサルティング合同会社 出崎 弘史
ディスカッションでは、グループ内の異なるシステムやデータ形態をどう統合するかという課題に対して、「アップデートが継続的に行われているか」「属人的でないか」といった点が重要だという指摘がありました。また、「理想は一つのデジタルプラットフォームで全てを実装することだが、各企業のITリテラシーやビジネスへの寄与度を考慮し、まずは『できるところから』始め、無駄な投資にならないよう将来像を見据えたアプローチが必要」との見解が示されました。
本セミナーを通じて、人的資本経営・情報開示においては、単なる「開示のための開示」を超え、事業戦略とのつながりを明確にし、実効性ある取り組みとしていくことの重要性が浮き彫りになりました。


