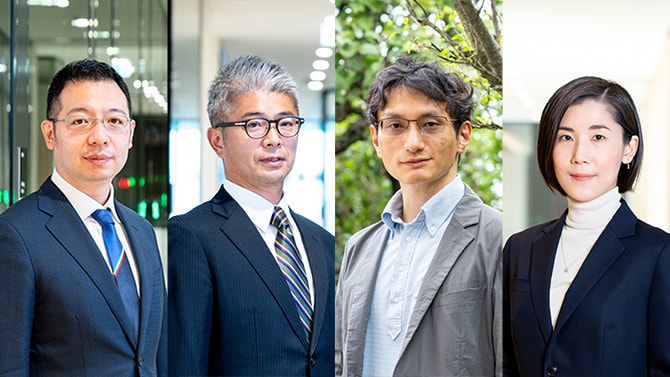{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2021-12-02
参加者
東京大学経済学部教授
東京大学マーケットデザインセンター・センター長
小島 武仁氏
PwCコンサルティング合同会社
公共事部 デジタルガバメント統括 パートナー
林 泰弘
PwCコンサルティング合同会社
Strategy& シニアマネージャー
大塚 悠也
PwCコンサルティング合同会社
公共事業部 マネージャー
古屋 智子
※本文敬称略
※法人名・役職などは掲載当時のものです。
(左から)大塚 悠也、林 泰弘、小島 武仁氏、古屋 智子
大塚:後半では、古屋が現場で職務を遂行する過程で体験した具体的ケースから議論を進めさせていきたいと思います。古屋はPwCコンサルティングの公共事業部門に所属し、児童福祉分野を専門としております。
古屋:ご紹介ありがとうございます。つい最近のことですが、児童福祉分野における制度や仕組みの問題で壁にあたりまして、ぜひ小島先生にアドバイスをいただきたいと考えています。
小島:はい。どのような壁でしょうか。
古屋:現在、児童虐待の通告窓口が法律によって複数に分かれています。その結果、重大さが異なる案件が相談しやすい機関に集中してしまうという現象が起きています。市町村で対応した方がよい緊急性の低い相談が児童相談所にまわってきたり、反対に児童相談所に相談すべき急を要する案件が、接点があるという理由だけで市町村に来てしまったりといったことが頻繁に発生しているのです。
そこで通告窓口を一元化して、内容による振り分けルールをつくり、どの機関が対応すべきかを決めていくという実証実験を行うことになりました。それぞれの相談受付機関に寄せられた案件を持ち寄って、ルールに則って振り分けをシミュレーションするというものです。
結果、不具合や違和感がぼろぼろと噴出することになりました。違和感の原因は、「ルールに従ったところAになったが、直感的にはBじゃないか」、もしくは「想定通りBになったが、本当に対応できるか不安でいっぱい」というような、ルールそのものや、振り分け結果に対する納得感のなさです。
新たな制度をつくる際、ルールと結果に対する納得感がない場合はどうするか。解決方法についてアドバイスをいただきたいです。
小島:私が話を聞く限りですと、非常に見込みがあると思います。最初のルールをPwCにて試験的につくられたとしても、各機関の方々からフィードバックを得られますし、ルールを改変してまた試すことができるわけですよね。児童相談所や市区町村が納得する振り分けを目的関数にするということであれば、いわゆる機械学習的なアプローチにも適しているはずです。データや結果について、都度、職員に評価してもらう時間はかかりますが、それ以外は自動化して稼働できる典型的な事例ではないでしょうか。
古屋:初期段階では違和感があることが当たり前で、納得できるまでルールを変えていけばよいのですね。当事者である児童相談所や自治体と、しっかりと話し合いをする機会を設けるのも重要なことだと理解しました。一方で、私たちはルールを設計する役割を担うものの、当事者ではありません。どこまで介入してよいかという悩みもあります。
小島:少し話を拡大すると、最終的な目的の設定や、それに対する合意が難しいということなのかもしれません。目的がクライアントである児童相談所と自治体の納得感なのであれば、当事者に聞いてアップデートしていくことが最善です。しかし、問題は当事者が本当は何が最善か分かっていない状況もあり得るということです。実は制度設計を行う際に、その手の問題は往々にして起き得ます。
大塚:クライアントワークである限り、クライアントの満足を最大化させることがよいことだと考えてしまいそうですが、公共制度の設計ではそうとも言い切れません。児童相談所の事例では、小島先生ならどのような目標を最大化させますか。
小島:最終的には子どもの死亡事故を防ぐなど、子どもにまつわる問題を解決することが大事だと思います。そしてそのためのデータとリサーチ方法をデザインすることが重要だと考えるでしょう。ただ実際に子どもたちの実情を知っている方が、理解が深い事柄もある。児童相談所に相談が集中するとリソースがひっ迫して効率が下がるというようなケースもあるでしょう。そのため、当事者と慎重にコミュニケーションしながら進めるべきだと思います。
また、長期的に制度設計ができる余裕があるのであれば、ランダムに使えるデータ、使えないデータなど、さまざまなデータを数年間かけて検証できないか相談します。つまり、目的関数を決める前に、何を目的関数に設定すべきか検証できるように体制を整えるということです。
東京大学経済学部教授 東京大学マーケットデザインセンター・センター長 小島 武仁氏
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 公共事業部 デジタルガバメント統括 林 泰弘
大塚:確かに、制度をつくる際は何を目的にするかが非常に重要ですね。しかも、その目的や最善の解決策について、当事者が理解していない場合もあり得ると。そのような場合には、まず何を目的関数に据えるか検証できるようにする必要があるということですね。
小島:はい。同時に制度運営者がルールを理解しているかを確かめることも大切です。自治体の担当者がそもそもなぜそのルールがつくられたのか理解していない、もしくは勘違いしているという事例は少なくありません。そのような場合、マッチング対象が不幸になります。
例えば、保育園の選定作業では、現状ほとんどの自治体に共通した類型があります。ある園を第一希望とする保護者の人数が定員に収まっていれば、全員その園に入園させる。定員を超えていれば、点数に応じて順番に入園させる。最終的に入れなかった人は第二希望の園に割り振るというものです。一見、すごく直感的な仕組みで公平に見えるのですが、マーケットデザインの専門家の間では評判が非常によくありません。
なぜかというと、まず本当に入園させたい人気の高い保育園を正直に書くと落ちると考える保護者がいて、安全策であえて第三希望を書く。そうなると変な読み合いになり、本当は入園できたはずなのにできないという不幸が起きます。自治体側からすると、本当の希望がデータから読み取れない。そういった事柄に気づかずに仕組みを使ってしまっているのが、そもそも問題というケースがあり得るのです。
林:児童福祉分野の話に限らず、さまざまな制度設計に悩みを抱えていらっしゃる自治体は多いです。その中のひとつに地域内での消費を活性化させたいというものがあり、域内ポイントや地域内通貨といったアイデアを検討していますが、これについてはどうお考えですか。
小島:地域内通貨をつくる技術的なハードルは下がっていると思いますが、通貨が流通する単位をあまり細かくすると利便性が下がる可能性があり、そうすると望ましいとは限りません。地域内のもっと魅力的な何かを見つけ出す、あるいは隣の大きな街と協力する方法を考えるなど、しっかりと制度を検討すべきですね。
林:まだ解決策は見つかっていませんが、同じような悩みを抱えている自治体は少なくありません。マーケットデザインなど経済学の知見を取り入れた自治体経営支援というのも、今後PwCで構想していきたいことのひとつです。
小島:児童福祉分野や自治体経営という話題は今日、はじめて相談を受けたので非常に新鮮です。過去に私が興味を持った課題としては、養子縁組などがあります。マッチングが非常に難しく、児童福祉分野などと共通性があるかもしれません。
古屋:日本の養子縁組にはハードルがいくつかあります。特別養子縁組だと、夫婦が揃っている、かつ子どもは原則15歳までという年齢制限などがあります。経済力があっても、独身の方々は養子を迎えるという選択肢をなかなか選ぶことができません。一方で、規制も強力です。日本の場合、民法で戸籍上の親の意見が強く反映されます。それも、養育力や経済力がある方々が養子を迎えることをためらうハードルになっています。
仮に規制がハードルになっていてマッチングがうまくいかないという場合、規制の範囲内でマッチングのルールを変えることに注力するのか、もしくは規制そのものに意見表明していくべきか、小島先生はどちらの対処が望ましいとお考えですか。
小島:とても月並みな答えになると思いますが、“ケースバイケース”ですね。ただ最近のマーケットデザインの潮流の一部では、制度的な制約は昔の人が考えていたように簡単に変えられない、そのため与えられた条件として捉えて、変えられるところから対処していくことが望ましいという認識が共有され始めています。
古屋:何か具体的な事例がありましたらご教示いただけますか。
小島:マーケットデザインの大きな成功事例のひとつに、臓器交換ネットワークがあります。これは、自分の家族から腎臓などの臓器提供を受けたい人、血液型の問題などで適合しない場合に、違う家族をペアとしてあてて交換できるようにする仕組みです。米国ではすでに実装されていて、年間約1,000人の臓器交換が実現しています。
臓器交換ネットワークは2005年前後に始まったのですが、当時、一部の経済学者の間では評判がよくありませんでした。そもそも問題は臓器売買禁止という規制にあるため、法律を改正すべきだという趣旨です。ただ臓器売買に関する反対意見は非常に大きく、法律の改正は現実味がありません。結果としては、規制の枠組みの中で解決方法を考えたことが、少なくない命を救うことにつながりました。
他の問題でも規制のコストを主張していくことは大事だと思います。一方で、規制を尊重したまま、できることは何かと発想することもとても重要です。臓器移植など変えることが難しい規制であればその範疇で考え、容易に変更できる規制に対してはコストを測る指標をつくって主張していく。ケースバイケースというのは、そういった意味合いです。
古屋:二者択一というよりも、問題によって戦略を変える柔軟性が大事ということですね。養子縁組の問題でいえば、もうひとつ問題があります。前提条件が折り合う人同士を探すのも大変ですが、親になる人の希望もあれば、子どもの希望や意見もある。さらに、人間は時によって要望が変わることがあります。そのような変化するマッチング対象がマーケットデザインの枠組みの中に入ってくるときに、個人の要望はどれくらい考慮されるべきでしょうか。
小島:これは本当に難しい問題です。子どもは確固とした意見が確立していないことが多く、年齢によって考え方も変わります。自治体の話題で出てきた、当事者自身が必要なもの、好むもの、目的が実は分かっていない場合どうするかという問題と共通点がありますね。
米国にいた頃、養子縁組のマッチングに関する研究に取り組んでいる学生から相談を受けたことがあります。彼らは個人の要望よりも、客観的なアウトカムを重要視していました。例えば、養子に行って戻ってきたかどうか、どのくらいの期間で戻ってきたかなどのデータをアウトカムメジャーとして採用していました。
古屋:アウトカムメジャーについてもお伺いしたいのですが、成功よりは失敗に近い話やデータを集めた方が制度設計をするうえでは有用なのでしょうか。
小島:成功・失敗のデータは裏返しで本質的に同じものなので、どちらでもよいと思います。というか、成功例か失敗例のどちらかだけを見るのではなく、両方とも見て比較することが大事です。例えば教育問題であれば、一般的にテストの点数や大学に進学したか否かを観察することが多いと思いますが、虐待や貧困などの問題を抱える家庭の子どもは進学率が低いことが多いため、母集団が小さすぎて、同じデータを検証する効果はあまりないかもしれません。逆に10代の妊娠やドメスティックバイオレンス、もしくは20年後の収入や犯罪歴のデータなど長期的スパンのネガティブなデータと関連づける方が、マッチング対象の幸福度を上げるために有用かもしれません。いずれにせよ、個人の幸福+客観性という物差しでデータの種類を選び、マッチングアルゴリズムに利用していくことが重要だと思います。
古屋:どのような種類のデータであれ、個人の幸福に関連する客観的なアウトカムデータをバランスよく組み合わせていくことが重要という指摘は非常に参考になりました。児童福祉や養子縁組などの社会課題に対してアルゴリズム的なアプローチを取れるという新しい視点を得られたと感じています。行政実務は定型的な業務やデータ収取・管理が基盤にある業務が多いので、DXとの相性はもともと良いと感じていました。ここでマーケットデザインを取り入れると、地域に暮らす当事者の満足度や納得度が上がるという意味で、行政の質が高まるのですね。
PwCコンサルティング合同会社 公共事業部 マネージャー 古屋 智子
大塚:科学的なフィードバックを得ながら制度をテストしブラッシュアップしていくというのは非常に前向きな取り組みなのですが、日本ではなかなかそういう動きにならないという実感があります。一方で、米国ではそのような発想が文化として根づいているのでしょうか。マーケットデザインの活用からも、そうした両国の違いが浮かび上がってくるような気がします。
小島:日本ならではの問題はあるとも思いますが、私自身はそれほどネガティブには捉えていません。どの国も通らなければならない道があると思っているからです。先進国にはいずれも硬直化した仕組みやしがらみはあります。現在、米国でマーケットデザインが受け入れられている理由は、硬直した仕組みや制度に対する批判的な認識が20~30年前からすでにあり、改革への努力が長らく行われてきたからです。
私は2003年から2008年まで学生としてハーバード大学に在籍していましたが、当時はニューヨークの学校選択制度が改正された時期で、そこにマーケットデザインの知見が取り入れられました。臓器移植ネットワークの発足も2005年前後です。共通するのは、どちらにもきわめて大きな抵抗があったこと、そして、抵抗に対し圧倒的な労力を使ってひとつひとつ説得していった人たちがいたことです。日本が特殊というより、米国とは単純に問題に向き合ってきた歴史の積み重ねが違います。
大塚:確かに、日本はデジタルガバメントの進展が遅れていると指摘されていますが、問題意識を持ち始めたのが遅いだけと考えるとポジティブに考えられますね。
小島:私自身は日本で活動することになって、日本の現状にポジティブな印象を受けることが増えています。米国から日本に帰ると言った時、周囲はすごく心配していました。研究環境がよくないといううわさはもちろんですが、私の目的である社会実装にも日本社会は興味がないはずだと考えられていたからです。ただ実際に日本で活動をしていると、耳を傾けてくれる人は少なくありません。マーケットデザインに興味を持たれる方もたくさんいらっしゃいます。興味の段階からどう具体的に実行に移すか。日本はそんな節目に差し掛かっているように思います。
大塚:デジタル敗戦という言葉に象徴されるように、問題意識を持ち、まさに変革を行おうという機運が高まっているため、これを契機に科学的なアプローチを取り込んだ公共領域のデジタルトランスフォーメーション、デジタルガバメントを皆で推し進めていくことが必要ですね。デジタルガバメントの実現に向けて、マーケットデザインの知見をどう取り入れていくか、具体的な現場の課題も含めて議論させていただきました。経済学とコンピューターサイエンスの力を応用した新たな制度設計や、硬直化した仕組みの中でどのように最適解を見つけていくかなどについて、示唆に富むお話をたくさん伺うことができました。本日はありがとうございました。
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー Strategy& 大塚 悠也
PwCコンサルティング合同会社
公共事業部 デジタルガバメント統括
パートナー
大塚 悠也
PwCコンサルティング合同会社
Strategy& シニアマネージャー
古屋 智子
PwCコンサルティング合同会社
公共事業部 マネージャー
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}