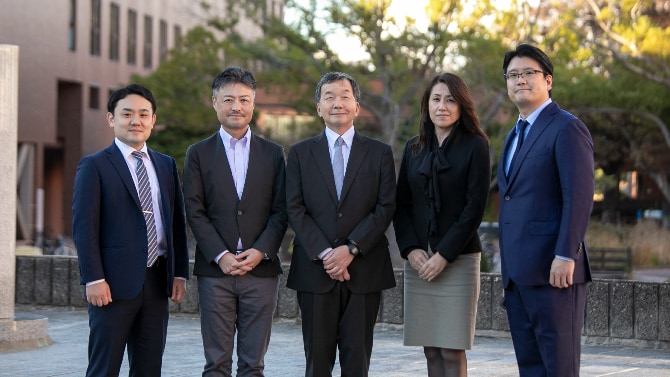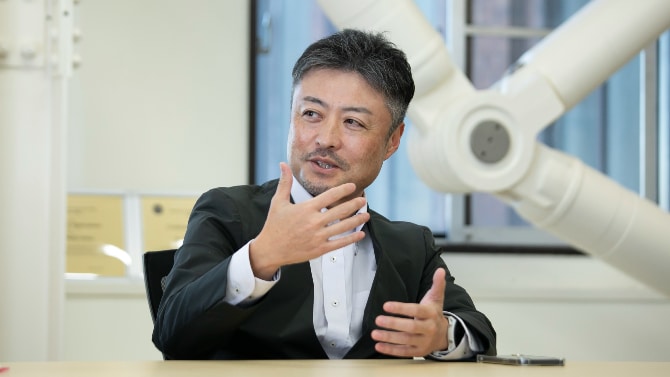{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
デジタル庁が2021年9月に発足し、政府・自治体も含めた社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が本格化しています。しかしながら、いくつもの課題が露見し、その歩みは鈍いのが現実です。PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)は自治体DXを実現するための取り組みの1つとして、筑波大学と「デジタル広域連携」の共同研究を進めています。ではデジタル広域連携、そしてその先にはどのような意義や可能性があるのでしょうか。学術機関、自治体職員、民間企業という異なる立場の有識者たちが、それぞれの視点から日本におけるDXの目指す姿や方向性について語り合いました。
参加者
筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授
大澤 義明氏
つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略監
中山 秀之氏
潮来市 市長公室 企画政策課 課長
河瀨 由香氏
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
渡辺 将人
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー
斎藤 達也
※本文敬称略
※法人名・役職などは掲載当時のものです。
左から)斎藤 達也、中山 秀之氏、大澤 義明氏、河瀨 由香氏、渡辺 将人
渡辺:
私と斎藤はPwCコンサルティングの公共事業部に属しており、中央省庁や地方自治体、独立行政法人などをクライアントとしてさまざまなサービスを提供しています。
DXは今やビジネスの世界で聞かない日はないくらいですが、日本で使われるようになったのは2004年頃からのことで、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」を発表し、一気に広がった印象があります。
大澤先生の専門は都市計画やまちづくりですが、日本のDXの現状や自治体DXの在り方についてお聞かせいただけますでしょうか。
大澤:
私がDXに携わるようになったのはモビリティからです。自動運転の時代に入り、車はセンサーの塊となり、収集したデータを都市計画にどのように活用していくかという共同研究から始まりました。
DXの「D」がデジタルで、「X」がトランスフォーメーションになりますが、日本は「D」は強いんだけれど、「X」がうまくいっていない。学校の教科であれば理科は5段階評価の通知表の5だけれど、社会が2か3というところです。技術が先行して、社会システムが追いついてないというのが実態ではないでしょうか。
私は、DXのテーマは「人づくり」と「まちづくり」の2つだと考えています。
デジタル化が進むことによって、人がルーティンワークから解放され、時間ができて、色々なアイデアを練ったり、クリエイティブな作業をしたりすることに時間を費やすことができるようになります。そして、自由な発想や自発的な行動を促すことが、「人づくり」への貢献となります。
一方「まちづくり」では、DXは横串を通す役割だと考えています。先ほどのモビリティを例に挙げると、交通を制御するだけではなくて、医療や教育、観光を組み合わせることで、色々な地域サービスの価値を生み出すことができるようになります。デジタルの力で、既得権の温床となっている縦割りの在り方や体制を見直せることが、「まちづくり」への貢献だと思います。
筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授 大澤 義明氏
つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略監 中山 秀之氏
渡辺:
DXの考え方は組織によって異なりますし、個人によっても異なると思います。つくば市と潮来市それぞれのDXの現状や方向性をお聞かせください。
中山:
つくば市は「つくばスーパーサイエンスシティ構想」を発表し、2022年4月にスーパーシティ型国家戦略特区に指定されています。最先端の技術を使って都市の課題や市民の困りごとを解決して、よりよい持続可能社会を作るというもので、これがDXの1つと捉えていいかと思います。
ただ、何でも技術先行でいいかというと、一概にそうでもありません。市長は「技術は、そこから一番遠い人の困りごとに必要だ」とよく言っています。簡単に言うと「高齢者がスマートフォンを使えますか」という話になりますが、技術を単に押し付けるという発想ではなく、新しい技術によって「選択肢を増やす」ことをコンセプトにしています。
例えば、大澤先生にご協力いただいて、インターネット投票の実現に取り組んでいます。家から出られなくて投票に行けない人たちに「インターネット投票という選択肢がありますよ」と呼びかけたいと思っています。もちろん、紙の投票用紙がよければその選択肢があっていいと思います。
もう1つ大事にしているのは、課題ドリブンといいますか、現場で直接お話を伺うことです。課題だと思っていたものが、実は課題じゃなかったということがあります。例えば、つくば市内の子どもであっても、隣の市の小学校の方が圧倒的に近い場合もあります。その場合に、よかれと思い、越境できるような方策がないかと考えていたところ、実は親御さんとしては少し遠い学校でも、つくば市で教育を受けさせたいと考えていることが分かったという事例があります。
先ほどの高齢者とスマートフォンの話でも、持ってはいても使いこなせていない高齢者向けに教室をオープンしようとしたら「分かっている人に上から目線で教わるのは嫌だ」という声を拾うことができました。英語に置き換えると私もその気持ちがよく分かります。教わるときにあまりペラペラやられると抵抗がありますよね。
「友達感覚で『これってどうやって操作するんだろうね』っていうのが一番楽しい」と聞きました。教わるよりも、楽しく学ぶことができる場を作ればいいと分かり、それを打ち出したところ大きな反響をいただきました。
スマートフォンを学んで、メッセンジャーアプリで家族とやりとりするとかウェブ会議アプリでお孫さんと話すなど、これもコミュニケーションの選択肢を増やすことですよね。楽しみながらデジタルに触れる機会を増やして、身に付いていくのがいいかなと考えています。
河瀨:
潮来市は企画政策課の中にDX戦略室を作ることを宣言し、実際に2023年4月1日から設置されました。できたばかりのDX戦略室です。
デジタル庁が推進している「誰一人取り残されない」社会の実現を目指し、民間から人を受け入れてDX推進計画の策定をしているところでして、どのような改革が必要か、調査や検討に取り組んでいます。
DX推進とはいえ、やはり人と人が接する、対面で会う、話すということが大事であり、“田舎ならではの温かさ”という部分は残してきたいとも思っています。市民に抵抗なくスーッと、いつの間にかデジタルが静かに浸透していくようなスタイルを目指していきたいですし、そこがDX戦略室の腕の見せ所になると思っています。
潮来市の民間人材は1名、兼業という形で月の半分くらいを市役所で働いています。本業はシステムエンジニアですが、職員の目線とレベルを合わせて、業務をもっと効率化できないかリサーチしたり、積極的に提案したりしてくれています。例えば、生成AIを活用した実証実験も、議事録の作成も、まずは無料トライアルの範囲でやってみるなど、身の丈に合った、背伸びをしないDXを一生懸命考えてくれています。
役人は堅物なので、これまでのやり方を変えるのは簡単ではありませんが、「こうすれば業務を効率化できて、これだけ残業を減らすことができます」など、費用対効果を見せながら上手く掛け合ってくれるので、とても助かっています。
先ほど高齢者とスマートフォンの話がありましたが、高齢者といっても一括りにはできませんし、役所が「スマートフォンを持つように勧める」というのも違うと思っています。申請手続きが便利になるなどのメリットはありますが、全てがデジタル化されてペーパーレスでいいとも思えません。人が介在していいところもあるはずで、目指すべき将来像の中で見極めることのできる職員でありたいと考えています。
渡辺:
私たちはデジタル庁と仕事することが多く、そこで掲げられているミッションが「誰一人取り残されない、人に優しいデジタルを。」ですが、最初はかなり理想的なイメージがありました。しかし、お聞きしていると「選択肢を増やす」「身の丈にあったDX」というような、それぞれの取り組みが分かり、どうしたら現実的に実現できるか考える上でとても勉強になります。
潮来市 市長公室 企画政策課 課長 河瀨 由香氏
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 渡辺 将人
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー 斎藤 達也
渡辺:
筑波大学とPwCコンサルティングは、2021年から「デジタル広域連携」をテーマに共同研究に取り組んでいます。地方では過疎化、都市部でも少子高齢化が進んでいますが、デジタルの力を活用した地域間連携により行政やサービスの標準化を進められれば、こうした課題をより効率よく解決できるのではないかと考えています。
斎藤:
これまで広域連携というと、どうしても近隣の自治体との連携が多かったと思います。しかしデジタルを活用し、地理的な制約に依存せずに自治体同士が連携できるようになれば、同じような課題を抱える自治体が共通の行政サービスを利用することで、人材と財源の面でより効率的に解決に向けて取り組めるのではないかと考えています。また、行政サービスを効率化することができた分、各自治体の職員は個別の課題に集中できるようにしたい。これがデジタル広域連携の考え方であり、私たちは共同研究の中で検討や実証を進めてきました。
渡辺:
大澤先生は学術的な目線で、デジタル広域連携を推進していくための意義をどのようにお考えでしょうか。
大澤:
1つ目として、デジタル広域連携により相手の選択肢が格段に増えることがあります。つくば市に隣接するのはせいぜい10市町村程度ですが、全国が対象となると市町村の数は1,700を超えます。また、デジタルですから距離のハードルはなくなります。
隣同士のような近い地域での連携ですと、例えば水害や地震などの防災の面から見ると、支援が必要なタイミングが重なってしまいますが、遠方だからこそ助け合うことができる場合もあります。
2つ目としては、自治体間の共創の促進が期待できます。教育分野で言うと、多くの学校でデジタル化が進むと、受講生が少ない教育にも個別に対応できるようになります。例えば、数学Ⅲや地学のような専門性の高い科目にも、教師を手当てすることが可能となります。
共創により、課題ドリブンで同時に多くの自治体で解決を図っていくことができる。その意義は大きいと思います。
渡辺:
多くの自治体にとって課題解決の糸口になり得るデジタル広域連携ですが、後編では、日本全国にデジタル広域連携を広めていくためのアプローチについて、お聞きしたいと思います。
{{item.text}}

{{item.text}}