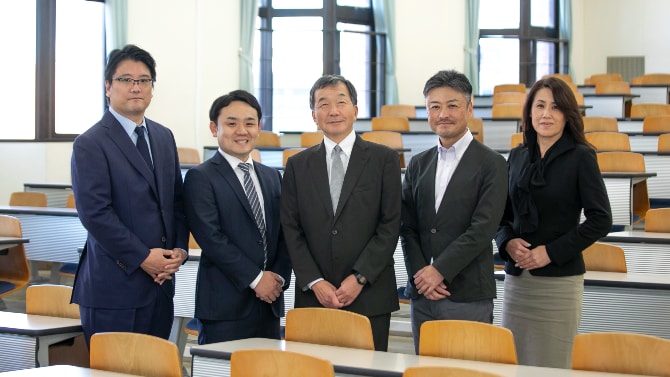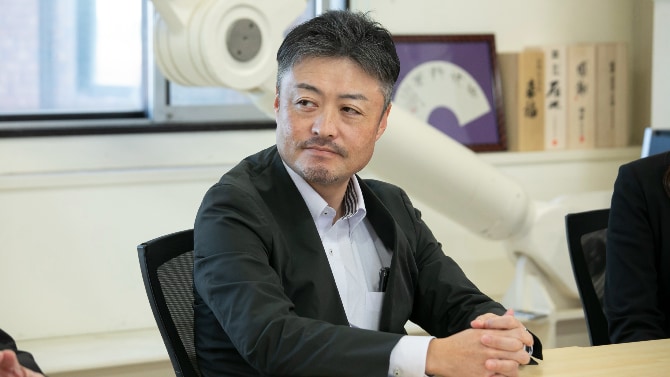{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)は自治体DXを実現する取り組みの1つとして、筑波大学と「デジタル広域連携」の共同研究を進めており、デジタル広域連携の先にある「行政サービスで稼ぐ」ビジネスモデルを提唱しています。自治体DXの意義や可能性について議論する座談会の後編では、学術機関、自治体職員、民間企業という異なる立場から、デジタル広域連携への思いや実際に行政サービスで稼ぐために何が必要かをそれぞれの視点から議論しました。
参加者
筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授
大澤 義明氏
つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略監
中山 秀之氏
潮来市 市長公室 企画政策課 課長
河瀨 由香氏
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
渡辺 将人
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー
斎藤 達也
※本文敬称略
※法人名・役職などは掲載当時のものです。
左から)渡辺 将人、斎藤 達也、大澤 義明氏、中山 秀之氏、河瀨 由香氏
渡辺:
前編では、つくば市と潮来市のDXの取り組みをご紹介いただいた上で、デジタルの力を活用することで地域間連携による行政やサービスの標準化を進め、社会課題の解決を目指す「デジタル広域連携」の意義についてお聞きしました。
デジタル広域連携について、筑波大学とPwCコンサルティングは教育分野で共同研究に取り組んでいますが、実際に現場で話を聞くと簡単な話ではないことが分かりました。地域単位のルールや文化の違いもありますし、人材不足もあります。
教育に限らず、日本全国にデジタル広域連携を広めていくには、どのようなアプローチがいいでしょうか。
大澤:
まず求められるのが標準化や統一化だと思います。教育であれば日本全体として推進しなくてはいけませんが、ここで障害となるのがシステムです。D(技術)は強いけれどもX(トランスフォーメーション)がうまくいっていないという状況を変えていくためにも、標準化・統一化が重要なのです。
また、異質なものの価値を認めるという視点も不可欠です。これが非常に大切になります。皆がいいと思うものよりも、異質なものを受け入れ、そこに価値を見出す。ここに社会を変えていく可能性があります。
近隣ではなく、離れた自治体と連携していく方が良いでしょう。よく知っている人よりも知らない人同士の方が、予想できない面白い化学変化を引き起こせる可能性が高いと思います。
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 渡辺 将人
筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授 大澤 義明氏
つくば市 政策イノベーション部 スマートシティ戦略監 中山 秀之氏
潮来市 市長公室 企画政策課 課長 河瀨 由香氏
渡辺:
最初は分からなくても、いったん受け入れて、そこに価値を見出す。異質とのぶつかり合いにより、イノベーションが期待できます。ぜひ、官公庁でも挑戦していきたいですね。
では、実際の現場ではどうでしょうか。中山さん、河瀨さん、それぞれの目線でご指摘いただけますでしょうか。
中山:
地域によって得意、不得意があって、リソースの偏りもあります。デジタル広域連携によってそれを補完し合うことで、都会でも田舎でも変わらない生活ができるのではないかと思います。
その1つとして、現在、つくば市と長野県茅野市で医師をシェアリングするようなことに取り組んでいます。茅野市は小児科医が不足しているのに対し、つくば市は医師が多い。そこで、24時間365日スマートフォンで医師と相談できるアプリサービスを利用して、つくば市にいる医師が遠隔対応し、茅野市の子育て環境を改善できるのではないかと期待しています。
河瀨:
潮来市でも、デジタルのない広域連携はすでにいくつか行っています。観光面では利根川を挟んで千葉県香取市と連携していますし、サイクリングによるまちづくりプロジェクトでは霞ヶ浦周辺の自治体と連携しています。現在、広域連携で実施しているレンタサイクルの仕組みは、土浦市や霞ヶ浦市で自転車を借りても潮来市で乗り捨てることが可能です。しかし、予約方法は利用者による手書き申請や電話であり、乗り捨てられた後の自転車回収ステーション間も全て電話・ファックスでやりとりしています。これをデジタル化すると、便利になるとは思います。そのほか、広域連携バスも走らせていますが、システムが一本化されれば遅延情報が分かるようになるなど、デジタル化の効果は大きいと思います。
ただ、デジタル化すると言っても標準化が足りていないのが実情で、それぞれの環境や考え方に左右されます。他の地域からデジタル連携を求められても、今はまだ、足並みを揃えることは難しいのではないかとの懸念が先行してしまいます。
斎藤:
共同研究ではICT教育を普及させたい学校をマッチングして、先生方にオンライン上でコミュニケーションできる場をセッティングしたり、オンライン勉強会を開催したり、事例・ノウハウを共有したりしてきました。
デジタルを活用して地理的な制約を超えることで、自治体間で行政サービスを融通できる機会は増えると思います。つくば市と長野県茅野市の取り組みもその適例ではないかと思います。
大澤先生もおっしゃっていましたが、標準化できるところは標準化し、異質な部分は認め合って、その自治体特有の強みとなるサービスをどんどん伸ばしていくべきと思っています。
そのサービスを磨き上げていって、他の自治体のニーズとマッチすれば、将来的には対価を受け取ること、いわゆる「行政サービスで稼ぐ」というビジネスモデルもありえると考えています。自治体DXのその先の未来として、私たちとしても積極的に支援を行っていきたいです。
渡辺:
「行政サービスで稼ぐ」というのが私たちの注目しているキーワードで、単純にコストをかけて行政サービスを提供するのではなく、行政サービスで稼いで、それをまた投資していくモデルです。このモデルの日本での可能性について、大澤先生はどのようにお考えでしょうか。
大澤:
大いにあり得ると思いますし、そうあるべきです。ここで大事になるのが、今まで東京起点だった地方の創生と活性化を、現場起点で行うことです。
その地域ならではの強みを引き出すには、全国共通ではなく、地域性に応じた現場の発想が欠かせません。先ほど話があった「楽しく学べるスマートフォン教室」や「静かに浸透するデジタル化」も現場起点だと思います。この方向性の先に、「行政サービスで稼ぐ」モデルの実現が期待できます。東京をトップにしたヒエラルキーからの転換が必要です。
渡辺:
「行政サービスで稼ぐ」まではいろいろなステップやハードルがあって、まずは東京、すなわち中央起点から脱却し、自治体が主体となる現場起点が求められるわけですね。
現場でなければ分からないことを、課題ドリブンで自治体が対等に意見やアイデアを出し合い、解決に向けて共創していく。今日のお話を聞いて、そのような形が望ましいと分かりました。私たちもデジタル広域連携、さらにその先の「行政サービスで稼ぐ」ビジネスモデルの実現に向け、自治体の皆さまの変革を支援できればと考えています。
本日はありがとうございました。
PwCコンサルティング合同会社 マネージャー 斎藤 達也
{{item.text}}

{{item.text}}