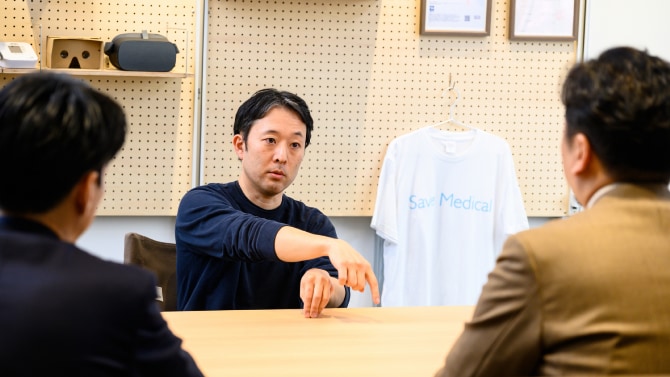{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
医師や看護師などの医療従事者、最新の知見や技術を持つ研究者、医療政策に携わるプロフェッショナルなどを招き、その方のPassion、Transformation、Innovationに迫るシリーズ「医彩」。第14回は株式会社Save Medical 代表取締役社長の淺野正太郎氏をお迎えしました。
淺野氏は株式会社リクルートに新卒で入社。米シリコンバレー駐在でVC拠点の立ち上げと国内外のデジタルヘルス投資・事業開発に従事した後、株式会社日本医療機器開発機構(現サナメディ)に参画し、2018年に100%子会社として株式会社Save Medicalを設立しました。デジタルヘルス分野で、疾患に対する治療介入を提供するデジタルセラピューテクス(DTx)におけるフロントランナーの1人である淺野氏に、DTxの現状や、異分野から参入したからこそ見えるDTxの意義や課題などを伺いました。
株式会社Save Medical 代表取締役社長
淺野 正太郎氏
PwCアドバイザリー合同会社 パートナー
河 成鎭
PwCアドバイザリー合同会社 ディレクター
大川 雄也
(左から)河、淺野氏、大川
※所属法人名や肩書き、各自の在籍状況については掲載当時の情報です。
大川:
デジタルヘルスの中で、デジタルセラピューティクス(以下、DTx)は近年特に関心が高まっている分野です。淺野さんは2018年にSave Medical社を創業なさる前は、リクルートに在籍しておられたのですよね。ヘルスケアに関わるようになった経緯からお話しいただけますか。
淺野:
私はリクルートで飲食・旅行などの事業領域を担当していました。その後、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の部署に異動し、投資担当としてデジタルヘルスの市場調査や投資先候補のデューデリジェンスを手掛けていました。そこで2013年に、医療的な考えを持ち込んだダイエットアプリ、今でいうところの生活習慣病系アプリを開発する米国企業への投資を担当したことがヘルスケアとの最初の接点です。私は医療者としてのバックグラウンドはありませんでしたが、2014年、2015年に米シリコンバレーで多くの起業家と議論をするなかで、医療にかかわっていなかった人でも成功している事例が多くあることを知り、気持ちが動きました。
大川:
投資家サイドではなく、プレーヤーとしてヘルスケアビジネスを手がけようと思われたのですね。
淺野:
デジタルヘルスが、人生における深いところで良いインパクトを出せるプロダクトになってきたと実感していましたので、「自分に何ができるか」ではなく、「自分が何をやりたいか」という気概でチャレンジをしていいのだと考えるようになったのです。帰国後、社内で事業化を模索しましたが、インターネット企業とライフサイエンス業界とでは、投資リターンについての時間軸が大きく異なる点がネックとなりました。
大川:
そこで、独立して起業する道を選ばれたのでしょうか。
淺野:
そうなのですが、すぐに起業したわけではありません。まずはご縁をいただいた、医療機器インキュベーターの日本医療機器開発機構(現サナメディ)に入社しました。医療機器の面からデジタルヘルスに取り組む方が、開発期間は長くかかるものの、普及スピードが一番早いのではないかと思ったからです。当時、日本医療機器開発機構では既に糖尿病アプリのコンセプトや原型となるプログラムが作成されていました。ただ、世に出すためには治験が必要で、時間も資金もかかるためにプロジェクトがホールドになっていたのです。そこで「資金を調達できたら子会社を作って取り組んでよい」との了解を得て、事業開発をリードさせて頂き、2018年に100%子会社としてSave Medicalを設立したという経緯です。
大川:
当時は国内で薬事承認されているDTxが存在せず、DTxという言葉すら認知されていませんでしたよね。DTxが普及するかどうか、さらにビジネスとして成立するかどうか、不安はなかったのでしょうか。
淺野:
創業するにあたって、デジタルヘルスへの期待について改めて考えてみました。医療、とりわけ日本の医療では、患者さんを救うという明確なベネフィットと、医療者の負担を軽減できるメリットがないと新しい製品やサービスを使ってもらえません。これは、以前の投資先を見て学んだことです。また、医療費増加という社会課題が顕在化するなかで、患者さんを救い、医療者などの省力化を可能とし、さらにコストを抑えるという3つの側面での解が必要になると考えました。つまり、ITに対する医療目線での期待は、「save」という単語に集約できます。DTxや治療用アプリは、その3要素を満たす製品・サービスです。デジタルヘルスにおける理想を事業化するわけですから、逆に「これしかない」という確信が深まりました。
大川:
それが、Save Medicalという社名の由来になっているわけですね。
淺野:
はい。事業の蓋然性はやってみないと分からないというのが正直なところでした。ただ、よく言われるように、日本は海外と比べて挑戦者が少ないですよね。この状況はDTx分野も例外ではありませんでした。製薬会社は数多く存在するのに、当時、DTxの開発に取り組んでいた企業は、CureApp(2014年創業)とサスメド(2015年創業)が知られていた程度です。当社がターゲットとして想定していた糖尿病の領域も、米国ではエビデンスも貯まってシステマティックレビューも多くありましたが、日本で本気で商業化に取り組んでいる企業がありませんでした。
河:
デジタルをてこにヘルスケアのエコシステムが変わっていくなか、旧来の医療セクターのプレーヤーだけでは、タコ壺化してブレークスルーが生まれないリスクもあります。適切な表現かどうかは分かりませんが、ペリフェラルな(周辺の)領域から志を持った方が参入することは、医療にとって良い動きだと思います。
淺野:
「変化はよそ者、若者、馬鹿者から」という言葉に勇気づけられました。もう若者とは言えない年齢ですが、よそ者と馬鹿者ならばいけるかなと。
株式会社Save Medical 代表取締役社長 淺野 正太郎氏
河:
先ほど、日本医療機器開発機構に入社した動機を振り返っていただいたときに、デジタルヘルスの社会実装は、医療機器からやっていくのが一番良いと考えたというお話がありました。この点はビジネスモデルを考える際の重要なポイントだと思います。
ビジネスモデルとしては、いろいろな選択肢がありますよね。医療機器の面から取り組むにしても、DTx単体で相当なアウトカムがないと治療における補助的な扱いとなり、十分な保険償還価格が得られません。また、医薬品とセットで売り出していく、つまりマネタイズの中心は医薬品にあって、その価値を高めるアプリケーションとしての位置付けとして開発し、利益をシェアする方法もあります。この場合、製薬会社との交渉が必要で、開発期間が長い医薬品のリスクも一緒に負うことになります。健保組合などと組んでマネタイズを図る道もよく模索されていますね。
御社は大日本住友製薬(現 住友ファーマ)と2型糖尿病管理指導用モバイルアプリの共同開発をしておられますね。これはどのようなビジネスモデルを考えているのですか。
淺野:
前提としてお話ししますと、DTxも、ビジネスモデルの検討方法は、スタートアップビジネスにおけるオーソドックスなアプローチと同じです。SPF(ソリューションプロダクトフィット:解決策を製品に実装できている状態)という意味では「治験(で現状の標準治療)に勝てるか」が問われ、PMF(プロダクトマーケットフィット:製品の提供価値が市場に受け入れられた状態)という意味では、「DTxは飛ぶように売れるのか」が問われると思います。
弊社のファーストトライアルでは、糖尿病領域において薬事承認を得て保険収載された医療機器としての使われ方を目指しました。CureAppの高血圧治療補助アプリと同様のシナリオですね。ただ、治験を終えた今の時点では、糖尿病アプリで医薬品と同等、もしくはそれ以上の効果を出すハードルの高さを実感しています。患者さんが、与えられたアプリを1人で使いこなせるようになることが主な課題です。一方で収穫も多く、プロダクト面、臨床開発面でどのような社内体制を構築するべきかについての知見が深まりました。
また途中の過程で、アンメットメディカルニーズが高い他の疾病でのDTx市場性について調査する機会にも恵まれました。グローバルを見ると、緊張や不安を和らげるメンタルヘルスの改善を目指すDTxの開発が活況を呈しています。モダリティとしてもアプリだけでなく、ウェアラブル、VRデバイス、はたまた嗅覚に作用するデバイスと組み合わせるなど、さまざまな可能性が広がっています。
河:
行動変容というより、治療に直接使える領域ということですよね。
淺野:
はい。良い医薬品がない領域に、唯一の治療モダリティとして入っていく製品が生き残るのではないかと思っています。糖尿病や生活習慣病の領域は引き続き目配りをしていますが、私たちが得たデータや周囲の状況から考えると、生活習慣病系の治療はDTxに固執しなくても良いのかもしれません。エビデンスを出せる良い製品を作った次の段階として、DTxが良いのか、エビデンス有りのヘルスケアアプリとして打ち出していくのかといった、事業の仕立て方を検討する局面が来るはずです。
河:
少し治験の話に戻ります。DTxの場合、被験者がきちんと使ったかどうかは問題にならないのでしょうか。
淺野:
非常に重要なテーマです。試験のデータ解析の際の閾値としての利用率・遵守率というのは当然重要です。また、それ以上にDTx開発側として気になるのは、「単にアプリを開いただけ」か「弊社の意図したとおりにアプリ機能を使い込んでもらえたか」などアプリの効能効果に関わる部分です。多面的に見ています。
大川:
そもそもの確認になりますが、糖尿病アプリの試験デザインは、基本的には対象群となる標準治療の群と、標準治療に上乗せして糖尿病アプリを使った群を比較するのですよね。その中で、血糖の状態を示すヘモグロビンA1cの値を主要評価項目として見るということでよろしいでしょうか。
淺野:
おっしゃるとおりです。
河:
では、デザインする過程は、「治験をしてエビデンスを出していく」医薬品と変わらないということですね。
淺野:
はい、変わりません。そのお話に関連するところでは、開発の投資対効果をどう考えるのかという点について、行政側にも問題意識を持っていただいていると認識しています。薬のような治験を実施するコストと、得られる医療機器の保険償還の点数が、事業者として捉えたときに適正かどうかということです。このバランスの悪さへの違和感は、当事者としてはありますし、変わっていくことを期待しています。
大川:
DTxは、使われ方や位置付けが医薬品に近い一方で、大きな枠組みでは医療機器になっていますよね。DTxの特性にふさわしい承認制度が日本では整備しきれていないと感じます。先行している米国やドイツなどと比較して、認証制度の在り方についてどのように捉えていますか。
淺野:
米国の行政の対応は確かに良いとは思いますが、日本でも医療機器の審査を担う医薬品医療機器総合機構(PMDA)にプログラム医療機器を専門とする相談窓口は設けられていますし、直にお話しさせていただく審査官や担当の方々の熱意をすごく感じます。新しい産業を育てようと、前向きに一緒に取り組んでいただいていると思います。
大川:
ドイツの場合はいかがでしょうか。
淺野:
ドイツが採用している二段階保険制度は、仮償還(仮での保険償還)のような形でとにかくたくさん市場に出して、一定期間内に有効性を検証したエビデンスが得られなかった製品については仮償還を破棄するといったプロセスです。また多くの場合、欧州におけるDTxはクラスIのリスクが低い製品とされており、製品自体の薬事承認審査は不要です。結論から言いますと、この制度は私たちのようなベンチャーからするととてもありがたいですし、日本でも同様の制度の導入に向けた議論が起きていることについては、大いに期待をしています。
と言いますのも、従来の医療機器は、医師が診断・治療に使うツールとして発展してきていますので、開発者は顧客である医師のニーズを捉えることにフォーカスしてきました。このため、開発期間が長期に及んでも市場性についてはある程度の推測が可能です。これに対してDTxは医師以上に患者さんが使うことを想定している製品です。しかも、効果が出るには一定期間使い続けないといけないという性質があります。医療機器でありながら、患者さんに使い込んでいただくというこれまでにない領域であるため、市場性の予測が非常に難しくなります。
一般的に、他産業でアプリ開発するときは、まず必要最低限の機能のみに絞って世に出して、ユーザーの声を聞き、磨き上げていきます。既存の医療機器とは真逆の開発プロセスです。現状では、アプリを開発する事業者としては、使い心地や使用感といった細かい部分に関するユーザーフィードバックの量が圧倒的に足りない状態のままDTxを出荷しなくてはならず、製品の完成度として、どこで折衷点を見出すかが難しい状況です。これが、ドイツのような二段階認証制度に期待をしている理由です。
河:
承認プロセスそのものはPMDAが頑張っていると思うのですが、保険償還の方は克服すべき課題が多いのかなと思いながらお話を聞いていました。CureAppのアプリも、手技などとは別に保険償還される特定保険医療材料には分類されていません。アウトカム次第なのかもしれないですが、そこについての問題意識は何かありますか。
淺野:
私の立場からすると、まずは強いエビデンスを出すしかないという感じですね。
河:
ビジネスですから、エビデンスの程度に応じて、どのようなロジックで、どのくらいの額が償還されるのかがクリアになっていることが重要ですよね。
大川:
中には、当該DTxとの関係性をイメージしにくい別の医療機器の技術料が準用されて、保険償還の点数が決まっているような印象があります。
河:
淺野さんを含め、DTxの開発側にとって、保険償還価格の算出方法はクリアなのでしょうか。それとも、やってみないと分からない部分なのでしょうか。
淺野:
やってみないと分からないのは確かなのですが、保険償還価格はちょうど良いところに落ち着いているとも思っています。ただ、まだ事例が少なすぎるのが現状かと思います。
私ども事業者からすると、DTxを医薬品のように評価していただきたい、というのが基本的な主張となります。アウトカムで評価してもらえれば、薬価のような高い保険償還価格が付与されるので、ビジネスとして考えやすいです。米国のベンチャーも、カンファレンスなどの場で「私たちのプロダクトは医療機器ではなく、薬です」というメッセージを頻繁に発信していますので、これはグローバル共通の課題認識でもあります。
一方で、医療現場では見方が異なるのかもしれません。医療者は、糖尿病の治療で患者さんに自己血糖測定器を使ってもらうときの指導と同じ要領で、「アプリを処方するのでこういうふうに使ってくださいね」と患者さんにお伝えします。医療機器の導入と類似する業務フローですから、医療現場では医療機器として扱う方が違和感がないはずです。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の枠組み上、DTxはプログラム医療機器ですから、技術料の中で保険償還価格を考える従来の方法も、納得せざるを得ない部分があるのも事実です。
河:
製薬会社のコンサルティングをさせていただいていると、エビデンスを出すことと、エビデンスを浸透させることには異なる難しさがあると感じています。今のお話で言いますと、医師に「医薬品と同じだ」と腹落ちしてもらうのは簡単ではないかもしれませんね。
淺野:
実際、だいぶ違いますよね。例えば服用薬は、ユーザーのアクションとしては「飲むだけ」でよいのですから。ある意味、「最強のUX」です。アプリの場合、まずは医療者側にそれを処方する環境を整えていただく必要があり、また患者さんにも前向きにアプリ利用を理解していただく必要があります。患者さんにとっても、医師にとっても新しいプロセスですし、患者さんと医師というユーザーの立場では、医薬品とはだいぶ違う認識になるはずです。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}