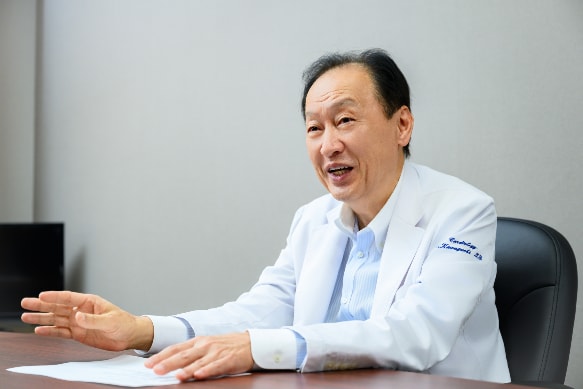{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
小田原市立病院(以下、市立病院)は、神奈川県の県西医療圏に属する417床の急性期病院であり、ほんの10年前まで医業利益がマイナス10億円まで落ち込んでいましたが、2022年度には繰入金を除く医業収支が黒字に転じるなど、新型コロナウイルス感染症による落ち込みを乗り越え、7年間で医業収支20億円の経営改善を実現しています。全国の公立病院の中でもトップクラスの医業利益を計上しており、令和4年(2022年)度に自治体立優良病院両会長表彰、令和5年(2023年)度には同総務大臣表彰を連続受賞*1しました。また、直近の2024年度では、医業収支で7億円の黒字、当期純利益は20億円を計上しています。
PwCコンサルティングは2016年度の新公立病院改革プラン策定支援を契機として足掛け2年程度、市立病院の経営改善の支援を担いましたが、支援後も独力で中期的な経営改善を実現するなど、まさにPwCコンサルティングが目指す「改善を持続できる組織」に移行しているといえます。そのような強い小田原市立病院を事業管理者・病院長の立場で築き、リードしている川口竹男氏に、病院経営への思いを伺いました。
小田原市立病院
病院事業管理者・病院長
川口 竹男氏(医師)
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
髙橋 啓
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター
小田原 正和
※所属法人名や肩書き、各自の在籍状況については掲載当時の情報です。
(左から)小田原 正和、川口 竹男氏、 髙橋 啓
小田原市立病院 病院事業管理者・病院長 川口 竹男氏(医師)
小田原:
初めて川口先生にお会いしてから10年近くが経ちますが、当時から今に至るまで、先生の病院経営に対するモチベーションの高さには驚くばかりです。公立病院・民間病院を問わず、病院長の経営に対する意識は千差万別と感じますが、川口先生は周囲のメンバーを叱咤激励し、周りを鼓舞しながら、時に厳しい状況においても勇気を持って決断を下し、病院経営に向き合う熱量の高さには一切の衰えを感じさせません。先生の病院経営に関するモチベーションはどこから来るのでしょうか。
川口:
「良質な医療を提供するためには経営的に安定していないと実現できない」という考えが根本にあるように思います。例えば、患者さんにとって侵襲性の低いロボット手術を実施しようとしても、経営的に安定していなければそういった投資も難しくなります。新しい投資ができなければ、医療者を始めとした人を集めることも困難です。特に、医師が集まらなくなった病院のほとんどが厳しい経営状態に置かれています。持続的に良質な医療を提供するためには、経営の安定が不可欠なのです。
髙橋:
気になっていたのですが、先生が初めて病院長に就任した時は、どのような気持ちで引き受けられたのでしょうか。
川口:
私が米国留学から日本に戻って以降、小田原市には30年近く関与しています。そういった年月が、自然と市民のためにという思いを日に日に強くさせたのでしょうね。自分が関わっている患者さんを放り出すことは到底できない。周囲の期待にも応えていきたいと。当時はそのような気持ちでしたね。言い換えれば、地域に根差したということかもしれません。
小田原:
少し時間軸を巻き戻して伺いたいのですが、10年程前の市立病院は医業利益がマイナス10億円まで落ち込んでおり、私たちが初めて病院長室に伺った際には、とても張り詰めた空気を感じました。当時、どのような思いで経営改善に取り組まれていたのでしょうか。
川口:
当時は、何か手を打たなければ後退してしまうのが目に見えていました。市立病院は地域の中で一番の基幹病院であり、その役割を果たさなければならないという強い危機感を抱いていましたね。それが張り詰めた空気を生み出してしまったのかもしれません。
小田原:
当時の経営改善プロジェクトではさまざまな施策を実施しましたが、何が最も効果的だったと考えますでしょうか。
川口:
何といっても診療科別に実施した科別面談でしょうね。各診療科の医師に病院の状態や診療科の状態を伝えることに加え、病院が目指す方向性や診療科への期待、診療科としてどのような医療を提供したいのかを相互に真剣に話し合った。部長クラス以外の先生は話しにくかったかもしれませんが、対面で実施し、危機意識も共有することができたと考えています。その基礎をPwCコンサルティングには作ってもらった。病院職員の育成にも力を注いでくれました。それ以降、職員が引き継いで科別面談の支援をしてくれています。毎年踏襲しており、年度ごとに資料や要点をファイルにまとめて病院長室に保管しているのです。毎年、前年の討議内容を見返してから臨むようにしています。
髙橋:
嬉しいですね。
川口:
病院に半常駐して実施いただきました。
髙橋:
詰め部屋がありました。(一同笑)
小田原:
何をどのタイミングでどのように伝えるのが最も効果的なのか熟考しましたね。また、科別面談ではさまざまなことが見えました。他病院へ紹介している疾患、診療科の先生ごとの考え、経営に興味を示す先生の存在など、労力はかかりましたが、各先生に危機感を共有していただくことや事務局側の人材育成の礎になりました。
髙橋:
各診療科の先生との信頼関係醸成の第一歩にもなりましたね。
川口:
もう一つ、病院経営の根幹を成す病診連携支援に関しても、ニーズ調査を含めて病院職員とともに周囲の開業医の先生を回っていただいた。苦情もあったと思いますが、本質課題を突き詰め、解決までの道を作ってもらった点が非常に助かりましたね。
髙橋:
地域医療連携室の職員の方も含めてチームでやり切ったプロジェクトの一つだと思います。
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 小田原 正和
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 髙橋 啓
小田原:
人材確保という観点で、川口先生の人材獲得手腕についても目を見張るものがあると感じます。同時に、病院に限らずどの業界でもそうですが、異動や退職を伴う人事に関する意思決定には相当な胆力を要します。どのような考えや思いで対応されているのでしょうか。
川口:
正直、人事に関する意思決定には苦しい面が多分にありますが、病院長である自分こそが決断しなければならない場面が必ず出てきます。そういった時は「患者さんに良い医療を提供するために」という信念に立ち返るようにしています。また、市立病院が位置する小田原市は山と海に囲まれており、進取の精神がなければ井の中の蛙になってしまいやすい。自分たちの実施していることが常に正しいと思い込まないように、より一層、外の風を吹かせることが重要と考えています。決して自分たちの現状に安住することなく、組織を活性化させ続けることが病院のさらなる発展には必須だと思っています。
小田原:
どのようにして優秀な人材を見つけてくるのでしょうか。
川口:
人に恵まれたというのはあります。ただ、大学にはよく挨拶に行くようにしていました。何年か実施していると分かってくることもある。そういった長年の関係性の中で紹介いただくことも多いですね。もちろん、市立病院には人材を送らないと言われてしまう可能性も考えていますが、結局困るのは患者さんやその家族なので、恥はかき捨ての気持ちで、言わざるを得ない時には自らに鞭を打って言うようにしています。市立病院の医師は1つの大学医局に偏っているわけではなく、5つの大学医局から医師を派遣していただいています。人材獲得の面では市立病院の強みと言えるかもしれませんね。
髙橋:
外部からの人材獲得にあたっては、獲得元のケアも必要ですが、その人が入ってきた時のケアも必要になります。時に周囲から浮いてしまう、もしくは組織が浮かせようとしたりもします。何か気を付けていることがあれば教えてください。
川口:
よくよく話し合うように心がけています。意識的にそのような場を作るようにする。また、新たに入ってくれた人が何か新しいことにチャレンジする場合には、理由をしっかりと確認し、合理性がある取り組みと思えば、病院長としてしっかりと後押しするようにしています。
髙橋:
重責がある中で、組織としてやらなければならないこと、決めなければならないことをリーダーとして胆力を持って決断していると感じます。
小田原:
ここからは病院経営者としての観点で、その他に川口先生が意識されていることを伺いたいと思います。先ほど、診療科別の個別討議の話にもありましたが、現場とのコミュニケーションをとても大切にされている印象を持っています。
川口:
現場とのコミュニケーションは意識的に実施するようにしています。例えば、病院長回診は現場の職員と直接会話ができる貴重な場と捉えています。職員に対して、何に困っているか、病院として必要なサポートは何かなど、面と向かって確認することができるので、病院が取り組まなければならない事項も見えてきます。
小田原:
公立病院では設置主体である自治体の長とのリレーションも大切です。こちらも頻度高く連携されているように思います。
川口:
経営管理課をはじめとした事務局が、市側との間に入って調整してくれるお陰で、良好な関係が構築できているように感じます。幸い、周囲に優秀なメンバーがいるので、彼らを信頼して任せることができています。病院長は医療のことだけに関心を持っていてもガバナンスを効かせた病院経営はできません。俯瞰的な視野を持ち、いかに周りの人の支援を得ながら進めていけるかが重要と思います。
髙橋:
周りの人の支援という意味では、川口先生には先生を支えるチームがあると感じます。
川口:
事務局が中心になって支えてくれていますが、幸いモチベーションの高いメンバーが集まってくれています。チームで固まりすぎるのは良くないですが、同じ方向性を向き、病院を引っ張っていくような推進力をもつ人たちは必要ですね。
小田原:
昨今、医療機関のみならず、製薬企業においてもペイシェントセントリシティ(患者中心主義)の考え方が浸透しています。川口先生は、普段から患者さんの立場に立って考えることが重要とおっしゃっています。
川口:
病院や医療のことを考える際には、常に患者さんの視点を持つことが大切だと思っています。自分が患者さんの立場になって初めて気が付くことも多い。現在、市立病院では新病院建設事業を進めていますが、スタッフと討議をしていると、導線のあり方やスイッチの配置など、なかなか患者目線に立てていないと思えることもあるので、そういった時には積極的にコメントするようにしています。自分自身が病気にならないと実感しにくいですが、特に若いスタッフには患者さんの目線で考えることを意識してほしいですね。
小田原:
事務局のメンバーの方々と話をしていると、病院長から下りてきた病院長課題という言葉を耳にします。最近の病院経営に対する考え方および経営課題の抽出方法について教えてください。
川口:
これまでは、患者さんに適切な医療を提供していれば収益は自ずと付いてくる、そのような考え方を基に、適切な医療提供のためには何を実施すべきかを考え、実践するようにしていました。ただし、昨今は風向きが変わってきたように思います。材料や人件費、経費といったコストがこれまでにないスピードで上昇している。一方で、診療報酬制度により収益の上限は見えている。この状況を切り抜けるために、経営的な部分でどうしたらプラスになるのか、どのような医療を提供していかなければならないかについては、常にアンテナを張っているつもりです。特に、業界の異なる人の考え方などは参考になりますね。自分の思考の枠外からの話が聞けるので。
小田原:
新型コロナウイルス感染症が落ち着いて以降、病院経営に関する潮目は確かに変わりました。ここ1~2年は医療機関の経営改善に関する相談は非常に多くなっています。
最後になりますが、市立病院では、2026年の春頃に新病院の開院が予定されています。病院長として、これから力を入れたいことについて聞かせてください。
川口:
やはり一番は、医師や看護師を始めとした医療者を呼べる病院になること。そもそも医療者を確保しなければ、患者さんに良い医療を提供することはできません。働く人に選ばれる病院になる必要があり、そのためにも市立病院に携わる全ての人の自己実現が支援でき、かつ、働きやすい環境を整備して提供すること、これが私の使命だと思っています。これからも小田原の地で、患者さんに良い医療を提供していけるよう病院職員一丸となって頑張っていきたいですね。
小田原:
医療職や事務職も含めた働きやすさの追求は今後ますます重要になりますね。本日は、以前からとても気になっていた病院経営に対する川口先生の考えに触れることができました。貴重なお話をありがとうございました。
*1:公益社団法人 全国自治体病院協議会
https://www.jmha.or.jp/jmha/contents/info/79
https://www.jmha.or.jp/jmha/contents/info/78
小田原市立病院の経営改善について:
コラム「これからの病院経営を考える 第18回 小田原市立病院の経営改善を振り返る(前編:組織変革のための土壌づくり)」
小田原医師会長とのインタビュー:
コラム「医彩―Leader's insight 第4回 小田原市立病院の経営改善活動が地域医療にもたらしたインパクトとは」
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}