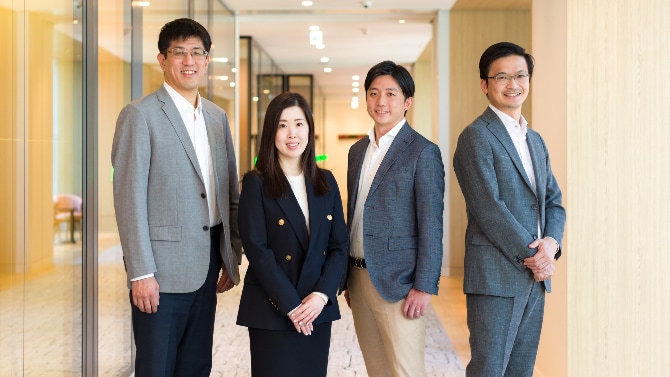{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
PwCコンサルティング合同会社は2024年2月、宇宙・空間産業に関する知見を有するプロフェッショナルを結集させ、組織横断型イニシアチブ「宇宙・空間産業推進室」を立ち上げました。「宇宙・空間」をリアルとデジタルの双方から俯瞰した視点で捉えていくことで、陸・海・空、そして宇宙における分野横断的な場づくりや関連産業の推進、技術開発、事業活動を支援しています。
本稿は前編・後編の二部構成となっており、後編ではリアルスペースにおけるビジネスの可能性と、「宇宙・空間産業推進室」の今後の取り組みについて主要メンバーが語り合います。
登壇者
PwCコンサルティング合同会社 パートナー 渡邊 敏康
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 中林 優介
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 片桐 紀子
モデレーター
PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 石川 慶紀
※法人名・役職などは掲載当時のものです。
左から 渡邊 敏康、片桐紀子、石川 慶紀、中林優介
PwCコンサルティング ディレクター 石川 慶紀
石川:座談会の後編では、PwCが考えるリアルとデジタルの2つのスペースのうち、リアルスペースにおいて話題に上がることの多い月面ビジネスの可能性について取り上げます。月面と聞くと先の話のように感じるかもしれませんが、実はPwCがグローバル規模で注力している領域の1つですよね。
中林:まずは、月面経済における事業機会についてお話したいと思います。「月または海外に行ったことはありますか」という質問をした際、「海外に行ったことがある」と答える方は多いですが、「月に行ったことがある」と答える人は、まずいないと思います。一方、約150年前の日本で「海外に行ったことはありますか」という質問をしたとしたら、「行ったことがある」と答える人の数は、現在「月に行ったことがある」と答える人と同じような結果になるのではないでしょうか。
日本はその後経済発展を遂げ、他国と貿易や交流を行う機会が増えました。それと同じような変化が月面ビジネスにおいては今後数十年で実現されるのではないかとの見込みがあります。したがって、月に人や物を輸送し、月のデータや月にある資源を活用するといった事業が大きな機会となるのではないかと考えています。
PwCはグローバルネットワークを通じて月面経済が盛り上がる可能性を考え、2021年には月面ビジネスに関するレポートをPwCフランスが中心となって発刊しました。このレポートは非常に多くの反響を呼び、日本でも問い合わせが相次いだことから、2023年には日本語版を発刊するに至りました。各種メディアで取り上げられたり、さまざまな企業や団体から問い合わせを受けたりした状況を踏まえても、月面ビジネスは非常に注目度の高いトピックだと考えられます。
石川:月面ビジネスというと壮大な感じがしますが、ビジネス機会をどのように捉えるべきでしょうか。
中林:月面ビジネスは、大きく「月輸送」「月データ」「月資源活用」の3つに分けて考えることができます。
PwCコンサルティング ディレクター 中林 優介
中林:まずは月輸送について説明します。自動車産業や製造業に精通されている方にはお馴染みかと思いますが、サプライチェーンには上流・中流・下流という考え方がありますよね。月面ビジネスも同じで、月に輸送するのは上流の部分にあたります。具体的には、ローバー(探査車)の製造、月軌道までの打ち上げ、月面着陸などです。一方、下流では、実際に月面に着陸したものを操作するビジネスが中心となり、例えばデータ信号処理やデータを介した物の輸送、月面からの物の持ち帰りなどが挙げられます。
月輸送ビジネスがどれぐらい盛り上がってくるのかについて、PwCコンサルティングでは「楽観」「基本」「保守」という3つのシナリオを描いていますが、「基本」のシナリオで見ても2020年から2040年の間で約790億米ドル、日本円で10兆円以上の大きなビジネスになると見込まれています。市場拡大が見込まれるなかで、自動車メーカーが月面を走る車の開発に挑んでいたり、建設会社や不動産企業が月面上に建物を建てることを検討していたり、さまざまな業界においてビジネスチャンスがあると感じています。
中林:続いて月データについてお話しできればと思います。昨今「DX」がだいぶ馴染みのある状態になってきているなかで、DXを通じて得られるデータは非常に重要であることは皆さんも感じているのではないでしょうか。
その重要性については月データも同じです。データの重要性を考えるにあたって、例えば、日本から遠く離れた国に物を輸送する際、「輸送中に壊れたため再度輸送してほしい」と依頼された場合、飛行機でも数日、船だと数十日はかかります。その間は物が届かず、事業や生活が止まってしまうので困ると思うのですが、月へ物資を輸送するということは、この話の延長線上にあります。月面に物を輸送するとき、量を間違えてしまった、または壊れてしまったという場合、再輸送には莫大なコストがかかります。
中林:このような事態を防ぐために、月輸送に関するデータを分析し、トラブルがないようにすることが必要です。月のデータにどれほどの市場規模が見込まれるのかについてですが、2020〜2040年の累計で85億米ドル、日本円で1兆円を超えると予測されています。今後、テレメトリデータ、エンタテイメントデータ、環境データが蓄積されていき、さまざまな分野でこれらのデータを活用したビジネスが広がっていくのではないかと見立てています。
月資源の活用については、よくニュースにもなるのでご覧になっている方も多いと思いますが、探査船で宇宙に行き、地球に持って帰ってきた未知の鉱物、新しいエネルギーになるようなもの、また月面にあるエネルギー源などが月資源に該当します。
例えば、宇宙太陽光発電は月資源活用の1つの例です。当たり前ですが、太陽は宇宙にあるため、地球の表面に置いておくよりも空に飛ばした方が発電効率が良くなるいう議論があります。宇宙太陽光発電は、衛星軌道上に発電施設を飛ばして発電を行い、エネルギーに変えて地球の表面に飛ばす仕掛けです。エネルギーは周波数で飛ばすことになりますが、その方法は、宇宙空間にいる宇宙飛行士が地球にいる家族とテレビ電話をする仕組みと同じで、画像や映像を伝達することができるのならば、エネルギーの伝達もできるのではないかと考えられています。
このように、宇宙にある資源を活用していく動きはさまざまな業界の方が関心を高く持っており、「資源の宝庫」と言われる月資源への期待も高いと感じています。
では、「なぜ月資源を活用することが重要なのか」ですが、仮に異国の地など普段と異なる環境で暮らす場合、日本から持参したものだけではなく、その場にある資源を活用して生活することになると思います。例えば、海外進出した企業が現地でサプライチェーンを構築していった方が、ビジネスコストが明らかに安くなるというロジックがありますが、これと同じで、月に存在する資源を活用して生活した方が、生活コストが圧倒的に安くなり、かつ生活の継続性が保たれるようになります。今後、月に行くことや宇宙プロジェクトを数多く、かつ質も高くこなしていくためには、月資源の活用は不可欠でしょう。
月資源活用の市場は、月輸送や月データ活用の2つと比べても、市場の立ち上がりは遅れています。月面経済圏を成立させるためには、さまざまな技術や生活環境の整備が必要ですが、2030年台後半ぐらいから市場が確立されるのではないかと見込んでいます。
世の中には、月だけでなく、火星に行くことも重要だと考える人もいますが、月だけではなく火星、さらには他の惑星に進出できれば、宇宙空間に存在する資源を活用して地球の社会課題を解決できる新しいビジネスが生まれてくるのではないでしょうか。
石川:月面開発を通じて地球上の課題を解決する世界の到来が迫ってきていますが、具体的にはどのようなことが考えられるのでしょうか。
片桐:例えば、農業分野での課題解決が考えられます。農業分野では、土や酸素が不足している月面での植物栽培の可能性や生態系についての議論が活発化してきています。もし、月面での植物栽培が可能になれば、地球における食料安全保障の問題の解決の糸口になるのではないでしょうか。月面開発のアプローチがさまざまなテーマにつながり、地球における新しい可能性として拓けることを期待しています。
PwCコンサルティング ディレクター 片桐 紀子
PwCコンサルティング パートナー 渡邊 敏康
石川:「宇宙・空間産業推進室」にはPwCコンサルティングのこれまでの取り組みがどのように活かされているのでしょうか、そして最後に、今後の展望についても教えてください。
渡邊:ここまでの議論を通じて、月面経済圏の可能性に加えて、宇宙・空間産業が実は身近なところにたくさん存在しているということをご理解いただけたのではないでしょうか。自動車業界には、CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)という考えがあります。リアルとデジタルといったシステム・アーキテクチャ視点で見ていくと、Sが一番上にあり、Cが真ん中にあり、そしてEとAが下にあると位置づけることができます。EやAのインフラやビジネスの場には、デバイスそのものや伝統的な産業構造があり、そのうえにコミュニケーションというコネクティビティが存在し、さらにシェアドサービスにつながっていき、その先にはルールといったものがあるといったイメージになります。宇宙・空間産業についても、このCASEのアーキテクチャ、アナロジーがあるものと考えています。
宇宙・空間産業でもCASEの考え方やトレンドを踏まえて、宇宙から地球の社会課題を捉えていきたいと考えています。今回の対談では、データ流通などの話が中心となりましたが、ルールメイキングやものづくりといったテーマについても向き合っていきたいと考えています。
今後も宇宙・空間産業推進室として、「宇宙・空間」をリアルとデジタルの双方から俯瞰した視点で捉え、陸・海・空、そして宇宙における分野横断的な場づくりや関連産業の推進、技術開発、事業活動を支援していければと思います。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}
石川:「宇宙・空間産業推進室」にはPwCコンサルティングのこれまでの取り組みがどのように活かされているのでしょうか、そして最後に、今後の展望についても教えてください。
渡邊:ここまでの議論を通じて、月面経済圏の可能性に加えて、宇宙・空間産業が実は身近なところにたくさん存在しているということをご理解いただけたのではないでしょうか。自動車業界には、CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)という考えがあります。リアルとデジタルといったアーキテクチャ視点で見ていくと、Sが一番上にあり、Cが真ん中にあり、そしてEとAが下にあると位置づけることができます。EやAのインフラやビジネスの場には、デバイスそのものや伝統的な産業構造があり、そのうえにコミュニケーションというコネクティビティが存在し、さらにシェアドサービスにつながっていき、その先にはルールといったものがあるといったイメージになります。宇宙・空間産業についても、このCASEのアーキテクチャ、アナロジーがあるものと考えています。
宇宙・空間産業でもCASEの考え方やトレンドを踏まえて、宇宙から地球の社会課題を捉えていきたいと考えています。今回の対談では、データ流通などの話が中心となりましたが、ルールメイキングやものづくりといったテーマについても向き合っていきたいと考えています。
今後も宇宙・空間産業推進室として、「宇宙・空間」をリアルとデジタルの双方から俯瞰した視点で捉え、陸・海・空、そして宇宙における分野横断的な場づくりや関連産業の推進、技術開発、事業活動を支援していければと思います。
PwCコンサルティング パートナー 渡邊 敏康
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}