PwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)が2024年11月26日に開催したセミナー「日本の人事のトップランナーが語る人的資本経営の最前線」では、「これからの人的資本経営を支えるスキルセントリック組織とは」と題し、各社でCHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)を担う日産自動車株式会社の井原徹氏、野村ホールディングス株式会社の尾崎由紀子氏、日本電気株式会社(NEC)の堀川大介氏が登壇。PwCコンサルティング執行役員パートナーの北崎茂がモデレーターを務め、人的資本経営とスキルセントリックをテーマにしたパネルディスカッションを実施しました。
登壇者
井原 徹氏
日産自動車株式会社
チーフHRオフィサー
人事、コンプライアンス担当
尾崎 由紀子氏
野村ホールディングス株式会社
執行役員
CHRO兼健康経営推進責任者(CHO)
野村證券株式会社
常務 人事担当
堀川 大介氏
日本電気株式会社(NEC)
執行役
Corporate EVP 兼 CHRO 兼 ピープル&カルチャー部門長
モデレーター
北崎 茂
PwCコンサルティング合同会社 執行役員 パートナー
組織人事コンサルティングリーダー

(左から)北崎茂、井原徹氏、尾崎由紀子氏、堀川大介氏
各社が社員に焦点を当てた人事制度改革を推進
セッションのはじめに、PwCコンサルティングの北崎茂は、「人的資本経営」と「スキルセントリック」という2つのテーマを取り扱う背景について説明しました。
「ステークホルダーの広がりや情報開示の要請を受け、人的資本経営は人事の中核を成すアジェンダになっています。また、ジョブ型雇用への注目が集まる近年、さらに細分化したスキルに焦点を当て人材を管理するスキルセントリックの流れが欧米を中心に生まれ始めています。とはいえ、欧米と日本では雇用形態や文化も異なり、欧米の流れに追従すべきかの判断も企業ごとに異なります。そんな中、人的資本経営の観点から取り組みを進める大企業のCHROの皆さんとのディスカッションを通じ、各社の考えを掘り下げていきたいと思います」(北崎)
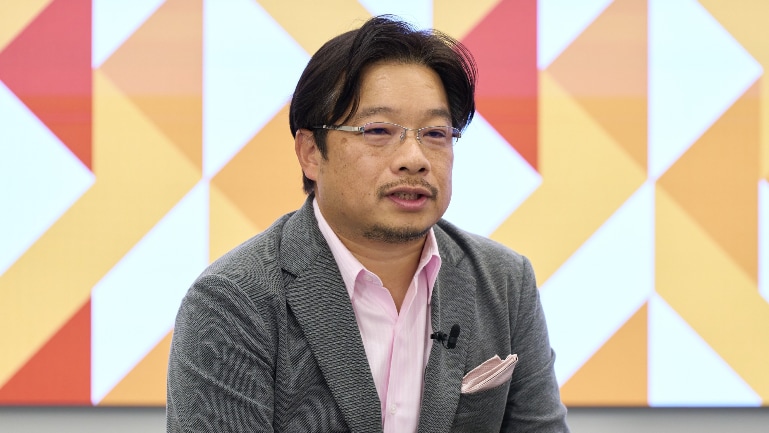
PwCコンサルティング合同会社 北崎 茂
パネルディスカッションの導入として、各社のCHROは自社の人的資本経営に関する取り組みについて紹介しました。日産自動車の井原徹氏は、組織と“人財”の可能性を広げるべく、従業員目線の人事改革に取り組んでいると語ります。理想として掲げているのは「意欲的でスキルのある従業員」。これを実現するため、スキル重視の人財マネジメントや従業員体験の強化、リーダーシップの強化に注力してきました。
「一部のリーダー候補を選抜して育成する従来のマネジメントを変革し、全従業員に向けてリーダーシップを高める施策を行っています。また、スキル重視のマネジメントを展開するために、従業員のスキルを全社的に管理するプラットフォームづくりを計画的に進めています」(井原氏)

日産自動車株式会社 井原 徹氏
人口減少の続く日本では、リーダー人材の確保が難しくなる将来が予測されます。そうした将来を見据え、野村ホールディングスの尾崎由紀子氏は、世界で戦えるリーダー人材の育成と、それを受け入れるための組織づくりに取り組んでいると話しました。
「キャリア自律と多様な人材の登用を促す、独自のジョブ型雇用を推進しています。具体的な例として、従来の野村證券では、全社一括で採用を実施し、人事が配属を決定する仕組みを続けてきました。しかし2025年度入社より、コース別の採用に完全移行。新たな付加価値をもたらすプロフェッショナル集団を形成し、豊かな社会の実現に貢献したいと考えています」(尾崎氏)

野村ホールディングス株式会社 尾崎 由紀子氏
日本電気株式会社(NEC)の堀川大介氏は、「人」が主役のカルチャーへ変革することが自身に課せられたミッションであると話しました。その上で、自社株価の動向と人事施策の関連性についてグラフを用いて説明。社員の声をベースに「人・カルチャーの変革」を愚直に推進した結果、エンゲージメントスコアとともに企業価値も向上していることを示しました。
「2018年度より、ジョブ型人材マネジメントを機能させるための環境を段階的に整備してきました。今年度から、ジョブグレード体系や報酬制度を改め、本格的に運用を開始しています。社内の制度・仕組みや組織構造を統一したことにより、ようやく人材を流動的に動かせるプラットフォームが整いつつあります」(堀川氏)

日本電気株式会社(NEC) 堀川 大介氏
企業と社員が目線を合わせ、ともに成長することが重要
各社の取り組みについて紹介が終わると、パネルディスカッションがスタートしました。最初のテーマは、「人的資本経営において最も大切なこと」。施策の実行にあたり、人事担当者が重視したものについて北崎が迫ります。
NECの堀川氏は、「社員の声を経営に反映し、社員に最大限の力を発揮してもらうこと」を挙げます。北崎は経営における従業員目線の重要性に深く共感しつつも、「従業員の声を重視しすぎると、事業とのミスマッチが起こるリスクがあるのではないか」と疑問を投げかけました。この質問について、堀川氏は次のように回答しました。
「もちろん、人材を流動化する仕組みをつくってきた背景には、事業戦略に応じてベストチームを形成したいという経営者目線の思いもあります。一方で、社員はその環境を活かし、自分でキャリアを選び取っていくことが理想です。会社と社員の間で、“選び・選ばれる関係”をつくる。そのバランスを考えることが重要だと感じています」(堀川氏)
続く野村ホールディングスの尾崎氏は、「社員のパーパスと会社のパーパスが重なりあっていること」が最も大切だと語ります。そして、企業と社員が『何を実現したいのか』を互いに明確にし、双方が目線を合わせた上でキャリアサポートや機会の創出に取り組むことが求められていると話しました。
しかし、日本では社員が組織にキャリアを委ねてきた長年の歴史があります。そうした従来のマインドから脱却してもらうため、野村ホールディングスとしてはどのような挑戦を続けてきたのでしょうか。そんな北崎の質問に尾崎氏が答えます。
「トップダウンの文化に長年身を置いてきた経営陣や上層部の社員たちはキャリア自律に馴染みがありません。そのため、部下のキャリア自律支援に難しさを感じています。そこで、私たちが間に入り、まずは上層部の理解を促進することから取り組みを進めてきました」(尾崎氏)
日産自動車が主眼を置いているのは、「人財に投資し、成長を実感してもらい、エンゲージメントの向上につなげていくこと」だと井原氏は話します。従業員一人ひとりのバリューを高めることは、企業と従業員に共通して重要なトピック。「会社は従業員が成長できる機会や環境を整え、その中で従業員はキャリア実現のために積極的に挑戦していき、結果として会社と従業員がともに成長していくカルチャーを創出することが求められている」と語りました。
全社一斉ではなく、可能な組織から進めていく
次の議題は、「人的資本経営におけるスキルマネジメントの必要性」について。スキルマネジメントを機能させるためには、個々のワークと個人のスキルを正しくマッチングさせることが合理的です。しかし、それは決して容易なことではありません。各社ではどのような工夫を凝らしているのか知りたいと北崎は話します。
野村ホールディングスの取り組みとして、「Digital IQ University」の構築があると尾崎氏は語ります。
「これは、野村独自のデジタル人材育成フレームワークです。Eラーニングインフラを用いることで全受講者に同じフレームワークを適用し、本来の業務とは別にグループ一体でデジタルスキルを底上げしています」(尾崎氏)
NECは、スキルベースのマネジメントに対してテクノロジー企業ならではの懸念を抱いているそうです。
「当社のように技術者の多い企業は、スキルを手に入れること自体が目的になってしまい、本来の目的を見失いやすい傾向にあります。その対策として、戦略的にキーとなるホットポジションに求められる具体的なスキルを明確にし、そこにマッチする人材を採用・登用することを重視すべきと考えています」(堀川氏)
スキルマネジメントに対する注目度が高まっている一方で、実際の導入に向けては多くのハードルをクリアする必要があります。それでも、「できるところからやっていく」という姿勢が大切だと日産自動車の井原氏は話します。
「私たちのような自動車企業であれば電動化、知能化といったように、これから必要になるスキルにまずはフォーカスしてスキルマネジメントの取り組みを進めたいと考えています。全社一斉で実施するのは難しいので、まずはニーズの高いファンクションから着手しているところです」(井原氏)
3社のスキルマネジメントに対する考えに触れ、単に新しい手法を受け入れるのではなく、合理的な判断に基づく柔軟な人事制度を導入することがポイントになるのではないかと述べる北崎。同時に、従業員がメリットを感じられるようなインセンティブ設計も必要になると続け、話題の尽きないパネルディスカッションを締めくくりました。
