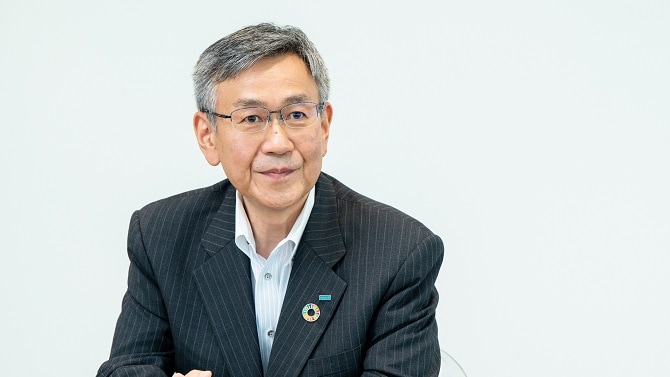{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2021-10-05
多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症の拡大、サイバー脅威の増加など、私たちを取り巻く社会環境のリスクは大きく変化しています。そのような状況下において、保険会社には何が求められているのでしょうか。MS&ADグループでは中期経営計画「Vision 2021」で、デジタライゼーションの推進を明確に打ち出し、多様化する顧客ニーズの先を行く施策を矢継ぎ早に打ち出しています。MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスの執行役員で、グループCDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)を務める一本木真史氏にMS&ADグループのデジタル戦略と新規ビジネスモデルの創造に向けた取り組みについてお話を伺いました。(本文敬称略)
鼎談者
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 執行役員兼グループCDO兼グループCIO兼グループCISO
一本木 真史氏
PwCあらた有限責任監査法人 パートナー/PwC Japanグループ 保険インダストリーリーダー
宇塚 公一
PwCコンサルティング合同会社 パートナー/保険インダストリーリーダー
古賀 弘之
(左から) 一本木 真史氏、宇塚 公一、古賀 弘之
宇塚:
最初にMS&ADグループのデジタル戦略について教えてください。2018年度にスタートした中期経営計画「Vision 2021」において、デジタル戦略はどのように位置づけられているのでしょうか。
一本木:
「Vision 2021」は前半の2年間を「ステージ1」とし、「デジタルプラットフォーム」を構築しました。これは、新しい施策やサービスの創出に必要なデータを収集・蓄積・分析する基盤となるものです。同時に「業務プロセス改革」「チャネル競争力の高度化」「商品・サービスのデジタル対応」の実現を目標に掲げ、営業や損害サービス、商品の領域ごとにデジタライゼーションを推進してきました。具体的にはオンライン刷新や、新損害サービスシステム「BRIDGE」の共同開発などです。
古賀:
「Vision 2021」でデジタル戦略を打ち出された当時、社員の方はどのように受け止めていましたか。
一本木:
「デジタライゼーション」に本腰を入れ始めたのは、「Vision 2021」を発表する前の2017年ごろからでした。当時はデジタル化による業務効率に主軸を置き、「既存業務をどのように改善するか」に取り組んでいました。そのときは「デジタライゼーション」と言われても、ピンとこない社員も少なくなかったようです。それから4年が経った現在は、ほとんどの社員がデジタライゼーションの必要性と可能性を理解していると思います。
宇塚:
現在は「Vision 2021」の「ステージ2」ですね。具体的にはどのような取り組みを実施しているのでしょうか。
一本木:
「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「デジタルイノベーション(DI)」「デジタルグローバリゼーション(DG)」を3つの重要な柱と位置づけてデジタライゼーションを推進しています。
既存ビジネスモデルの高度化は「DX」の一環として取り組んでいます。「ステージ1」で領域・部門別のデジタル化が一定の進展を達成したことから、「ステージ2」では部門を区切らずに、保険加入から保険金支払まで一貫したデジタル対応を目指し、異なる部門同士が一体となってデジタル変革を推進しています。
例えばグループ企業の三井住友海上では、2020年2月にAI(人工知能)を搭載した損保業界初の代理店営業支援システム「MS1 Brain」を導入しました。このシステムは、お客さまの情報をAIで分析して今後の需要を予測し、最適な商品やサービスの提案を支援するものです。お客さま起点の提案が可能になることで、代理店の経営高度化や営業社員の役割高度化を実現し、これまでの課題であった「代理店と営業社員の二重構造の解消」を図っています。
また、2021年2月には、お客さまとの新たなデジタル接点として「MS1 Brainリモート」をリリースしました。これは、お客さまのスマートフォン上で代理店とのWeb面談や保険契約手続きができるものです。保険の提案から手続きまでの一連のプロセスをデジタル化することで、お客さまの体験価値向上と保険募集業務の生産性向上を目指しています。
古賀:
コロナ禍では「非対面でサービスを受けたい」という声が多く聞かれました。こうしたサービスに対する需要は多いのではないでしょうか。
一本木:
そうですね。私たちは「MS1 Brainリモート」をリリースする以前の2020年11月から、グループ企業であるあいおいニッセイ同和で、自動車保険を対象にした新たな保険募集スキームを導入しました。それが、契約時に署名と押印が不要なサインレスのWeb手続きシステム「らくるまネット手続き」です。また、同じタイミングで代理店がお客さまごとにパーソナライズされた動画を生成・配信できる「らくっとMovie」システムも導入しました。同システムは先述の「MS1 Brainリモート」と同様に、非対面での保険契約手続が可能です。
古賀:
MS&ADグループのデジタル戦略は「既存プロセスを効率化する」だけでなく、顧客接点や業務プロセス全体を根本から見直し、既存ビジネスモデルの高度化を進めていらっしゃるのですね。
宇塚:
2017年に「デジタライゼーション」という言葉にピンとこない社員がいたとのお話がありました。そうした方は「これからはデジタルが主役」になると不安に感じたのではないでしょうか。しかし、今お話を伺って、「お客さまや社員が中心にいて、デジタルは人のために働く存在である」と明確に位置づけていらっしゃることがよくわかりました。大変すばらしい取り組みで、PwCもご支援させていただき、とてもやりがいを感じます。
一本木:
デジタル活用が当たり前となる中で、私たちがフォーカスすべきは「いかにお客さまの体験価値を高められるか」と「自らの業務生産性を引き上げられるか」です。そのためには「デジタルで何をするか」ではなく、「価値向上のためにデジタルをどのように活用するか」に知恵を絞ることが重要だと考えています。
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 執行役員兼グループCDO兼グループCIO兼グループCISO 一本木 真史氏
PwCあらた有限責任監査法人 パートナー/PwC Japanグループ 保険インダストリーリーダー 宇塚 公一
宇塚:
MS&ADグループでは新たな事業領域や新規サービスにも積極的に参入していらっしゃいます。現在はどのような取り組みをされているのでしょうか。
一本木:
MS&ADグループでは「DI」の一環として、新規ビジネスモデルの創造に取り組んでいます。例えば、三井住友海上では「Risk」を「Technology」で解決する「RisTech」という取り組みを進めています。これはお客さまのデータや企業の保有するデータと、私たちが保有するデータや統計データなどを掛け合わせて分析することでリスクを可視化し、課題解決を図るサービスです。2019年度と2020年度の2年間で約260社と取り組みを実施し、約175億円の増収につなげました。
古賀:
さまざまな企業や組織が保有するデータとオープンデータを掛け合わせて分析することで、これまで気付かなかったようなリスクを可視化できます。それを情報として提供し、役立ててもらうのですね。「RisTech」の適用範囲は多岐にわたりそうです。
一本木:
はい。企業のみならず、スマートシティや自然災害リスク対策といった社会課題の解決に向け、積極的に拡大していきたいと考えています。
一方、あいおいニッセイ同和では「デジタル募集基盤」という新しいビジネスモデルの創造に取り組んでいます。これは、近年注目されている「Embedded Finance(埋め込み型金融)」として、フィンテックを手掛けるベンチャー企業と共同で開発した次世代型保険販売システムです。
デジタル募集基盤は、複数の顧客基盤を持つ事業者(プラットフォーマー)が、自社のECサイト上で商品やサービスを提供する際に、保険商品も同時に提供できるものです。例えば旅行サイトであれば、顧客が予約した旅行商品に最適な保険商品を提示し、同じプラットフォーム上で保険の加入ができるようになります。お客さまは旅行の予約時に入力したデータでシームレスに保険契約も完了できます。
宇塚:
損害保険会社の枠にとどまらない新規ビジネスに取り組んでいらっしゃるのですね。新規ビジネスのアイデアは社員からも公募していると伺いました。
一本木:
イノベーティブなビジネスを創出していくためのアイデア発想の場として、「デジタルイノベーション チャレンジプログラム」をグループ企業横断で実施しています。これは、新たなビジネスモデルや商品・サービスなどを生み出すアイデアコンテストで、2019年度から開始しています。
古賀:
応募状況はいかがですか。
一本木:
2019年度と2020年度の2年間で、約4,000件の応募がありました。そのうち約40件は、実現化候補案件としてビジネス化を進めています。例えば、ドライブレコーダーの映像をもとにAIが道路の損傷箇所を検知し、自治体の道路のメンテナンスを支援するアイデアなどは、すでにマネタイズの目途が立っています。
宇塚:
新規ビジネスモデルを考える場合、ネックとなるのが売上見込みや予想利益といった「数字」を明示することです。これまで新規事業の立ち上げを経験したことのない社員にとって、「確度の高い数字を出す」ことは難しかったと拝察したのですが、2年間で約4,000件のアイデアが寄せられるとは驚きました。これには何か秘策があったのでしょうか。
一本木:
心がけているのは「透明性を持たせる」ことです。「どのようなアイデアが寄せられて、どれが実用化候補になったのか」を全社員が見られるようにしています。透明性を持たせてオープンにすることは、応募してくれた人に対する最低限の礼儀だと考えています。また、そうすることで、応募者のモチベーションアップにもつながりますし、社員にとっては気づきにもなるでしょう。アイデアが事業化した場合、本人の希望次第ですが、関与してもらえる仕組みを構築しています。
古賀:
アイデアを創出した人がその事業に積極的に関与できるのであれば、モチベーションもアップしますし、アイデアを出す時点で「事業化を見据えた数字の出し方」や「中長期スパンでの成長」といった観点も考慮できるようになるのではないでしょうか。
アイデアを出した人が事業に関わるという仕組みは、デジタライゼーションが進んだ組織だからこそ可能であると感じます。従来の大規模企業に見られる縦割りの組織体系では難しいですよね。そうした部分を含め、デジタライゼーションとはデジタルをツールとして利用するのではなく、ビジネスモデルの創造や人財育成といった領域までを包含して変えていく力があると考えています。
宇塚:
今後の事業ポートフォリオについて教えてください。事業ポートフォリオの多様化やその収益をどのように上げていくかは、「デジタルとビジネスをいかに融合させていくか」といった点が重要になると考えます。事業ポートフォリオの多様化についてはどのような戦略を執られるのでしょうか。
一本木:
私たちは国内損保事業を中核とするグループですが、事業ポートフォリオの分散を図る取り組みを進めています。当面の目標として、利益ベースで国内損保事業以外のウエイトを50%にすることを目指し、海外事業や生保事業などに注力してきました。この目標は2021年度末には概ね達成できる見通しです。
国内損保事業では、種目ポートフォリオの分散にも注力しています。現在は、最大種目である自動車保険と自賠責保険が過半を占めています。しかし、安全装置や自動運転などの普及により、自動車保険マーケットは中長期的には縮小することが見込まれています。
また、主要種目の1つである火災保険は、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化により11年連続の赤字です。こうした中、火災保険の収支改善とともに、国内損保の種目ポートフォリオの変革に取り組み、新種保険の拡大に注力しています。
古賀:
なるほど。自動運転自動車やMaaS(Mobility as a Service)などの台頭で、これまでの損害保険商品では対応が難しくなっているのですね。
一本木:
はい。さらにデジタル化の進展に伴い、「サイバー保険」に対する需要も急増しています。ですから、これまで想定していなかったリスクや存在していなかった新市場(ニューリスク・ニューマーケット)への対応が必要です。現在は、「テレワーク総合補償プラン」や「GIGAスクール構想販売事業者向け補償プラン」など、ライフスタイルの変化や社会のニーズに対応した商品の展開にも注力しています。
今後は、こうした取り組みによる国内損害保険事業の収益基盤強化を土台として、海外の事業基盤拡大、さらに「補償・保障前後における価値提供と収益化(MS&AD Value戦略)」と「新規ビジネスの拡大」を進めていく計画です。
宇塚:
保険に対する顧客のニーズも変化しているのですね。
一本木:
保険は経済的損失に備えるものですが、それに加え、事故・災害に対して「未然に防ぐ」「影響を減らし回復を支援する」ことが重要になると考えています。
例えば、ドライブレコーダー付きの自動車保険は運転中にアラートを発信して事故を防いだり、万一事故が発生した場合は事故状況を迅速・正確に把握したりすることで、事故解決のサポートになります。私たちは、このような機能を持つサービス一体型商品を「DX valueシリーズ」の名称で展開しており、今後さらにラインアップを拡充していく計画です。
古賀:
最後に社会課題に対する取り組みについて教えてください。先ほど気候変動による自然災害の激甚化について言及されました。MS&ADグループではこうした社会課題をどのように捉えていらっしゃいますか。
一本木:
私たちは「気候変動は課題解決の1丁目1番地」と決めて、全社員で取り組んでいます。気候変動のような大きな社会課題に対してはグループ企業が一致団結し、「社員一人一人が当事者意識を持って課題解決に臨む」という姿勢が重要です。
そして、取り組むべき社会課題は気候変動だけではありません。ヘルスケア、モビリティ、地方創生など山積しています。MS&ADグループではこれらの社会課題の解決に資する新ビジネスの創造と収益化にグループ一体でスピード感を持って取り組み、新たな事業の柱とすることで持続的な成長を実現していきたいと考えています。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー/保険インダストリーリーダー 古賀 弘之
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}