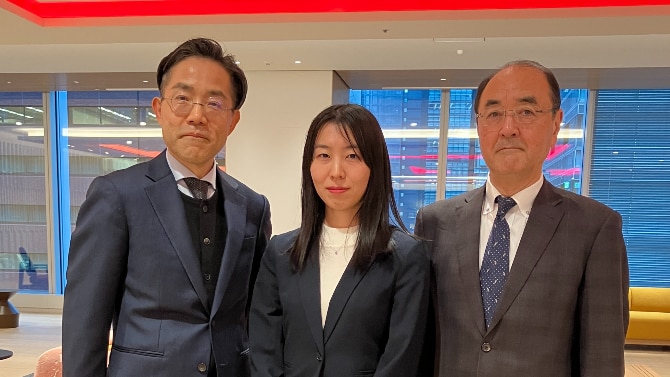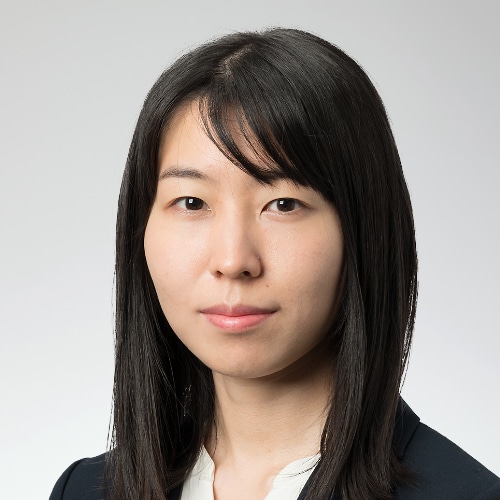{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2024-01-30
PwC Japanグループは「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というパーパス(存在意義)を追求しています。PwC税理士法人もグループの一員として、重要な社会課題の解決に取り組むという観点を踏まえ、企業の税務に関わる立場からどのような社会貢献が可能か、検討を続けています。特に、移転価格税制の領域においては、税務執行分野での提言を行うべく、「税務で社会に貢献」プロジェクトの一環としてさまざまな課題に取り組んでいます1。
2022年は、当法人の数名のクライアントの方々から、国税当局が力を入れて取り組んでいるデジタルトランスフォーメーション(DX)をテーマに、納税者としてのさまざまな意見を集めて国税庁担当者と意見交換を行いました。この取り組みを受け、PwC税理士法人のパートナー黒川兼、ディレクターの藤澤徹、アソシエイトの山崎梨佳が税務当局の対応や当法人の活動について議論。その前編では、これまでの活動の経緯や、実際に行った支援活動について振り返りました。
黒川 兼
PwC税理士法人パートナー
藤澤 徹
PwC税理士法人ディレクター
山崎 梨佳
PwC税理士法人アソシエイト
(左から)黒川 兼、山崎 梨佳、藤澤 徹
黒川:
鼎談の前編では、税務当局の対応を理解して意見する、特に、改善点を提言するにあたって重要な「正しく理解を深める」ということに焦点を当てて考えていきます。
そこで、この「税務で社会に貢献」プロジェクトのメンバーでディレクターの藤澤徹、アソシエイトの山崎梨佳との3名で、そのための具体的なアプローチを話し合う機会を設定しました。藤澤さん、山崎さん、よろしくお願いします。
藤澤:
私は40年間、税務に関わっています。最初の30年は国税当局で、直近の10年間は、PwC税理士法人で税務に携わってきました。「税務で社会に貢献」プロジェクトは、税理士法人として、税務当局と納税者とのコミュニケーションの仲立ちをする立場にあるという社会貢献の理念を発信し、納税者に税務行政への関心と適切な対応を促すというコンセプトを出発点としています。本日は、税務当局の経験者として、コメントさせていただければと思います。
黒川:
はい、お願いします。私は、税理士法人の目線からお話ししていきたいと思います。山崎さんは、当法人の新人職員ではありますが、前職の事業会社では国際税務を含め、事業部の経理財務全般を担当されていました。その経験を活かし、納税者目線でのコメントを期待しています。
山崎:
はい。「税務で社会に貢献」プロジェクトの取り組みについては、2022年10月の「PwC’s View」2に掲載された「移転価格税制の税務執行分野での提言―税務で社会に貢献」を読んで知っていました。2021年6月、国税庁から公表された「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2.0-」(以下、DXレポート)3も拝読しており、移転価格という個別分野で、どのように税務当局が取り組み、納税者としてどのような対応が必要かということを考えるきっかけになる記事でした。
黒川:
読んでいただき、ありがとうございます。私たちの専門分野である移転価格の分野では、従来から資料提出依頼書や調査官意見書を使った書面のやり取りという、リモートでの執行が行われており、DX対応に比較的なじみやすいと考えたところです。そのため、移転価格の分野は、他の調査分野に先駆けて急速にDX対応が進んでいくものと考えました。
藤澤:
ウェブサイトベースのテクノロジー・環境の整備が進んでいます。移転価格の重要なテーマの1つである無形資産については、その形成に関わっている研究所や工場が、遠方にあるケースが多いので、オンラインで調査官のいる本社会議室と繋いで調査が行われるケースが常態化してきていると感じています。
山崎:
納税者としては、そういった税務当局の対応の変化に適切に対応していきたいと考えます。
黒川:
税理士法人としては、税務当局の対応の変化を正確に把握し、納税者であるクライアントに正しく理解してもらい、必要な対応に取り組んでもらうことを心がけています。
PwC税理士法人 パートナー 黒川 兼
PwC税理士法人 アソシエイト 山崎 梨佳
山崎:
納税者の立場としては、専門家のサポートを重要視しつつも、待ちの姿勢になってもいけないと思います。納税者として、能動的にできることは何でしょうか。現在の私の立場ですと、クライアントにどのようなアドバイスができるか、考えなくてはならないと感じています。
藤澤:
税務当局は昔から盛んにパンフレットを配布したり、説明会を開催したりして、納税者に対して税制や執行に係る情報の周知に努めてきました。特に、ウェブサイトが普及してからは、最新動向を常にアップしています。オンラインですから、昔のようにわざわざ税務署や国税局に赴かなくても、自分の都合の良い時に必要な情報を入手できますし、出典を明示すれば職場での説明資料への引用も手軽にできます。
山崎:
確かに、前職で役員や営業などの税務以外の部署の方に対しては、国税庁の移転価格事務運営指針4、特に、別冊の参考事例集5を活用しながら説明を行っていました。特に、移転価格などの国際税務の仕組みや当局の考え方を説明する際に、非常に有用です。参考事例集には取引図を使った事例が掲載されており、分かりやすかったのですが、工場や研究所の方々に説明するには、もう少し初歩的なものがあればよいと思っていました。
藤澤:
そういうご相談をクライアントから受けることがあります。初歩的な観点のものというと、財務省の国際課税のウェブサイト6があります。このサイトは、図表を使って、簡潔にポイントがまとめられていますので、税務以外の部署の方にも分かりやすいと思います。税務ガバナンス向上の観点からも、税務部署以外の方々に、税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)以降、課税リスクが着目されている国際課税、特に移転価格について理解してもらうことは有効だと思います。
黒川:
私自身は国税庁が毎年6月に公表している「国税庁レポート」の内容に着目しています。国税庁レポートとは、国税当局の年次報告書のようなものです。
山崎:
「国税庁レポート」というものがあることを知りませんでした。着目し始めたのは、何か理由があったのですか。
黒川:
少し古い話で恐縮ですが、私がPwCで移転価格に本格的に取り組んで間もない2004年に、取引単位営業利益法の導入という、日本の移転価格にとって大きな税制改正がありました。2004年版国税庁レポートには、その導入の背景として、日系企業の製造拠点の海外移管について解説されています7。また翌年の2005年度版には「移転価格問題に関する最近の動向としては、我が国企業の製造拠点の海外移転の増加に伴い、例えば、本社機能を有する親会社から製造技術や製造ノウハウといった無形資産を製造子会社に供与するとともに、経営指導や業務管理などの役務の提供が行われるケースが見受けられるなど、製造子会社に供与される無形資産に係る適正な対価を授受する必要が出てきました。このような無形資産取引については、平成16年度税制改正で導入された取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM)の適用も視野に入れて、円滑な執行を図るためのノウハウの蓄積に努めています」と書かれています8。
山崎:
私も報道や前職での上司や先輩から聞いた知識しかありませんが、まさに、この20年間の当局の移転価格調査の執行そのものですよね。
黒川:
そのとおりだと思います。この間、私は、納税者であるクライアントに移転価格税制の仕組みはもちろん、具体的な当局の執行、どういったところに移転価格課税リスクがあるのか、それをどのようにして把握し改善していくのかといったことを説明、アドバイスしてきました。
山崎:
まさに、「税理士法人として、税務当局と納税者とのコミュニケーションの仲立ち」をされてきたわけですね。特に、ここ数年ではBEPSという大きな国際課税の見直しがありましたが、この点、国税庁レポートからは、どのようなことが読み取れるのでしょうか。
黒川:
レポートの移転価格に関する部分について、最新の2023年版と10年前の2013年版を読み比べ、簡単な対比表を作成してみました。何か気づいたことはありませんか。
| 2013年版 | 2023年版 | |
| 運用面 | 法令解釈通達や事務運営指針の公表や改定 | 海外取引法人等に対する法人税課税調査を実施し、移転価格税制の運用の明確化を図る 多国籍企業情報の報告制度により、多国籍企業グループのグローバルな活動や納税実態を把握 |
| 課題面 | 取引の内容の複雑化や無形資産を伴う取引の重要性の高まり | 国際的な二重課税や租税回避を防止 |
| 海外当局との関係 | 国際的なルールとして、OECD移転価格ガイドラインとの整合性を図る 国際的な情報交換や調査手法の共有にも取り組む必要性 |
相互協議や事前確認により、外国税務当局との連携を強化し、納税者の予測可能性を高める |
山崎:
2013年版では、移転価格税制運用のための問題認識やルール作りといった事前準備的な内容との印象を受けます。それに対して、2023年版はある程度の実績を踏まえて、そこから生じてきた課題に取り組むといった印象を受けました。
藤澤:
そのとおりだと思います。日本に限らず、多くの国が2013年当時は、同じような問題意識を持ち、そのための新たなルール作りの必要性を意識していたのではないのでしょうか。それが、G20という大きな規模でのBEPSにつながっていったのではないかと個人的には思っています。
黒川:
やはり、税理士法人は、こういった長期的な観点から移転価格税制の執行を正しく理解し、納税者がどのような対応を採るべきか、一緒になって考えていくことが求められていると改めて感じました。移転価格は、取引相手である国外関連者の課税リスクにも影響しますので、納税者としては、自らの課税リスクはもちろんのこと、国外関連者との連携を密にすることが重要です。その際、PwCの海外ネットワークも「仲立ち」の一員として重要となってくるわけです。
山崎:
BEPSの過程でみられたように、各国当局の協力体制を考えると、納税者側も、その仲立ちをする税理士法人も、各国との協力体制が必要になるということですね。
藤澤:
BEPS以降、国税庁のウェブサイトには「国際税務関係情報」という、移転価格はもちろん、国際課税全般に関しての情報を取りまとめたサイトが開設されています。特に移転価格については、BEPS最終報告書で、納税者の自発的な税務コンプライアンスを高めることが謳われたことから、「移転価格ガイドブック」が公表されました。これを見ると、移転価格文書の中でも、特にローカルファイルを中心とした税務コンプライアンスの維持・向上、課税リスクの低減に当局が力を入れていることが読み取れます。
山崎:
私は当法人に転職して最初の仕事が、日系企業のローカルファイルの作成でした。その際に、海外のPwCメンバーファームの担当者との意見交換や打ち合わせを行いました。当局が注目しているローカルファイルを作成するにあたっては、一層、そういったコミュニケーションが大事だったのですね。
黒川:
そうですね。私たちのクライアント、その国外関連者、国外関連者所在地国のPwCメンバーファームと4者間で良好なコミュニケーションをとることは、移転価格にとって大きなポイントです。
藤澤:
当局にとっても、事実関係や考え方が各者バラバラですと、二重課税の解決の支障にもなると思います。情報共有や共通の理解は重要ですから、専門家としての税理士法人の活躍が大いに期待されるところです。
黒川:
国税庁の移転価格調査は、ますます高度化・国際化が進んでいます。納税者としては、国税庁の取り組みの変化に適切に対応していくことが求められます。そのためには、税務当局の情報を常にチェックし、税務ガバナンスを強化し、税理士法人との連携を密にすることが必要です。PwC税理士法人は納税者のサポートを行うとともに、税務当局とのコミュニケーションの仲立ちをすることで、税務で社会に貢献することを目指したいと思います。
山崎:
国税庁のウェブサイトもですが、PwC税理法人のウェブサイトも、前職のころから仕事はもちろん、自己研鑽の目的でも活用していました。
黒川:
移転価格については、クライアント目線で多面的な切り口でサイトを構成しています9。移転価格管理、コンプライアンス対応、調査対応および事前確認という基本的なものはもちろん、最近の各国当局の動向を踏まえて、移転価格管理におけるテクノロジー活用に係るページも設けています。
藤澤:
サイトだけではなく、当法人の知見や経験を生かしていただくために、国際税務領域の人材育成支援を目的とした有料のe-learning講座であるTax Academy(e-learning 講座プラットフォーム)10の開設や、書籍「現場で役立つ「移転価格」入門」11の発刊も行っています。この書籍では、架空の製薬会社を舞台に経験の浅い職員とベテラン職員、PwC税理士法人のパートナーの3名の対話を通じて、移転価格における最近の重要課題である無形資産について解説しています。
山崎:
製薬会社が舞台ということは、特殊な無形資産を取り扱っているのでしょうか。
藤澤:
そうではありません。移転価格における無形資産を取り扱う際の基本的アプローチを、図表を豊富に使いながら、OECD移転価格ガイドラインや移転価格事務運営指針を対話形式で分かりやすく解説しています。詳細は、以下をご参照ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/publication/tax-transfer-pricing2401.html
PwC税理士法人 ディレクター 藤澤徹
1 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202210.html
2 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202210/40-07.html
3 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation/index.htm
4 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/00.htm
5 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/pdf/bessatsu.pdf
6 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/index.htm
7 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2004.pdf(23頁)
「移転価格問題に関する最近の状況として、我が国企業の製造拠点の海外移管の増加に伴い、無形資産・役務提供に関係する取引の重要性が高まっています。このような取引について、我が国親会社が海外子会社から適正な対価を受け取るよう、企業経営者にその重要性を認識していただく必要があります。」
8 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2005.pdf(23頁)
9 https://www.pwc.com/jp/ja/services/tax/transfer-pricing.html
国税庁、東京国税局での30年間の勤務経験を持つ国際課税の専門家。2014年2月にPwC税理士法人の東京事務所に入社。東京国税局では、15年以上にわたって大企業、多国籍企業の移転価格調査の企画・実施、事前確認審査を担当。国際情報第一課の上席国際専門官として、移転価格調査事案のすべての管理および他国税局の移転価格調査事案のサポートを担当。国税庁での3年間の相互協議経験も有し(米国、オーストラリア、インド、スイスなど)、国税庁調査課国際係長3年間の在任中には、OECD租税委員会第6作業部会のメンバーとして、PE帰属所得ルールであるOECD承認アプローチ(AOA)のドラフトづくりにも関与。OECD会議、タイ駐在、相互協議、タイ・インドネシア・中国および発展途上国への知的支援を通じ、各国の国際課税担当者とは真摯に深い信頼関係を構築。
※法人名、役職、インタビューの内容などは掲載当時のものです。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}