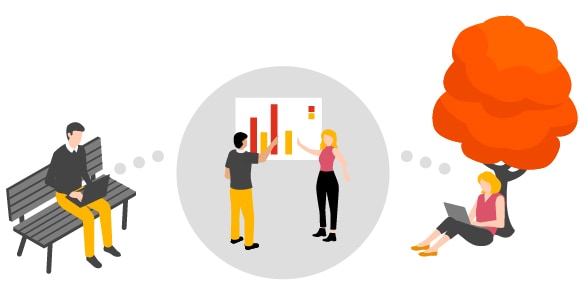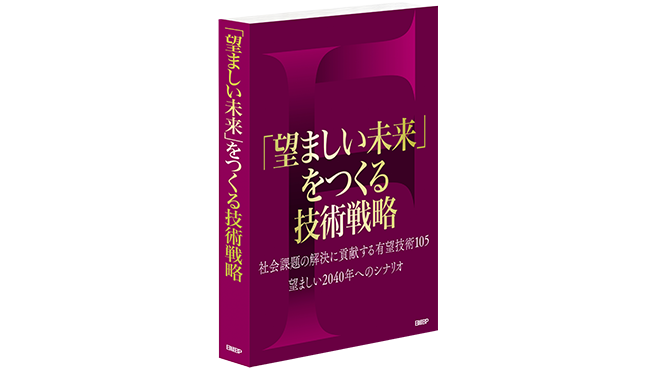{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2021-08-17
多発する自然災害や感染症の流行などによって事業環境は一変し、不確かな時代に入ったことで、従来のように現在を起点とした将来予想は困難を極めています。
PwCでは、未来を見通し、そこから導かれる複数のシナリオから次の一手を見定め、迅速に行動を起こすことが、これからの企業の発展に不可欠であると考えます。
そこで本シリーズでは、現在の延長線上にある「おそらく起こる未来」に加え、今後登場が期待されている技術を起点にした「より望ましい未来」の双方向から、2030年から2040年時点での立場で未来シナリオを提示し、その実現の鍵となる重要なドライバーを解説します。
読者の皆様に未来を見通すヒントと幅広い可能性を提示できれば幸いです。
さて、今回はどのような未来が待っているでしょうか。
今回は、街づくり・モビリティ分野にフォーカスし、望ましい未来を考察します。「おそらく起こる未来」では、大都市中心のスマート化とMaaS(Mobility as a Service)の拡充が実現する一方で、地方の空き家やコミュニティ、交通、治安といった問題は解消まで道半ばとなっていることが想定されます。「より望ましい未来」では、単にテクノロジーに依存するだけのスマートシティモデルから脱却した、「新しい生き方、働き方、暮らし方の実現を加速するため、課題を解決するために適切にテクノロジーを活用した都市」が日本各地に勃興し始めていることが考えられます。
北欧諸国やフランスなどでは、出産および育児に対する手厚い手当とサポートや、多様な夫婦形態が法的に認められたことで、2020年前後から出生率が緩やかに回復しました。米国や英国においても産休および育休後のキャリア継続が容易なことから、出生率の低下が食い止められました。他方、2020年時点で抜本的な少子化傾向の改善が見られなかった日本は、2030年には総人口は1億1,912万人、生産年齢人口比率は57.7%まで減少し、結果的に高齢化率は31.2%にまで上昇しました。
人口構造の変化により、心身ともに健康的で最低限度の生活を送るために必要な「安心」「安全」すら担保されない地域が2030年の日本には数多く生じてしまいました。人口減少が著しい地方都市を中心に、公共・公益サービスの維持も困難となっています。また、医療や教育といった拠点型サービスは、総人口の減少により需要密度が低下し、一部の拠点ではその維持が難しい状況となりました。一方、電力、ガス、水道、通信、公共交通、あるいは道路・橋梁・トンネルなどの整備、治水治山事業などのネットワーク型サービスは、総人口減少による需要密度の低下により、利用者1人あたりの維持コストが上昇しています。
日本の多くの地方都市においては、地域の魅力の低下、需要・歳入の減少、収支の悪化、公共・公益サービスやインフラ品質の低下が連続的に発生する「負のスパイラル」に歯止めがかからない状態となっています。一方で、大都市においても大都市固有の課題が数多く残されています。2020年のコロナ禍に伴う行動様式の変化によってリモートワークが進展したものの、全ての業種・業態において定着するには至らず、10年が経過した今、大都市は変わらず人口過密な状況となっています。
スマートに大都市と地方都市の課題を解決するためのアーキテクチャー(基本構造)は、端的には下図表のような「3つの層と11の機能の有機的な組み合わせ」によるとされています。3つの層とは、一番の土台となる「安全」層とその上に築かれる「安心」層、そして「賑わい」層で構成されます。11の機能とは、住民がその街で生活する上で必要となる次の基本的な機能を指しています。
2030年頃には、「センサーやAIなどを駆使した農業の効率化」や「ドローンやGPSなどの活用による産業の高度化」「多様なデータのオープン・データ・プラットフォーム構築」「データアナリティクスによる渋滞の解消」など、11種類のスマートシティの機能がさまざまなテクノロジーによって実装されています。
図表:スマートに大都市と地方都市の課題を解決するためのアーキテクチャー
より望ましい2030年において、大都市または地方都市の課題解決に一定の成功を収めた都市は、いずれもデータを利活用して社会課題を解決する「仕組み」づくりに成功しています。
時代や地域の環境を反映したさまざまな社会課題が生まれる現実がある以上、一時的な取り組みではなく、継続的な取り組みを維持する「仕組み」が不可欠です。そのため、2030年において一定の成功を収めたとされるスマートシティには、住民がデータを提供する「仕組み」、それらを適切に管理・運営する「仕組み」、社会課題への取り組みの検討にデータを利活用する「仕組み」が組み込まれています。
スーパーシティ法(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案)の成立と施行、「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」の成果、コロナ禍による生活様式の変化などが絡み合い、2020年ごろから大都市とその周辺のベッドタウン、さらにそこから離れた地方都市の在り方は変化を見せてきました。
2020年から2021年にかけてのコロナ禍以降、人々の暮らしは大きな変化を余儀なくされました。リモートワークに関する技術の進歩と社会通念の変化によって、エッセンシャルワーカーに該当しない企業や職種を中心に、ワークスタイルとライフスタイルをより柔軟に選択をすることが一般的となってきていました。
コロナ禍において各業界を代表する大企業が全面的なリモートワークにシフトしたことを皮切りに、多くの企業が都市部におけるオフィスの規模縮小とリモート中心の働き方への移行を同時並行的に進めてきました。そしてオフィスと働き方の変化は、徐々に個人の生き方の変化へと影響を及ぼしてきたのです。いわゆる電車通勤エリア外にある、自分や家族の趣味嗜好やライフスタイルに合わせた地域に居住する人の割合が増大し、その結果として「ただスマートであることを目的化したテクノロジードリブンの都市」ではなく、「新しい生き方や働き方、暮らし方の実現を加速し、課題を解決するために適切にテクノロジーを活用した都市」が新しい志向に目覚めた企業や個人の共感を獲得し、人口減少下の日本における新たな繁栄モデルを切り拓いています。
2030年、日本の人口は1億1,662万人となり、ピーク時の2010年と比較して約1,200万人減少しました。2030年においては都市のスポンジ化がより進み、必要な生活サービス施設が失われ、インフラの維持管理がおろそかになることで、生活の質が低下しています。このようなスポンジ化の進行は、特に運転免許の返納によって公的交通機関に頼らざるを得ない高齢者の生活に大きなインパクトを与えています。
より望ましい未来においては、都市とモビリティ、ドローン、医療、防災をシームレスに連携させることで解決の糸口を掴む都市も出てきました。「移動の制約によって人生100年時代の可能性を狭めない都市」というコンセプトを打ち出した都市は、2020年頃から複合的な施策を展開することで、人生100年時代の生活の質を高めています。
2020年前後から高まってきたESG投資やSDGsに対する意識によって、企業や個人はよりクリーンかつ持続可能な暮らしや、新しい資源を可能な限り使用しない循環型社会への関心を高めてきました。同時に、再生エネルギーをはじめとする技術の高度化によって、2020年時点ではただの理想であった未来の街の姿が、2030年の今は実現可能なものとなってきました。求めていた機能を実装する環境が整備され、以下のような施策を展開することで、クリーンで持続可能な循環型社会に関心を持つ個人や産官学を引き付ける都市が登場したのです。
超高圧水素インフラなどの整備により、より環境負荷が少ない水素社会へシフトしました。同時に、高温超電導技術を用いた送電や、マイクロ波によるワイヤレス給電を状況に応じて使い分けることにより、送電効率が向上しました。また、ポストリチウムイオン電池や固体高分子形燃料電池といった蓄電方法のブレークスルーも、エネルギーエコシステムの高度化に寄与しています。同時にマテリアルズインフォマティクスによって素材レベルのブレークスルーも進展しました。
再生エネルギーの獲得には天候などによる不安定さが伴うため、一定量の火力発電に加えて、2020年以降に米国で研究および実装が進んだ、モジュール化された小型原子炉を組み合わせる場面が出てきています。
都市の各所に人工光合成や熱電材料を活用することで、より一層CO2を削減した暮らしが実現しています。
都市OSを結節点として、モビリティのFMS(フリート・マネジメント・システム)や、各種エネルギー・マネジメント・システムであるHEMS、BEMS、CEMS、FEMS(ホーム・ビルディング・コミュニティ・ファクトリーなどの各種エネルギー・マネジメント・システム)が連携することにより、ヒトやモノの移動の最適化・エネルギー消費の最適化を実現しています。
循環型社会の実装機運の高まりと、地政学リスクや食資源獲得競争のトレンドから地産地消が進み、またフードテックが進展したことで、わがままな食生活と持続的かつ循環的な食生活の両立に成功しました。これまでは「スマートシティにおけるスマートなアーバンライフ」と、「人間的かつ心豊かで、持続的な暮らし」は対立する概念でしたが、望ましい変化を遂げた未来において、この対立構造は超克されました。
この対立構造を超克するため、例えば技術的なブレークスルーとして、時空間をデカップリングするためのデジタル・ツイン・ワークプレイスやデジタル・ツイン・シティが進展しました。技術的なブレークスルーのみでなく、時空間デカップリングワークライフを送る人々を受け入れる「働く場や企業」、もしくは「労働と対価をデジタル上で交換するプラットフォーム」のような仕組みの進化、整備も不可欠となります。
より望ましい未来に向けては、データを利活用して社会課題を解決する「仕組み」づくり、技術を活用したクリーンで持続可能な循環型のビジョンの実現、デジタル・ツイン・シティの進展などにより、「ただスマートであることを目的化したテクノロジードリブンの都市」ではなく、人口減少や人生100年時代を見据えた「新しい生き方、働き方、暮らし方を実現する都市」の出現が期待されます。
『「望ましい未来」をつくる技術戦略 社会課題の解決に貢献する有望技術105 望ましい2040年へのシナリオ』(日経BP刊)では、2040年をターゲットとした「12の望ましい未来」を描くとともに、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を抽出し、技術解説や研究の動向を示したうえで、生み出す市場、その規模、市場化の課題を分析しています。
【参考:文章上の関連技術の定義・説明】
| 技術名 |
概要 |
|---|---|
| ドローン | 定義はさまざまあるが、航空法の定義では飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g未満のものを除く)を示す。いわゆるマルチコプター、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが該当する。 ※ただし、200g以下の機体もドローンと呼ぶことが多く、人が乗る場合でも小型で自動操縦できる機体や水中を移動する無人機をドローンと呼ぶこともある。 |
| 超高圧水素インフラ | 燃料電池自動車の世界最速普及を実現するための水素ステーションなどに係る超高圧水素技術(1000気圧と同等の100MPaの水素を安全かつ安価に輸送・貯蔵・供給するための技術)などを指す。 |
| 高温超電導技術 | 高温超電導体とは安価な液体窒素での冷却により実現できる超電導体を指す。なお、超電導とは、電気抵抗がゼロになる現象のことであり、超電導技術により電気抵抗がゼロであることから発熱が起きず、電流をエネルギーロスなく半永久的に流すことが可能になる。 |
| ワイヤレス給電 | 電線を使わずに電力を伝送する技術のことであり、「WPT(Wireless Power Transfer)」「ワイヤレス電力伝送」「無線給電」「非接触給電」などとも呼ばれる。本稿では主に「ワイヤレス給電」の名称を用いている。特に電力をより遠距離に1対Nで届ける「空間伝送型ワイヤレス給電」が実現されると、ケーブルやバッテリーといった目に見える形で電気を意識することがなくなるため「インビジブルパワー」とも呼ばれ注目されている。 |
| ポストリチウムイオン電池 | 現行のリチウムイオン電池の性能限界を超える可能性があり、かつ、社会に対し一層のポジティブなインパクトを与えることが期待される技術群を指している。具体的には、金属空気電池、リチウム硫黄電池、多価カチオン電池、ナトリウムイオン電池などが挙げられる。 |
| 固体高分子形燃料電池 | 固体高分子形燃料電池(PEFC:Polymer Electrolyte Fuel Cell)は、燃料電池の1つで水素と酸素の電気化学反応により、電力と熱を発生させる技術。発電の際に発生するのは水のみであり、二酸化炭素などの環境に問題となる排気ガスは排出しないゼロエミッション電源として注目される。 |
| マテリアルズインフォマティクス | 効果的に材料開発を行うデータ科学を用いた新材料開発手法を指す。機械学習/深層学習などのデータ科学を活用することで、開発期間の短縮、開発コストの低減を目的としている。 |
| 小型原子力発電 | SMR(Small Modular Reactor)と呼ばれる小型原子炉による発電を指す。30万キロワット以下で非常に小規模であり、その構造のほとんどを工場で組み上げることにより品質向上と工期短縮を図り、初期コストの大幅な削減が可能。また、最も重要な安全性の面でも、原子炉出力が小さいことから炉心冷却機能喪失時に自然冷却による炉心冷却が可能なことに加え、重力による冷却水の注水など受動的機器(パッシブシステム)の採用により安全性の強化とシステムの簡素化が図られている。 |
| 各種エネルギー・マネジメント・システム | 電気・熱・ガスなどのエネルギーの見える化や電力運用の最適化などを実現するシステムを示す。データを表示して省エネ行動につなげるケースや、自動的に使用量を調整するケースなど、需要側、供給側、送電側・監視側の連携程度によりさまざまなシステムが存在する。代表的な例としては、BEMS(Building and Energy Management System)、HEMS(Home Energy Management Service)、FEMS(Factory Energy Management System)、CEMS(Community Energy Management System)が挙げられる。 |
【参考文献】
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}