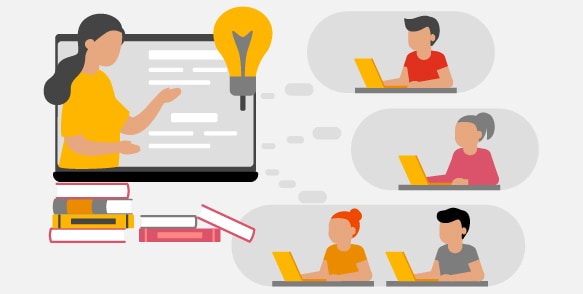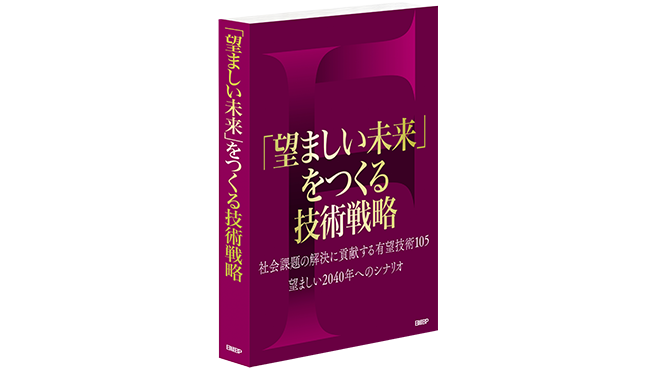{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2021-09-01
多発する自然災害や感染症の流行などによって事業環境は一変し、不確かな時代に入ったことで、従来のように現在を起点とした将来予想は困難を極めています。
PwCでは、未来を見通し、そこから導かれる複数のシナリオから次の一手を見定め、迅速に行動を起こすことが、これからの企業の発展に不可欠であると考えます。
そこで本シリーズでは、現在の延長線上にある「おそらく起こる未来」に加え、今後登場が期待されている技術を起点にした「より望ましい未来」の双方向から、2030年から2040年時点での立場で未来シナリオを提示し、その実現の鍵となる重要なドライバーを解説します。
読者の皆様に未来を見通すヒントと幅広い可能性を提示できれば幸いです。
さて、今回はどのような未来が待っているでしょうか。
今回は、教育分野にフォーカスし、望ましい未来を考察します。「おそらく起こり得る未来」では、6・3・3・4制の日本の教育システムのいずれのフェーズにおいてもデジタル教育が進み、教育の機会均等とデジタルアップスキリングが進むことが想定されます。「より望ましい未来」では、単に学ぶだけではなく、より自発的かつ偶発的に学びの環境をアップデートし続けられるようになったり、過去の経験を蓄積した上で自分の目指す方向性に関する気づきを得て、それらを考慮に入れながら新たな学びを引き寄せられるようになったりすることが考えられます。
日本においては教育基本法、学校教育法の公布後、小学校6年間、中学校3年間、高校3年間、大学で4年間という6・3・3・4制の学校制度が形作られました。学校が基本的な学びの場として存在し、教師と生徒という関係の下で、学びが醸成されてきました。
2020年からのコロナ禍に伴う行動様式の変化は、学校における教育環境にも大きく影響を及ぼし、リモート授業の実施をはじめデジタル活用が進む契機となりました。必要とされたのはリモートで教育が行える環境であり、各家庭のデジタル環境や教師のデジタルリテラシーによって対応に差が出たものの、デジタルを活用した教育環境は加速度的に進展したと言えるでしょう。
その結果、2030年の学びの環境においては、リモートで取り組めるものはリモートで取り組むことが一般的になっています。授業内容はアーカイブされ、後日見返して宿題などに活用することもできるようになりました。すべての学校で、児童・生徒全員がPCとタブレットを所有し、自宅と学校それぞれの勉強で使い分けられるようになっています。語学学習においては海外の学校と提携して友達づくりが進められるなど、より実践的な取り組みが進められるようになっています。
2030年の教育現場では、オンライン参加の生徒とリアルに参加する生徒がより臨場感を持った形で1つの教室で学び合う光景が新たな日常となっています。オンラインで参加する生徒がスクリーン越しに教師やクラスメートとコミュニケーションを取ることはもちろんのこと、自身の代わりに分身ロボットがリアルな教室での授業に出席することすら当たり前になっています。この「コミュニケーション・アバター・ロボット」が教室内を動き回れるようになったことで、リモート環境から授業に出席している生徒は、この分身を通じてプレゼンテーションやインタラクティブな議論の展開が可能となりました。これによってさらに実体の伴った討議が進められるようになり、良質なアウトプットや新たなイノベーションに向けた機会が創出されています。また、アバターの活用は教室だけにとどまりません。大学では、これまでリアルな世界においてキャンパスごと、学部ごとに隔てられていた物理的および心理的な「壁」がバーチャルキャンパスの活用により低くなっています。学部間の交流や討議、研究は、よりゲーム感覚が強くなりました。これを契機に新たな研究成果やビジネスの創出を活発化させています。
小学校6年間、中学校3年間、高校3年間、大学で4年間という学校教育制度を経た後に社会人として就労し、65歳以降の老後人生を送る、という一方通行な教育システムの概念は変容しつつあります。人生100年時代を見据えた技術や社会環境の変化に応じたリカレント教育の重要性・制度が浸透し始めています。
かつて古典文学を研究していた社会人が最新のテクノロジーやプログラミングを学び直す、かつてコンピューターサイエンスを突き詰めていた社会人がAI(人工知能)との共存の在り方を哲学的観点から学び直す、かつて地球物理にのめり込んだ社会人が、地球温暖化により差し迫る自然災害(地震・火山噴火・洪水など)から住民の命を守るための「伝える」コミュニケーションを学び直す――。そんな異分野への関心と新たな知識を積み上げながら、社会人になってからの約70年~80年間をより柔軟に、充実して過ごすスタイルが受け入れられ始めています。生涯にわたり1つの分野の専門性を磨くことも、他分野を自由に探索することも、個々人が長年にわたって選択していくことも可能となった結果、学校教育における、いわゆる「文系」「理系」の区別が大きな意味を持たない価値観も浸透してきました。
そして生涯学習が浸透し、ITやAI、ビッグデータ、ロボット工学などの先端技術の発展に対応し、それらと共存していくためにeSTEM(STEM:Science, Technology, Engineering and Mathematics。科学・技術・工学・数学の教育分野の総称を示す)教育や、自ら課題を見つけ、解決することを重視したSTEAM(STEMにArtを加えた言葉)教育に基づくカリキュラムの重要性が一層増しています。従来の工業的な視点にとどまらず、先端技術や技術の向上を環境に配慮した設計・実装にどのようにつなげるか(eSTEM)、知の創造性を養い、技術による便益や幸福などの価値観をどう並行して追求するのか(STEAM)といった視点での教育がより重視されています。
パーソナルデータのさらなる蓄積と連携により、知の「情報銀行」が確立、進展しました。また、AI技術の発達により、自身の学習履歴から生涯にわたる学びの道筋をより円滑に描きやすい社会が実現しています。日々の読書記録や新聞記事の閲覧記録、オンライン講座の修了履歴、PCでの資料作成や検索の際の動作および思考パターン、趣味で参加している地域サークルの情報――。これらの統合・分析により自身の強み、あるいは克服すべきスキルや知識の傾向を容易に把握でき、同時に学びのレコメンドを受けることもできます。
人生100年時代を見据えた生涯学習制度が確立し、社会に浸透することで、人々の学びに対する関心や価値も高まりました。自身で学びの情報の管理をしていく、自分の人生を学習により自身が主導していくというオーナーシップも浸透しており、このような学びを蓄積すると同時にAIが別の経験を促し、セレンディピティの誘発につながっています。「学び」の情報が観光やヘルスケアといった異なる分野や産業のパーソナルデータと紐づけられていくことで、2020年代には起こり得なかった人材交流が実現し、イノベーションの創出はもちろんのこと、孤独感からの脱却による健康寿命の向上といった波及効果まで生まれています。経験をシェアするためには、外界をセンシングして現在の環境をみることができるXR(Extended Reality)技術、その情報を蓄積する情報銀行、そして自分の履歴を管理するためのブロックチェーン技術が活用されています。これらは個人の経験をシェアするために、バーチャルとリアルな情報をやり取りするための情報技術であるコモングラウンドによって、3D情報の記述のために実装されています。
より望ましい未来に向けて、企業は教育に関するコンテンツと、経験をシェアするための技術開発に取り組むことが期待されています。本質的には、個人(従業員および消費者)は生涯におけるどのタイミングでも学ぶことのできる環境を得られるため、就業環境と就労機会をより柔軟にしていくことが求められます。
『「望ましい未来」をつくる技術戦略 社会課題の解決に貢献する有望技術105 望ましい2040年へのシナリオ』(日経BP刊)では、2040年をターゲットとした「12の望ましい未来」を描くとともに、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を抽出し、技術解説や研究の動向を示したうえで、生み出す市場、その規模、市場化の課題を分析しています。
【参考:文章上の関連技術の定義・説明】
| 技術名 |
概要 |
|---|---|
| XR(VR/AR/MR)テクノロジー | VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを総称して、「XR(Extended Reality)」という。XRによる新しいインターフェースは人間、コンピューター、デジタル環境間のより自然で摩擦のないコミュニケーションを可能にし、ユーザーをよりデジタルの世界に近づける。音声やテキストなどの従来のインターフェースに加えて、感情、触覚、全身の動き、脳波、行動などをユーザーデータ、環境または状況などの文脈に沿ったデータと組み合わせることで、ユーザーにインサイトを提供する。それにより、実世界、デジタル的な世界と直感的に対話できるようになる。 |
| ブロックチェーン | 分散型のデジタルデータベースであり、広い意味では信頼性・匿名性の高い方法でネットワーク内に発生した取引を記録・確認する、ソフトウェアアルゴリズムを用いたデジタル台帳のことを指す。 |
| 情報銀行 | パーソナルデータを含めた多種多様かつ大量のデータの円滑な流通を実現するために、個人の関与の下でデータ流通・活用を進める仕組みのこと。 |
| コモングラウンド | デジタルの世界とフィジカルの世界が共存できるよう仕様や技術がまとめられた、両者を分け隔てなく行き来するためのプラットフォーム。アバターとなるロボットが物理空間を認識するためには、そこに存在するものを認知し、情報をデジタル(データ)記述化する集積場が必要となる。さらに言えば、デジタル化を推進する上では私たち自身が、その利便性やリスクに対する共通理解を持つ必要もある。こうした情報の汎用的な仕様が社会的に共有されるのを経て、物理空間とデジタル空間をつなぐものがコモングラウンドと称されている。 |
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}