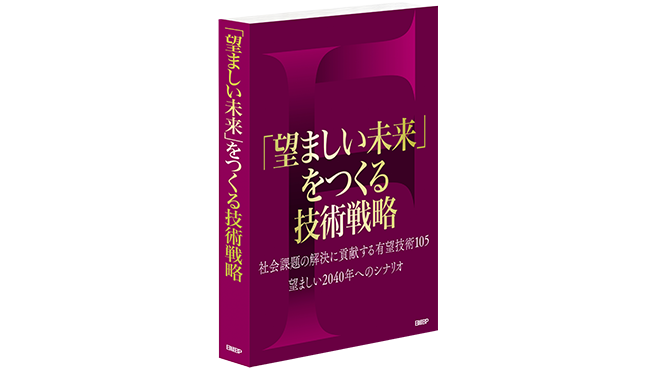{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
2021-09-01
多発する自然災害や感染症の流行などによって事業環境は一変し、不確かな時代に入ったことで、従来のように現在を起点とした将来予想は困難を極めています。
PwCでは、未来を見通し、そこから導かれる複数のシナリオから次の一手を見定め、迅速に行動を起こすことが、これからの企業の発展に不可欠であると考えます。
PwCコンサルティングは、このようなコンセプトに基づき、12の未来像を描き、この12の未来それぞれに紐づく105の技術の展望についてまとめた書籍『「望ましい未来」をつくる技術戦略』を発刊しました。
書籍の中では12の未来を描きましたが、今回お届けした「2040年 未来シナリオ」シリーズでは、その中から4つの未来のエッセンスと、今回、新たに書き下した1つの未来を取り上げました。皆さんは、どのような感想を持たれたでしょうか。未来に登場する個々の技術や個別の事象は、時として実現しなかったり、別のものに置き換わったりする可能性があります。しかし、私たちが伝えたかったことは、「未来を予測し、当てにいく」ことではなく、「望ましい未来を描き、実現していくこと」にあります。
人が存在する限り、未来はより望ましいものに変えられます。私たちは社会課題からメガトレンドを把握し、未来を予測するというアプローチに加え、活用が期待されている技術を起点にした未来との双方向での掛け合わせを示すよう試みました。可変要素がある前提での未来シナリオを描くことができると考えたからです。未来は、一通りの方向性だけではありません。それぞれの描く未来の積み重ねが、今、この現実をつくっていくはずです。
皆さんが考える望ましい未来とは、何でしょうか。それは、どのような技術で達成できるものでしょうか。
望ましい未来の実現は、隣にいるその人を幸せにするように願い、行動することから始められます。ちょっとした出来事の積み重ねが、人、技術、社会をアップデートするように導くのです。そうした意思が集まることで、企業、行政もより良い未来を折り合わせて、さらに創発的な未来を実現することができるようになります。
より速く環境が変わる現代では、時として意図しない未来に向かって進んでしまうこともあるでしょう。そのような局面でも、より望ましい未来像を描こうとすれば、いくつもの可能性が開かれるはずであり、それぞれの高い専門性を持ち寄ることで、次のステージに行けると信じます。
私たちPwCは、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というパーパスを実現するため、望ましい未来と、その未来を実現するための技術の在り様をこれからも提案していきます。
『「望ましい未来」をつくる技術戦略 社会課題の解決に貢献する有望技術105 望ましい2040年へのシナリオ』(日経BP刊)では、2040年をターゲットとした「12の望ましい未来」を描くとともに、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を抽出し、技術解説や研究の動向を示したうえで、生み出す市場、その規模、市場化の課題を分析しています。
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}
{{item.text}}

{{item.text}}