
はじめに
プライベート・エクイティファンド等の投資ファンドにおいて、その投資先企業の価値をより高めたり、投資先企業への投資に柔軟性を与えたりする手段の1つとして、継続ファンドを使用した投資形態の採用を検討する事例が増えています。
継続ファンドを採用することにより、投資ファンドはさまざまなメリットを得られますが、選択するスキームによって、貸借対照表や損益計算書に与えるインパクトが変わる可能性があります。
本稿では、継続ファンドとはどのようなものかを説明した上で、継続ファンドを採用したときに想定される2つのスキームを取り上げ、それぞれのスキームで生じる主要な会計論点に関して、日本基準の単体と連結、および国際財務報告基準(IFRS、連結)における一般的な会計処理について解説します。本稿で取り上げるスキームの1つ目は、ファンドのジェネラルパートナー(以下、GP)の共通支配下の取引に該当した場合です。また、2つ目は、別の新規投資会社からの出資を受け、その新規投資会社が投資先企業の支配持分を保有している場合です。
なお、文中の意見に係る記載は筆者の私見であり、PwCJapan有限責任監査法人および所属部門の正式見解ではないことをお断りします。
1 継続ファンドの概要
一般的な継続ファンドを使用した投資形態は、GPが運営する既存ファンドの保有資産を、同一のGPが組成した新規のファンドが取得するというものです(図表1)。ここでGPが組成する新規のファンドのことを「継続ファンド」と呼びます。
図表1:一般的な継続ファンドの投資形態

この際、既存リミテッドパートナー(以下、LP)が出資を完了させ、その代わりに新規LPが出資を行うことや、新規投資会社が追加で出資を行うケースも考えられます。
日本において継続ファンドを実際に採用して組成する事例はまだ少ない状況ですが、2022年10月にベンチャーキャピタルが継続ファンドを設立した事例があります。
継続ファンドを採用する主要なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
① 価値を最大化するための投資期間の延長が可能
プライベート・エクイティファンド等の投資ファンドには、通常、運用や償還の期限があります。何らかの理由で、投資先企業の上場までの期間がファンドの期限を超えそうな場合や、市況が悪化してからではなく、市況が回復してから上場や投資売却を行ったほうがファンドにとって有利である場合に、投資ファンドとしてはファンドの期限を延長したい、という希望を持つことがあります。継続ファンドには実質的にファンド期限を延長する効果があることから、既存ファンドから新規ファンドに投資先企業を移行することで、この希望を叶えることができます。
② 投資先企業の一部の現金化が可能
継続ファンドを使用した場合、投資先企業を新規ファンドに移行する際に、新規で追加の外部出資を受けることがあります。この追加の外部出資は、既存ファンドから見た投資先企業の売却額を填補することになるため、既存ファンドから見ると投資の一部を現金化できることになります。
③ 既存投資家へ投資の柔軟性を与えることが可能
例えば既存投資家であるLPが、今後も投資先企業へ投資したい場合は、投資先企業の移行先の継続ファンドに投資を続けることを選択できます。一方、LPが投資先企業への投資を完了したいと考えた場合、既存ファンドが継続ファンドへ投資先企業を売却する際に、投資の引き上げを選択できます。このように、継続ファンドは既存投資家に対して柔軟な投資の選択肢を提供します。
以下では、日本基準およびIFRSそれぞれについての継続ファンドを使用した投資形態に係る主要な会計論点を解説します。
2 GPの共通支配下の取引に該当した場合の会計処理
継続ファンドを使用した投資形態は、同一のGPの下で行われる取引であるため、「共通支配下の取引」に該当する可能性があります。「共通支配下の取引」か否かにより、既存ファンドおよび新規ファンド傘下の新買収SPC(特別目的会社)での投資先企業の会計処理が変わります。
なお、継続ファンドを使用した投資形態では、現金を対価としないと継続ファンドを採用する目的が達成できないことが多いため、以下では「現金」を対価とした場合の、既存ファンドおよび新買収SPCでの会計処理に限定して解説します。
I. 共通支配下の取引か否かの判定(図表2、2-Ⅰ)
日本基準において、共通支配下の取引とは、「結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合」(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」16項)とされています。
なお、支配の主体である「同一の株主」は企業に限定されず、個人も含まれます(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第201項)。
継続ファンドの場合、基本的にはGPが、自身が受け取る配当や投資売却時点でのキャピタルゲインの最大化のために投資の意思決定を行い、投資先企業の売買を行います。そのため、GPの傘下の事業体である既存ファンドと新規ファンドを支配していると会計上判定されることが多く、継続ファンドを使用した投資形態で行われる旧買収SPCと投資先企業の売買取引は共通支配下の取引として判定されることが多いと考えられます。
一方、IFRSにおける共通支配下の定義は、基本的には日本基準と変わらないものの、IFRSにおいては「事業」の定義や「支配」の判定について詳細な規定があるため、必ずしも日本基準での共通支配下の取引とIFRSでの共通支配下の取引が同一になるとは限らない点に留意が必要です。
図表2:GPの共通支配下の取引の場合の各論点へのマッピング

II. 既存ファンドの会計処理(図表2、2-Ⅱ)
継続ファンドを使用した投資形態では、既存ファンドが、保有している旧買収SPC株式を新規ファンド傘下の新買収SPCに現金を対価として売却するのが一般的なスキームであるため、既存ファンドは旧買収SPCを通した投資先企業への投資を事実上清算することになります。そのため、日本基準における既存ファンドの単体会計処理上は、基本的には単体で計上している旧買収SPC株式の簿価と対価である現金との差額を売却損益として計上します。
また、日本基準における既存ファンドの連結上の会計処理は、既存ファンドが、投資先企業の資産負債を含めた旧買収SPCの資産負債全てを新規ファンド傘下の新買収SPCに現金を対価として売却することになります。新買収SPCへの資産負債の売却は、現金を対価とする場合、既存ファンドにとっては投資先企業への投資の清算と扱われ、連結上も単体と同様、連結簿価と対価である現金との差額を売却損益として計上することになると考えられます。
なお、IFRSにおいては、投資先企業に対する支配の喪失の会計処理を行うことになりますが、現金を対価として投資先企業への投資を全て売却する場合においては、結果として、日本基準の連結会計処理と同様の会計処理になると考えられます。
III. 新規ファンド傘下の新買収SPCの会計処理(図表2、2-Ⅲ)
継続ファンドを使用した投資形態は、新規ファンドの傘下に新買収SPCを設立し、この新買収SPCが既存ファンドから投資先企業を保有する旧買収SPCの株式を取得するのが一般的なスキームです。新買収SPCが新規ファンドおよび新規投資会社から出資を受け、金融機関から借入を実行し、対価である現金を支払うことにより買収を行うため、以下では新買収SPCの会計処理に焦点を当てて解説します。
日本基準における新買収SPCの単体会計処理について、新買収SPCが、既存ファンドが保有している旧買収SPC株式を、現金を対価に購入することになるため、旧買収SPC株式を子会社株式として計上します。
一方、日本基準における新買収SPCの連結上の処理について、継続ファンドを使用した投資形態では、新買収SPCが、投資先企業の資産負債を含めた旧買収SPCの資産負債全てを、現金を対価に買収することになります。本買収取引がGPの共通支配下の取引に該当したという前提で現金を対価として買収が行われた場合は、受け入れた資産負債の簿価と現金との差額をのれんとして計上することになります。なお、共通支配下の取引に該当した場合、新買収SPCが受け入れる資産負債の簿価は、既存ファンドの連結財務諸表上で計上されていた簿価を引き継ぐことになると考えられます。
IFRSでは日本基準と違い、共通支配下の取引がIFRS第3号「企業結合」の適用範囲から除かれているため、共通支配下の企業または事業間の結合に係るガイダンスはありません。そのため、実務上は、各企業で選択して定めた会計方針に従って会計処理することが多いと考えられます。一般的に共通支配下の取引に該当する取引は、売却元で計上していた資産負債の簿価を引き継ぎ、買収先が支払った対価との差額を資本として計上する「簿価引継法」、または売却元で計上していた資産負債を公正価値で測定し、買収先が支払った対価との差額をのれんとして計上する「取得法」の2つの方法が存在します。各企業はこのどちらかの方法を、毎期継続し、首尾一貫して適用することを前提に会計方針として選択します。
一方、継続ファンドを使用した投資形態の場合、新買収SPCは投資先企業への投資を行うのみで、IFRS第3号「企業結合」において定義されている「事業」を行っていない事業体であると考えられます。このため、継続ファンドを使用した投資形態による買収取引は「企業結合」に該当せず、「資本の再編成」に該当すると考えられます。ここで、「資本の再編成」とは、「企業集団の経済的実質は変わっていないが、企業集団の構造が変わること」をいいます。この「資本の再編成」に該当する場合、新買収SPCは、旧ファンドから受け入れる資産負債を旧ファンド側で計上していた簿価で受け入れることになり、対価との差額はのれんではなく資本のマイナスとして扱うことになると考えられます。
Ⅳ. 新規ファンドによる投資売却時の論点(図表2、2-Ⅳ)
継続ファンドを使用した投資形態に限らず、新規ファンドが投資先企業を売却する際には、新買収SPCと旧買収SPCおよび投資先企業を合併し、この合併存続会社を上場申請企業とした新規株式公開、または投資売却というスキームを採用することが多く見られます。
この合併処理が論点になるのは単体の会計処理のみになるため、以下では、日本基準における単体の会計処理のみ解説します。なお、以下の解説は親会社と子会社(孫会社含む)の3つの事業体が合併する順合併を前提としています。
共通支配下において、新買収SPC(親会社)と旧買収SPCおよび投資先企業(子会社および孫会社)の3つの事業体全てが順合併する場合、新買収SPCにおいて子会社および孫会社から承継する資産負債を連結簿価で計上し、新買収SPC(親会社)が保有する抱合せ株式(子会社株式である新買収SPC株式全額)との差額を「抱合せ株式消滅差損益」として処理します。
継続ファンドを使用した投資形態を前提とした場合、具体的に新買収SPC(親会社)が承継する資産負債の連結簿価は、一般的には以下の内容で構成されると考えられます。
- 既存ファンドが買収した時点で識別可能資産として認識した各償却資産の測定額から、償却資産の償却後の残高
- 既存ファンドが買収した時点で識別可能負債として認識した引当金から、合併時点までに引当金の取り崩しがあればその取り崩し額を控除した後の残高
- 既存ファンドが買収した時点で計上したのれん額から、投資売却までの期間に渡って償却した額を控除したのれん残高
3 新規投資会社が投資先企業を支配している場合の会計処理
継続ファンドを使用した投資形態には、既存ファンドが投資先企業の買収後から継続ファンドへの移行までの期間に、投資先企業のEBITDAを改善し、投資先企業の企業価値を向上させているという前提があります。この場合、継続ファンドを使用して新規ファンドが投資先企業を買収する際には、既存ファンドが当初投資した額よりも多額の投資額が必要になります。取引の実行にあたっては、新規ファンドと共同で出資に同意する新規投資会社からの出資も受けた上で、新買収SPCでも新規の借入を実行し、投資先企業へ再投資をすることも考えられます。
このとき、新規投資会社が支配持分を保有する場合は、既存ファンドによる投資先企業の新規ファンドへの売却取引は、GPの共通支配下の取引ではなくなる可能性があります。
I. 新規投資会社が支配を有するか否かの判定(図表3、3-Ⅰ)
一般に、日本基準においてもIFRSにおいても、新規投資会社が、新買収SPCが発行する議決権付株式の過半数を保有している場合は、会計上は新規投資会社が新買収SPCを通して投資先企業を支配していると判定されることが多いと考えられます。他方で、例えば、GPに投資先企業の意思決定機関の役員の過半数を指名できる権利を付与するなどの状況があると、議決権比率に限らず、新規ファンド側を通してGPの支配があるとみなされる可能性があります。そのため、GPの共通支配下か否かの判定同様、新規投資会社の支配の有無の検討には、新規ファンドと新規投資会社における契約内容や各諸条件を考慮した慎重な検討が必要になります。
以下Ⅱ、Ⅲでは、新規投資会社が新買収SPCを通して、投資先企業を支配していると会計上判定された場合の会計処理を解説します。
なお、契約内容や各諸条件次第では、新規ファンドと新規投資会社が新買収SPCを通して投資先企業を共同支配する、という可能性もあります。
新規ファンドと新規投資会社が共同支配していると会計上判定された場合においても、各事業体においては、以下で述べる会計処理と同様になると考えられます。
図表3:新規投資会社が支配を有する場合の各論点へのマッピング

II. 既存ファンドの会計処理(図表3、3-Ⅱ)
既存ファンドは現金を対価に保有している旧買収SPC株式を新規ファンド傘下の新買収SPCに売却するのが一般的なスキームであることから、2と同様に、既存ファンドは旧買収SPCを通した投資先企業への投資を事実上清算することになります。このため、日本基準における既存ファンドの単体会計処理上は、基本的には単体で計上している旧買収SPC株式の簿価と対価である現金との差額を売却損益として計上します。
日本基準における既存ファンドの連結会計上の処理については、2と同様に、既存ファンドが、投資先企業の資産負債を含めた旧買収SPCの資産負債全てを新規ファンド傘下の新買収SPCに、現金を対価として売却することになります。新規投資会社による投資先企業への支配が認められる場合、新買収SPCへ投資先企業を売却することによって投資先企業への投資を清算することになります。そのため、既存ファンドの連結会計上も、連結簿価と対価である現金との差額は売却損益として計上します。
IFRSにおいても、日本基準の連結上の会計処理と同様の会計処理になると考えられます。
III. 新規ファンド傘下の新買収SPCの会計処理(図表3、3-Ⅲ)
日本基準における単体会計処理は、2と同様に、新買収SPCが、既存ファンドが保有している旧買収SPC株式を、現金を対価として購入することになるため、旧買収SPC株式を子会社株式として計上します。
一方、日本基準における新買収SPCの連結会計処理は、新買収SPCが、投資先企業の資産負債を含めた旧買収SPCの資産負債全てを、現金を対価として買収することになります。新規投資会社が投資先企業を支配している場合は、この取引は新買収SPCによる「取得」取引に該当します。そのため、識別可能資産負債は時価で測定し、識別可能資産負債の測定額と対価である現金との差額はのれんとして計上することになります。
IFRSにおいても日本基準の連結会計処理と同様、新規投資会社が投資先企業を支配している場合、新買収SPCによる投資先企業を含む旧買収SPCの買収は、IFRSにおいて「企業結合」に該当すると考えられます。
そのため、現金を対価とした場合、識別可能資産負債は公正価値で測定し、識別可能資産負債の測定額と対価である現金との差額はのれんとして計上することになります。
IV. 新規ファンドにおける投資売却時の論点(図表3、3-Ⅳ)
2で述べた内容と同様という前提で、新規ファンドが投資を売却する場合に採用する合併スキームについて、日本基準上の新規ファンドの単体の会計処理を解説します。
新規投資会社が支配を有する場合で、新買収SPC(親会社)と旧買収SPCおよび投資先企業(子会社および孫会社)の3つの事業体全てが順合併する場合、新買収SPCにおいて、子会社および孫会社から承継する資産負債を連結簿価で計上し、新買収SPC(親会社)が保有する抱合せ株式(子会社株式である新買収SPC株式全額)との差額を「抱合せ株式消滅差損益」として処理します。
このとき採用される連結簿価は、共通支配下で行われた合併の場合と測定額が変わってくるため、注意が必要です。
継続ファンドを使用した投資形態を前提とした場合、具体的に新買収SPC(親会社)が承継する資産負債の連結簿価とは、一般的には以下の内容で構成されると考えられます。
- 新規ファンドの傘下の新買収SPCが、旧買収SPCおよび投資先企業を買収した時点で識別可能資産として認識した各償却資産の測定額から、償却資産の償却後の残高
- 新規ファンドの傘下の新買収SPCが、旧買収SPCおよび投資先企業を買収した時点で識別可能負債として認識した引当金から、合併までに引当金の取り崩しがあればその取り崩し額を控除した後の残高
- 新規ファンドの傘下の新買収SPCが、旧買収SPCおよび投資先企業を買収した時点で新たに計上したのれん額から、投資売却までの期間に渡って償却した額を控除したのれん残高
4 おわりに
2および3で解説したように、継続ファンドを使用した投資形態は、それぞれのケースで会計処理や測定額が変わる可能性があります。
図表4で、それぞれのケースごとの会計処理と測定額をまとめています。
図表4:継続ファンドにおける各エンティティの主要会計論点まとめ

継続ファンドを使用した形態はプライベート・エクイティファンドのような投資を行う企業にとってメリットが多いものの、実際に継続ファンドを使用した場合は、そのスキームの条件等により検討事項および内容が複雑になります。また、図表4からもわかるように、採用する会計基準によっても会計処理が変わる可能性が高くなります。そのため、専門家を交えて慎重に検討することが望まれます。
執筆者
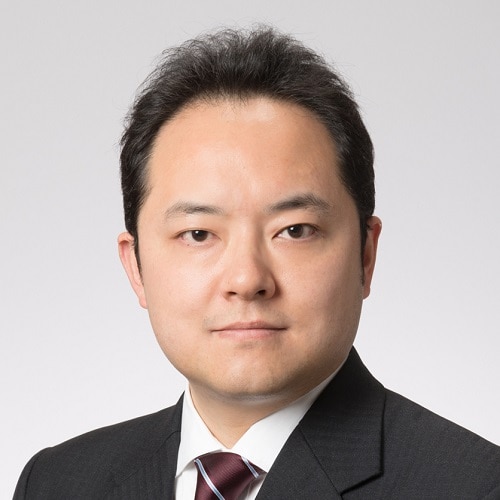
PwC Japan有限責任監査法人
パートナー 嶋方 亮

PwC Japan有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
マネージャー 髙田 栄理


