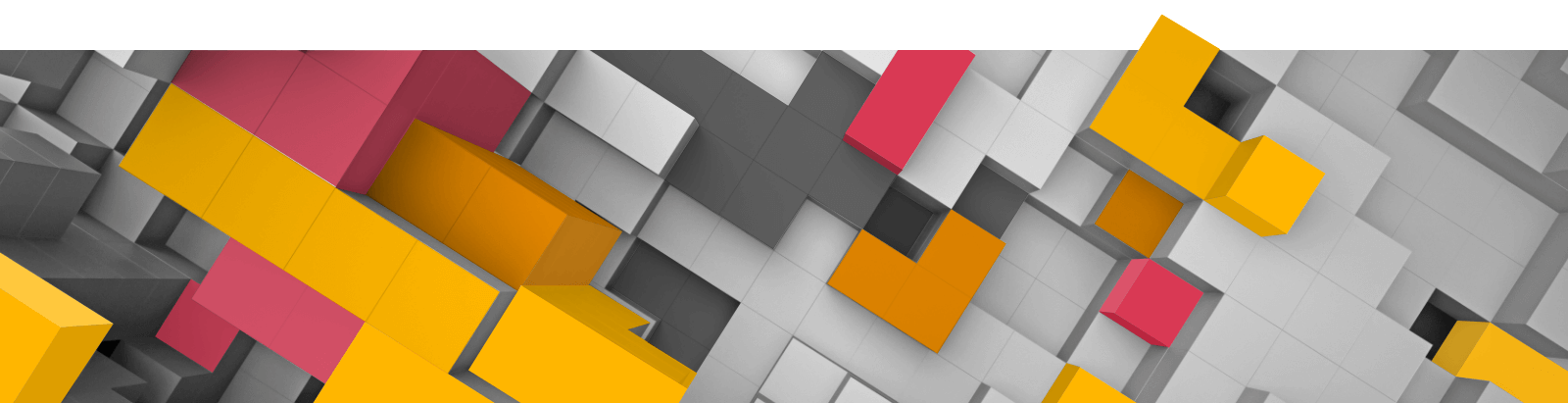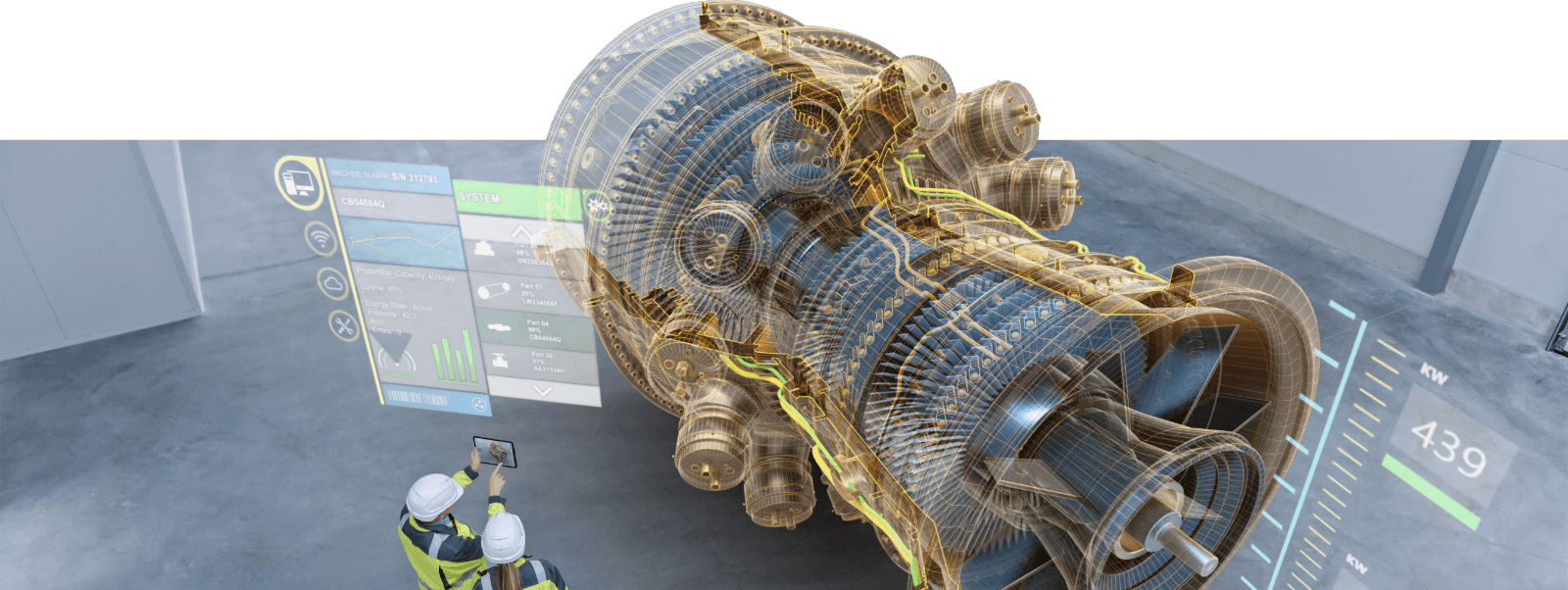{{item.title}}
{{item.text}}

Download PDF - {{item.damSize}}
{{item.text}}
メタバースは今後、どのような展開を見せるでしょうか。そして、企業にどのような影響を与えるでしょうか。PwCはメタバースをグループ内で活用し、またクライアントへの導入を支援した経験をもとに、メタバースの今後に関する6つの予測を立てました。ここには、「次に活用が進む領域はどこか」「活用されない領域はどこか」「最も早く進歩する可能性が高いのはどのテクノロジーか」「企業がリスクを避けつつメタバースを活用するにはどうすればよいか」などが示されています。ここに記す示唆が、企業の変革に向けた準備の一助になれば幸いです。
2022年のメタバースに関する話題は、消費者、特に若年消費者についての内容が多くを占めていました。例えば、ゲームやアバターによるコミュニティ形成、あるいは暗号通貨を使ったショッピングなどについてです。これらのアクティビティは今後も活況を呈することが予想されます。しかし、2023年はBtoB領域やBtoBtoC領域での活用が広がりつつあることにも注目すべきでしょう。
1つの兆しを例に挙げてみましょう。PwCが行った「米国企業・消費者メタバース調査2022」によると、ビジネスリーダーが「検討する可能性が最も高い」と答えたメタバースの利用事例は「新人研修、その他の研修の提供」でした(42%)。同率2位で「職場の同僚との交流」と「顧客が利用できるバーチャルコンテンツの作成」が挙げられています(いずれも36%)。
ますます多くの企業が、メタバース上で現実の業務活動をシミュレートするようになっています。例えば小売・流通事業者は、実店舗をバーチャルで再現して顧客や従業員にさまざまな体験を試してもらい、満足度の向上や実店舗での売上増を志向しています。また、オフィス設計や客席配置のシミュレーション、製造ラインの効率向上を目的とするデジタルツインなど、さまざまな業種での活用が広がっています。
消費者向けメタバースと企業向けメタバースそれぞれが今後数年以内にさらなる広がりを見せ、それと同時にアバターによるユーザーサポートやシームレスな決済など、技術面での進化も加速していくと予想されます。
スタートとして有効なのは、メタバースによる事業成果を測定できるようにすることです。現在、メタバースが企業にもたらす一般的な成果としては、ブランド力や顧客エンゲージメントの向上、販売チャネルの拡大、労働力の最適化などが挙げられます。まずは明確な目標を設定した上で、メタバースに特化した価格戦略やパートナーシップ戦略、あるいは新しいオペレーティングモデルとガバナンス体制など、必要な検討事項をリストアップすることが、メタバースのビジネス活用の青写真をより鮮明にすることでしょう。

メタバースのビジネス活用の成否を大きく左右するのは、自社の信頼性にあると私たちは考えます。目を見張るような体験ができる一方で、セキュリティの甘いメタバース空間があったとしても、ユーザーはそのような空間を日常的に使用することはないでしょう。メタバース空間で詐欺や脆弱なセキュリティ問題・プライバシー侵害が一度でも起きれば、制裁や追徴金などの対象者として自社がメディアを賑わせることになりかねません。残念ながら、没入型の3次元デジタル世界ではインターネットと同様に、ユーザーをターゲットとする悪質な行為が発生する可能性は大いにあります。企業は自社サービスにおいてそのような行為を発生させないよう、細心の注意を払わなければなりません。新たなリスクに対応し、むしろ自社の信頼を高められる機会とするべく、既存のセキュリティ要件を見直し、ガバナンス体制を構築することでユーザーエクスペリエンスがどのように変化するのかシミュレーションを行うなど、着手できるところから確実に実行に移すことが必要です。
メタバース上のリスクを管理する際の指針は、前もって、かつ徹底的に設計しておく必要があります。メタバースのビジネス活用がまだ計画段階にあるうちからリスクと管理方法を検討し、計画に組み込んでおけば、後で多額のコストがかかるような事態は起きにくくなります。重要なアクションは以下のとおりです。
企業によるメタバースの活用が進むのは、仮想現実(VR)をはじめとするエクステンデッドリアリティ(XR)の技術が進歩し、利便性が高まることによるところが大きいでしょう。PwCも、従業員研修や社内イベント、チーム間のコラボレーションなどにVRを活用しています。VRでの研修は研修速度や集中度を向上させるという結果も出ており、今後もニーズは拡大すると考えられます。
メタバースがさらに発展・普及する上で欠かせないのが、人工知能(AI)でしょう。メタバース空間では、ユーザーが訪問したワールドや購買の履歴など、さまざまなデータが蓄積されます。アバターがどのアイテムを手に取り、購入までに何秒かかったか、どのゲームを何分間プレイしたか、どんなコミュニティで誰と会ったか……。AIが膨大なデータから傾向を読み取り、私たちにインサイトを提供するという未来は、すぐ近くまでやって来ています。
AIは今後、「デジタルヒューマン」(コンピュータが生成する本物のようなアバター)としての機能をますます高めるとも考えられます。AIが従業員向けトレーニングの相手となったり、カウンセラーとなったりと、これまで人間同士で行ってきた交流を代替する日も遠くないかもしれません。
当然のことながら、AIのこうした進歩はディープフェイクをはじめ、悪質な行為を引き起こすというリスクを生むことにもつながります。企業にコンプライアンス上の新たな課題を突き付けるのはほぼ確実と考えられており、メタバースを対象としたAI規制が導入される可能性も頭に入れておいたほうがよいでしょう。

メタバース上でのサービスにAIを組み込む上で望ましいのは、「信頼できるAI」を配備することです。自社が望むことだけを過不足無くAIに行わせるためです。AIは企業に、より広範なデータに基づく戦略策定やガバナンス強化をもたらすと考えられます。AIを活用するメリットを正しく享受するために、要件定義や概念実証(PoC)の準備のステップを丁寧に歩んでいく必要があるでしょう。
PwC米国が5,000人以上の消費者と1,000人以上のビジネスリーダー(企業のエグゼクティブ層)に実施した調査によると、「3年以内にメタバースの利活用計画が事業活動の一部になると予想する」と回答したビジネスリーダーは82%に上りました。メタバースは今後、企業のあらゆる活動領域で使用される可能性があるのです。これは、部門や領域を問わず、全てのビジネスリーダーがメタバースを理解し、適切な対応をできるようにならなければいけないことを意味します。以下に、新たに生じ得る職務の例を記します。
上記のような非技術系のビジネスリーダーであっても、メタバースとは無縁ではいられません。自社のデジタル活用を推進する最高デジタル責任者(CDO)、情報管理やセキュリティを司る最高情報責任者(CIO)、最高情報セキュリティ責任者(CISO)などとも密接に連携し、メタバースのビジネス活用を進めていく必要があるでしょう。
新たなビジネストレンドに対応するため、多くのチームにスキルアップが求められるでしょう。しかし、それだけでは十分ではないと私たちは考えます。多くのシニアリーダーが関わることで軋轢や誤解が生じないよう、メタバースに関連する自社の全ての活動を統括する人材を配置することを検討する必要があります。新たなポジションとして設けても、既存のポジションに役割を追加しても構いません。部署またはチームの間で何らかの問題が生じた場合に、客観的な目線で最良の判断を下せる人材がいることが、企業経営をよりスムーズにしてくれるはずです。いずれにせよ、ビジネスリーダー間のコミュニケーションの強化が、このポジションが行うべき優先事項の1つになるでしょう。
環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する企業の取り組みに、ますます強い関心が持たれるようになっています。そうした時代にあって、メタバースは自社のESG経営の推進を後押しする可能性があります。例えば、対面での会議の代わりにメタバース上で会議を行えば、炭素排出源の大きな要素である出張を減らすことができます。メタバース上に製造ラインのデジタルツインを整備すれば、シミュレーションを通じて生産効率をアップできますし、メタバース上に店舗を再現すれば、消費者によるリアル商品の返品輸送を減らすこともできるでしょう。デジタルトークンを使用すれば、原材料の原産地を追跡し、サプライチェーンにおける環境濫用を減らせるかもしれません。
自社の業務活動をさらにバーチャル化することで(業務活動を地理的な境界や多くの物理的制約から解放することで)、グローバルの連携力は高まり、より多くのサービスや製品が人々の手に届くようになるでしょう。また、メタバース上でのリアルなシミュレーションは、アカウンタビリティと透明性を高める上でも役立つと考えられます。クライアントをはじめとするステークホルダーを自社のメタバース空間に招き、時にモニタリングしてもらい、時に活動に参加してもらうことで、自社の姿をより鮮明に知ってもらうことができるからです。こうしたメタバースの可能性を開花させるために、経営層がビジネス化の決断を迫られる機会が増えてくると私たちは考えています。
自社のメタバース関連活動をビジネスとして成り立たせ、さらにはESG目標達成のツールとしても役立たせるために、企業は活動の優先順位を初めに設計しておく必要があります。ESG目標および関連する統制体系を早い段階からビジネスプランに組み込むことで、投資家や従業員その他のステークホルダーへの説明はよりスムーズになり、メタバース活用への支持も得られやすくなると考えられます。そのためには、メタバースのビジネス計画と主要な関連技術がESGに与える影響を評価することから始める必要があります。
新しいテクノロジーを活用するには新しいスキルが必要です。メタバースも同様で、テクノロジーの理解と習得には専門性の高いスキルを必要とします。web3エコシステムにおけるトランザクションの監視と検証、データの収集と保護など、数年前まではほぼ存在しなかったようなスキルが、メタバースのビジネス活用を本格化する上で必要になります。
外部パートナーの協力を仰ぐといった対応は可能ですので、全てを自社で理解する必要は必ずしもありませんが、対等に議論し、自分事として必要な施策を打ち出していくためには、スキルを習得する、あるいはスキルを持つ人材の採用を急ぐことが賢明でしょう。

メタバースに関する基本的な知識は、自分がメタバース空間に入ってみることで得ることができます。しかし専門性を要するものに関しては、技術者を講師として招いて研修を行ったり、新規採用を行ったり、専門人材を派遣してくれるサードパーティと提携したりすることで、積極的に対処していくことが求められます。失敗を許容したり、研修や採用に重点的に投資したりといった姿勢を社会に訴求することも、優秀な人材を惹きつけるための大切な要素となるでしょう。
私たちがここに記した6つの予測はいずれも可能性に過ぎません。ただ、デジタル世界と現実世界がシームレスに融合した未来がもたらす豊かさを想像すれば、社会がそれを追い求めるのは必然でしょう。そして、メタバースが私たちの生活や価値観を変革する日は遠くないようにも思えます。
物理的な商品やアセットをデジタル化したり、デジタルなアイデンティティを分身として生活したり、デジタル商品を価値として販売・購入したり……。ふと気付けば、私たちは日々の生活でこうした行動を自然に取るようになっています。いずれも、メタバースがもたらした新たな常識と言えるかもしれません。「変革」と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、日々の小さな変化は確実に起こっています。メタバースの動向を読み解くことは難しいですが、いざという時に迅速に対応できるよう、今できることに着実に取り組んでおくべきと言えるでしょう。
※本コンテンツは、Beyond the hype: what businesses can really expect from the metaverse in 2023を翻訳したものです。翻訳には正確を期しておりますが、英語版と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。