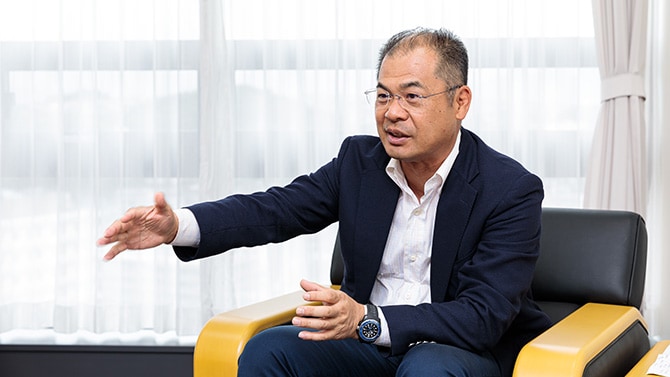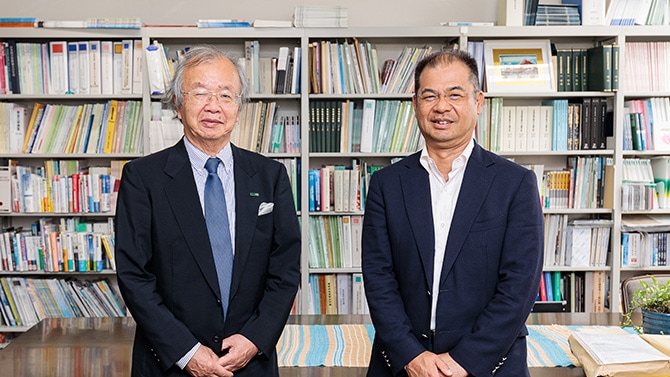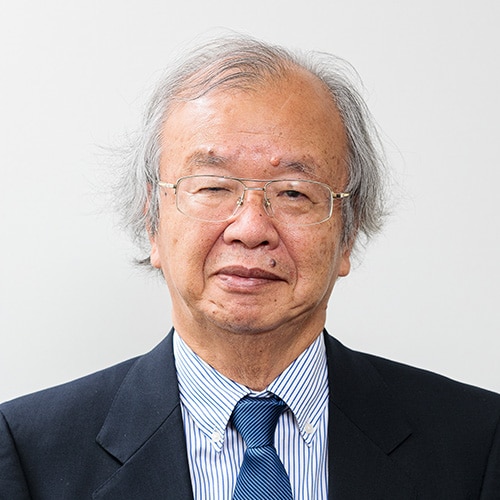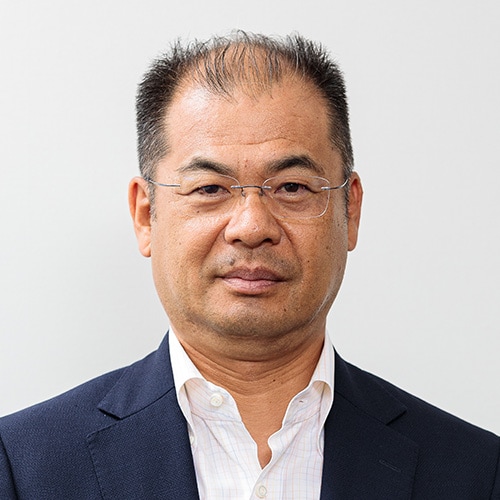{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}


関西大学社会安全学部・社会安全研究センター センター長
河田 惠昭氏
PwC Japanグループ グループマネージングパートナー
鹿島 章

SDGsの道しるべ
パートナーシップで切り拓くサステナブルな未来
予見が難しい地震・噴火などの災害や、激甚化の傾向を強める豪雨・水害、土砂災害など、日本ではさまざまな自然災害が日常のすぐそばに潜んでいます。阪神・淡路大震災、東日本大震災の大きな教訓に学び、自然災害への備えが進められてきました。しかし2022年3月の福島県沖地震後の大規模な停電や需給ひっ迫が起き、危機に対する備えが十分であるのかという課題が改めて浮き彫りになりました。
【あらためて考える真の「防災」】と題したシリーズの第2回では、長年にわたり防災の第一線で国や社会に対して警鐘を鳴らし続けてきた関西大学社会安全研究センター長の河田惠昭・特別任命教授をお招きし、PwC Japanグループの鹿島章とともに、国の防災の取り組みや企業の危機対応の課題について意見を交換しました。
鹿島:
気候変動の影響が大きいと思われる大規模な水害が毎年発生し、また一方では南海トラフ地震や首都直下型地震への警鐘が鳴らされています。来年2023年は関東大震災から100年の節目でもあります。「今そこにある危機」「来るべき国難」に対する国としての防災の取り組みについて、河田さんはどのようにとらえていらっしゃいますか。
河田:
日本は、「過去に起きたこと」を踏まえての対策はきちんとやる国です。例えば、集中豪雨で大きな土砂災害が発生した場所に砂防ダムを整備したり、津波や台風に伴う大波・高潮の被害があった地域に防潮堤を築いたりしてきました。一度起こった災害を繰り返してはならない、という発想です。
一方で私たちの社会は、「これまで起きていないこと」「想定外に生じたこと」への対応が苦手です。その意味で、自然災害を予防する措置が十分に講じられているとはいえません。今のままでは、予防策が何も手当てされていない地域や場所をひとたび自然の猛威が襲うと、被害はたちまち甚大化します。憂うべきことですが、「大惨事はめったに起こらない」という楽観主義に日本人の多くが陥っており、災害に関して日本社会全体に「“起こらないこと”にする症候群」が広がっているようにも思えます。
鹿島:
「“起こらないこと”にする症候群」というご指摘は、深く考えさせられます。
自然災害からはややそれますが、ご指摘は日本企業のリスクマネジメント全般にも通底することのように感じます。
例えば経営上のリスクである企業不祥事への対応では、優良と評価されている企業ほど、「不正は起こらない」あるいは「あってはならない」という考えの下、内部統制を構築するケースが日本ではよく見られます。過去に発生した事案、もしくは発生しそうになったことのある不正に対しては、一定の想定のなかできちんとした対策が用意されている。他方、過去に類例のない想定外の手段を悪用した不正は発見が遅れ、その不正が発覚した場合の対応も後手となりがちです。
また、サイバーセキュリティに関しても事情は似ています。これまで、「セキュリティ上の脅威は外部から来る」「社内のネットワークは安全で問題は発生しない」という考えに基づき、社外と社内を隔てる強固な障壁(ファイヤウォールなど)を設けて外からの攻撃を防ぐ方法が主流でした。しかし近年はクラウドサービスの利用拡大やリモートワークの浸透に伴い、社外ネットワークと社内ネットワークとの境界があいまいになったことで、社内からウイルス感染が広がるケースが増加しています。そこで、社の内外を問わずセキュリティリスクはあると考える「ゼロトラスト」と呼ばれるサイバーセキュリティ態勢の構築が急務となっています。
自然災害でも危機管理でも、先入観を捨てて想定の視野をとらえなおし、「症候群」を脱する努力が、企業にも求められているといえそうですね。
河田:
リスクマネジメントで最も大切なのは、「最悪の事態」は起こり得ると認めることです。もちろん、それを認めたところで損害を完全に防ぐことはできません。しかしたとえ不完全な対策であっても、最善の努力を「最悪」の前提の下で尽くすことに意味があるのです。
「災害対策基本法」には当初「防災=自然災害による被害ゼロを目指す」ことが明記されており、日本の災害対策はこれまで、「被害ゼロの防災」を目標に進められてきました。しかし1995年に発生した阪神・淡路大震災は「被害ゼロの防災」が幻想にすぎなかったことを白日の下にさらしました。私が「被害が生じることを前提にして、その被害をできるだけ小さくする」という「減災」を提唱しているのはこうした考えからです。
2011年の東日本大震災で阪神・淡路大震災を超える戦後最大の被害が生じたことも受け、日本の災害対策は、「被害ゼロの防災」から「減災」へと大きくシフトしました。ただ、今後に想定される南海トラフ地震や首都直下型地震が未曾有の災害になることは確実です。これらに備えるには、「減災」をさらに一歩進めた「縮災」が求められます。「縮災」が目指すのは、「予防力」および「回復力」の向上です。災害を見越し、事前の対策を推し進めて被害の発生を抑えたり小さくしたりする「予防力」。そのうえで、災害が起こった後にいち早い復旧と復興を実現する「回復力」。この2つです。
鹿島:
今ご指摘になった「回復力」という意味で、企業活動においては事業継続計画(BCP)の策定による早期の復旧が重要です。
企業のBCPの策定状況に関する内閣府の調査(2022年3月公表「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」)によると、BCPを策定している国内の大企業は70.8%。前回調査(2019年)より2.4ポイントの微増にとどまり、「2020年度までにはほぼ100%」としていた政府の当初目標は未達成です。また、BCP策定済み企業(中堅企業含む)で「被災時にBCPがとても役に立った」とした回答は20%未満でした。実効性が高いBCPの取り組みは日本企業ではまだ限定的で、自然災害などの危機に対する具体的な想定と備えが十分にできているとはいえない状況です。日本企業のBCPについてはどうご覧になっていますか。
河田:
日本企業のBCPも国の災害対策と同様に、「防災=被害ゼロ」の考え方にとらわれすぎているように感じます。
リスクマネジメントの取り組みで先行する米国企業は、「災害を完全には防ぐことは不可能」=「自社の取り組みは不完全」という前提に立ってBCPを策定し、自社で防げない部分・足りない部分については民間保険を活用しています。特に地球温暖化に伴って、強大なハリケーンが来襲するようになった米国では、高潮によるニューヨーク・ビジネス街の水没や集中豪雨によるヒューストン・ダウンタウンの水没など、新たな被害が生まれています。この損害保険は減災や縮災にも通じる考え方であり、自社で対策を講じ得ないことがあることを認識する姿勢は日本企業にとっても参考になる点があると思います。
鹿島:
日本企業は「攻め」には経営資源を投じますが、「守り」については手薄になりがちです。リスクを見極める体制が社内に十分に整っておらず、未整備だという認識も弱いように思います。したがって、自社が対応できない部分に対して保険もかけないという循環になっているのかもしれません。
東日本大震災では国内のサプライチェーンが寸断され、その反省から、日本企業のBCPの取り組みが進みましたが、こうした「守り」の備えはまだ脆弱です。国内のサプライチェーンだけでなく、海外のサプライヤーも含むより複雑な対応が求められています。直近ではCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響による生産の停滞や世界的な物流網の混乱が続いていることなど、日本企業の事業継続を脅かすような新たな事態が相次いでいます。いずれも、起こってみて初めて事態の重大さを認識したという企業も少なくなかったと思われます。世界情勢であると自然災害であるとを問わず、こうした「未経験の危機」シナリオにあらゆる事態を想定・反映させることは、確かに簡単ではありません。しかし少なくとも、想定シナリオの“幅”をもっと広げる必要はありそうです。
河田:
ご指摘の通り、自然災害に対し、企業単独での備えには限界があります。また、防災について非合理的・非科学的な意思決定が取締役会でなされるケースも少なくありません。そのため大企業といえども防災投資が過剰になったり、逆に防災への備えが極端に不足したりすることもあります。日本企業にはもっと、われわれのような専門家の歴史を生かした科学的知見を生かしていただきたいと感じています。
また、危機対応には一貫性を保つ難しさもあります。行政の場合、知事や市長などのトップが交代してしまうと組織的に積み上げられてきた防災への理解や取り組みが見直されて、その結果新たな取り組みが始まって過去からの努力が途絶えてしまうという話をしばしば耳にします。企業の防災の取り組みにも同様の問題はあると想像しますが、いかがですか。
鹿島:
外部の専門家の知見を生かすべきとのご指摘は、まさにその通りだと思います。企業は経済合理性を睨みながらリスクへの対策を講じます。ただ自然災害については、合理的な“物差し”が不足しているために何をどの程度やればよいか分からず、結果的にやりすぎたり、逆に足りなすぎたりといったことはあろうかと思います。AIなどの分野ではアカデミアとの関係が強くなっていると感じていますが、防災分野においても、アカデミアとの連携を一段と深めるべきですね。
また、リーダーの交代に伴い施策の一貫性が損なわれる問題は企業にも当てはまることだと思います。防災関連施策の有効性・継続性を担保するには、精緻な言語化や仕組み化などの工夫がもっと必要かもしれません。
鹿島:
防災に限ったことではありませんが、リスクマネジメント全般に関する日本企業の大きな課題として「Lessons Learned(過去の教訓に学ぶ)が苦手」という特徴が挙げられると思います。危機対応に失敗した場合に、職を辞すことで責任を取ることがありますが、その結果として組織のリスク管理能力を十分に高めることができなくなるおそれもあります。
企業不祥事や危機対応での失敗を完全にゼロにすることは困難です。企業のリスクマネジメントにおいても、組織として失敗から真摯に学び、次につなげることが重要でしょう。
河田:
経験を「組織知」として残すためのマネジメント手法の1つに「AAR」(After Action Review)が知られています。災害対応においても、失敗の責任を個人に帰するのではなく、失敗例やそこから得た教訓を徹底的に分析し、次の災害に備える知識としてプログラムに組み込む検証体制が必要です。AARは失敗の事例だけでなく、うまくいったケースにも有効です。成功体験を「運がよかった」で終わらせず、知識として蓄積し、組織で共有するのです。これらの作業は社内の常設のプロジェクトチームが継続しなければなりません。
鹿島:
河田さんが所属されている関西大学の社会安全学部は、学際的な学びを通して問題を解決する能力を養っていると伺っています。そうした能力は、Lessons LearnedやAARに通じたリスクマネジメントとの共通要素も多い。リスクマネジメント人材は日本社会全体で不足していますから、学生の皆さんに対する企業からの引き合いも多いのではないですか。
河田:
ご指摘の通り、災害のマネジメントは実は応用範囲が広く、企業からも評価いただいています。
鹿島:
防災を論じるさまざまな場面で「レジリエンス」という言葉を目にする機会が増えました。最後に、防災におけるレジリエンスについて教えていただけますか。
河田:
先ほどお話しした「予防力+回復力=縮災」が英語でいうところのレジリエンス(Resilience)です。一般的に「打たれ強い」「素早くリカバリーする」といった意味で理解している人が多いのですが、本来は「予防力」の意も含むべき言葉です。
国はこのレジリエンスの考え方に基づき、防災施策強化の方向性として「国土強靱化」(National Resilience)を打ち出しました。ただ、日本政府がNationalを「国土」と訳したため、「インフラの強化=国土交通省のマター」との誤解も生じています。本来レジリエンスは、小は家庭から大は国家までの「人々の組織のレジリエンス」であり、政府としては厚労省・総務省・経産省・環境省など、さまざまな省庁が協力して取り組むべきものです。
かつて「被害ゼロの防災」を目指していた「災害対策基本法」は、東日本大震災の甚大な被害を受けて改正され、考え方を「減災」に改めました。しかし、南海トラフ地震や首都直下型地震などの大規模災害は既存の法律の想定を大きく超えており、このまま放置すると、不作為が理由で政府は裁判で負けてしまうでしょう。個人的には法律の上位の憲法でカバーすべき事態も想定されると考えています。国民的議論をもっと深めていく必要があるはずです。
鹿島:
最悪の事態が起き得ることを認め、それに対して最善を尽くすためには、多様な専門家が同じ目標に向かって協力していくことが必要であり、そのためには国民の理解を深めていくことが大切ですね。
企業においても、国の対策を把握し、自社で備えること、備えられないことを科学的に把握し、これまで以上に実践的な対策を講じていくことの重要性を再認識しました。
河田先生との対談は、防災と危機管理についての示唆にあふれる貴重なものでした。最悪の事態が起き得ることを想定することが、危機管理の第一歩であることを強く認識した対談でした。激甚化する自然災害に加え、いつ起きてもおかしくない大規模な地震。全ての被害を防げないなかで、どのような対応を実施していくのか。自然災害だけでなく、サイバーリスクなど企業経営におけるリスクマネジメント全般に共通する経営者にとって非常に難しい課題ですが、アカデミアをはじめ、社内外のさまざまな専門家と協力することで、現実的で効果の高い備えを整えることができると思えました。
1974年京都大学大学院工学研究科土木工学専攻博士課程修了。工学博士。1986年に国連に創設されたSASAKAWA防災賞を2008年に受賞。1995年阪神・淡路大震災をきっかけとして設立された「人と防災未来センター」センター長兼務。
1985年、大手監査法人に入所。監査業務を経験した後、1995年にアーサーアンダーセンビジネスコンサルティング部門に転籍し、2001年にパートナー就任。ベリングポイント株式会社マネージングディレクターなどを経て、2012年にプライスウォーターハウスクーパース株式会社のコンサルティング部門代表、2015年に同社代表取締役に就任。2016年より現職。
※ 法人名、役職、本文の内容などは掲載当時のものです。