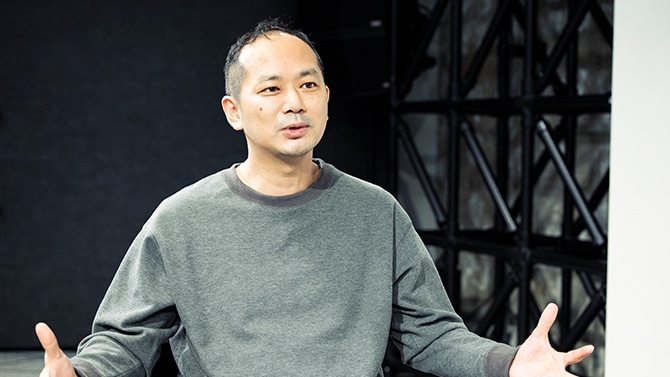{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}


医師/神経科学者
紺野 大地 氏
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
三治 信一朗
未来を創るDX
~デジタルが加速させる社会のトランスフォーメーション
人間の身体・精神に備わるさまざまな機能や能力を人工的に強化・向上させる技術「人間拡張」(Human Augmentation)が注目されています。生活の質の改善、社会コストの低減、産業創出など、多方面での効果や成果が期待される一方、人体そのものに関わる技術だけに、漠然とした恐れや不安、倫理上の問題など、解決すべき難題も少なくありません。では、その有益性を広く社会に還元し、ディストピアへの転落を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。
「ERATO 池谷脳AI融合プロジェクト」※のメンバーで、現役の医師であるとともに脳・AI分野における気鋭の若手研究者として注目を集める紺野大地氏と、テクノロジーを活用した社会課題解決に向け産官学の連携を支援するPwCコンサルティング合同会社「Technology Laboratory」(テクノロジーラボラトリー)の所長を務める三治信一朗の対談から浮かび上がってきたカギは「ストーリーテリングの重要性」でした。
ERATO…ERATO(Exploratory Research for Advanced Technology)は、科学技術振興機構が実施している研究開発プロジェクト。今後の科学技術のイノベーションの創出を先導するもので、予算規模が大きいのが特徴。
三治:
人間拡張について一般的によく知られているのは、義手や義足などで身体機能を補ったり、視覚・聴覚などの感覚機能を回復・強化したりするフィジカルな技術領域です。しかしもう1つ、重要な研究分野が、脳の認知機能です。
脳研究は「生命科学の最後のフロンティア」とも言われ、ビジネス界からも今熱い視線が注がれています。医師でもある紺野先生は、人間拡張と脳機能のどのような点に注目なさっていますか。
紺野:
脳のポテンシャルに特に関心があります。誤解を恐れずに言えば、疾患や負傷により「マイナス」の状態となった人間の機能を「ゼロ」に戻そうとするのが医療ですが、人間拡張はゼロ地点を超えて「プラス」にエンハンス(強化・高度化・増幅・向上など)するものです。
脳の機能は汎用性が極めて高く、視覚をつかさどる領域を聴覚の領域に変えることができたという研究さえ報告されています。そんな脳の潜在力を、人間はまだ十分に使い切れていないのです。
三治:
すると、極端に言えば「目で聞き、耳で見る」こともあながち不可能ではないのですね。考えてみれば、視・聴・嗅・味・触という5つの感覚機能は、あくまで人間がそう定義づけているにすぎないのかもしれません。そこを改めてとらえ直せば、人間が五感以外の別の感覚を獲得できる可能性も大いにあり得そうですね。
紺野:
その通りです。例えば東京大学の池谷裕二教授の「ERATO 池谷脳AI融合プロジェクト」では、AIを活用して脳の潜在能力を見極め、機能を拡張する研究に取り組んでいます。
その試みの1つに「地磁気を感じるネズミ」の実験がありました。視力を失わせたネズミの脳に地磁気センサーを備えたコンピュータチップを埋め込む。そのネズミを、ゴールに餌を置いた迷路に入れる。そしてネズミが向いた方角に応じて、脳に電気刺激を与える実験です。
実験開始から数日後、ネズミは地磁気を「感じて」餌のある方向を認識し、正しい経路をたどるようになりました。この結果から分かったことは、「先天的には感じない刺激であっても、コンピュータやAIの力を借りれば利用できるようになる」ということです。
視覚の場合、外部からの刺激である「光」を感覚器官としての「目」が受け止め、神経を通じて脳に伝えます。つまり、脳に入った刺激はニューロン同士の電気的な反応に置換されるわけです。他の感覚も同様です。
ならばネズミの実験が示唆するように、人類が脳機能を拡張して、五感を超える“第六感”のような新たな感覚を獲得することは不可能ではないと考えられます。
三治:
脳の機能拡張には大きな可能性がありそうですね。もっとも、脳情報の測定技術自体は以前からありました。MRI(核磁気共鳴画像診断)しかり、CT(コンピュータ断層撮影)しかりです。現在、人間拡張の技術領域で産業への応用を展望すると、アカデミアではどのような分野が注目されているのでしょうか。
紺野:
脳の機能を拡張するには、2つの方向からのアプローチがあります。1つは「脳情報の読み取り」です。これは「脳活動の記録から、その人の考えていることや気分を読み取る」ことで、例えば「頭に思い浮かべたことをAIが文章化する」ことなどが挙げられます。
もう1つは「脳への情報の書き込み」です。これは「脳を刺激することで、狙い通りの運動や感覚を生じさせる」もので、先ほどの地磁気を感じるようになったネズミの例はこれに当たります。
さらに、情報の読み取り・書き込みの方法として、頭蓋骨に小さな穴を開けて脳に電極を直接挿すなど、身体を物理的に傷つける「侵襲的手法」と、損傷を避けて頭皮の上から行う「非侵襲的手法」があります。
侵襲的手法のほうが記録する脳波の質は高いのですが、身体を傷つけるのは重大なデメリットです。一方、非侵襲的手法は身体を傷つけずに済むものの、記録できる脳波の質は低く、その点が弱点です。
これらのうち、ビジネスや産業への応用でまず広がっていく可能性が高いのは、非侵襲的手法による脳情報の読み取りでしょう。米国のスタートアップがヘルメット型のBMI(ブレイン・マシン・インタフェース)端末を開発するなど、急速な進歩が見られます。
ただし一般向けに広く普及するには、主に記録精度の点でさらなるイノベーションが求められます。
脳の機能は汎用性が極めて高く、視覚をつかさどる領域を聴覚の領域に変えることができたという研究さえ報告されています。そんな脳の潜在力を、人間はまだ十分に使い切れていないのです。
三治:
脳情報の読み取りや書き込みは、具体的にどのような成果を想定して研究されているのですか。
紺野:
現状では精神疾患の治療が主です。例えばうつ病では、脳の特定部分を磁気で刺激する治療方法が実用化されています。これは非侵襲的手法による脳情報の書き込みです。こうした治療の延長線上には、普段健康な人が「今日はちょっと調子が悪いな」と感じるくらいの気分を改善することも考えられるでしょう。
三治:
脳情報の書き込みによって、例えば「精神を高揚させる」「仕事に没頭できる状態を継続させる」など、パフォーマンスの向上も期待できるのでしょうか。
紺野:
そうした試みは始まっています。東京大学では頭皮上から脳に電気刺激を与えて記憶力をアップさせる実験を行っており、私も被験者になったことがあります。論文としてはまだ発表されていないのですが、どのような結果が出るのか楽しみです。
また、スポーツの世界ではニューロフィードバックと呼ばれる手法が実用化されています。自分の脳の活動を視覚や聴覚への刺激としてフィードバックすることで、脳活動を望ましい方向へと変化させて脳の機能を強化し、運動パフォーマンスを向上させるというものです。こうした方向への応用は広がる可能性があると思います。
三治:
頭皮上への刺激だけで記憶力が高まるのはいいですね。でも、それは脳に継続的な刺激を与えるような方法なのでしょうか。それとも、いったん刺激を与えれば、それが影響を及ぼし続けて良好なサイクルが回り始めるものなのでしょうか。
紺野:
先ほどの研究では、何かを記憶するタスクを実行するときに脳を刺激することで、「そのときの記憶=シナプスの結びつき」を強めると考えられています。シナプスの結びつきはその後も残るので、結果的に記憶力の向上につながります。
三治:
ではその効果を定常的に計測し、結果に応じてさらに刺激を与え、パフォーマンスをまた高める──そんな累進的な進化を実現する人間拡張もあり得るということですか。
紺野:
脳への刺激によるパフォーマンス向上のメカニズムは、ドーパミンやセロトニン、アセチルコリンといった神経調節物質の量が一過的に増えることと関連があると考えられています。脳を刺激し続けるとこれらの物質は枯渇してしまいますから、ずっとパフォーマンスが高まった状態にあることは現実的には難しいかもしれません。
三治:
瞬発的にパフォーマンスを発揮したいスポーツ選手には有効かもしれませんが、少年マンガで描かれるような「機能が拡張された超人」であり続けるのは難しいわけですね。
そんな超人は別としても、一般論として、人間が一定のパフォーマンスを発揮し続けることは難しいですよね。いわゆる「人間国宝」(重要無形文化財保持者)は、演劇や音楽、工芸といった“わざ”を安定して高度に体現できる希有な存在だからこそ、「国の宝」であるわけです。
では、人間が安定して高いパフォーマンスを維持したい場合には、脳をどのように使えばよいのでしょうか。
紺野:
サッカーのプロ選手とアマチュア選手それぞれの脳活動を比較すると、プレー中、プロの選手の脳のほうが活性化“していない”という研究があります。一般的なイメージとは逆ですよね。
具体的には、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)で脳の活動を記録すると、活性化している領域はプロの選手のほうが限定されているのだそうです。人間が安定して高次のパフォーマンスを示し続けるには、「脳を使いすぎない」「脳を酷使するまでもなく発揮できる力のレベルを高める」といった鍛錬が大切なのでしょう。
三治:
効率的な脳の使い方が身に付いていること。そしてパフォーマンスを発揮し続けるための効率的な脳。脳自体を高効率の状態にすることで最高のパフォーマンスを導き出すという考え方は、人間機能を拡張する上での重要なヒントになりそうです。
脳を効率的に使えるようになるということは、人間の感覚そのものを自在に使いこなせるようになることにもつながります。とても面白いですね。
紺野:
はい。ですから、ドーパミンが枯渇しない“超人”を生み出すことは困難だとしても、少ないドーパミンでとてつもないパフォーマンスを発揮する人間なら、実現の可能性があるかもしれません。
(※中編に続く)
1991年生まれ。東京大学医学部卒。医師、神経科学者。脳や人工知能(AI)の研究を通じ、「脳の限界はどこにあり、テクノロジーによりその限界をどこまで拡張できるのか」を探究。書籍やSNSを通じ、積極的な情報発信にも努めている。
日系シンクタンク、コンサルティングファームを経て現職。産官学それぞれの特長を生かしたコンサルティングに強みを持つ。社会実装に向けた構想策定、コンソーシアム立ち上げ支援、技術戦略策定、技術ロードマップ策定支援コンサルティングに従事。
政策立案支援から、研究機関の技術力評価、企業の新規事業の実行支援などまで、幅広く視座の高いコンサルティングを提供する。
※ 法人名、役職、本文の内容などは掲載当時のものです。