{{item.title}}
{{item.text}}

{{item.text}}
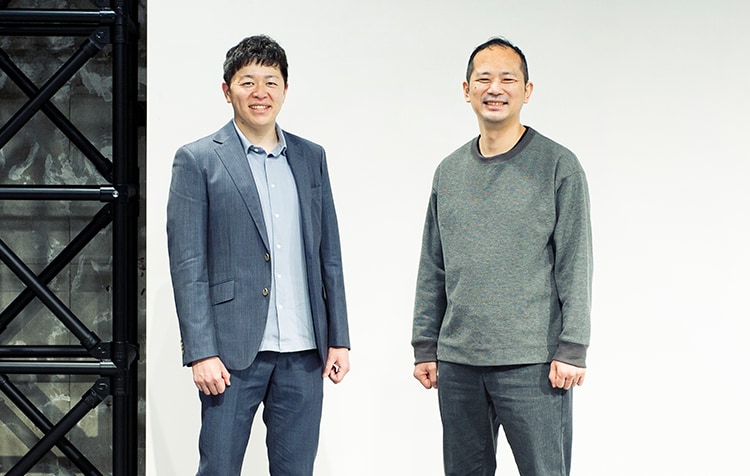
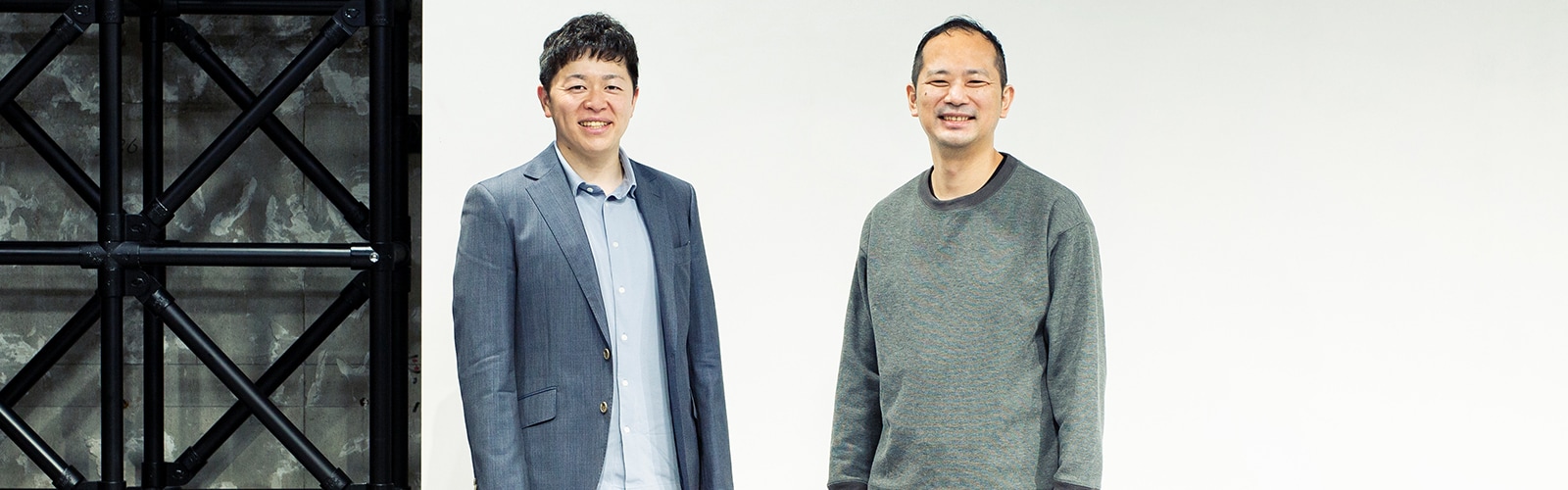
医師/神経科学者
紺野 大地 氏
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
三治 信一朗
未来を創るDX
~デジタルが加速させる社会のトランスフォーメーション
人間が持つさまざまな機能や能力の強化・向上を目指す「人間拡張」(Human Augmentation)の技術が注目を集めています。現役の医師であるとともに脳・AI分野における気鋭の若手研究者として注目を集める紺野大地氏と、テクノロジーを活用した社会課題解決に向け産官学の連携を支援するPwCコンサルティング「Technology Laboratory」(テクノロジーラボラトリー)の所長を務める三治信一朗との対談。脳への刺激による人間のパフォーマンス向上の可能性について意見交換した前編に続き、中編では人間が新たな身体感覚を後天的に獲得する可能性や、新しいテクノロジーの産業化に向けた課題について見解を交わしました。
三治:
前編で紺野先生が言及されたように、最近はスポーツ選手による脳情報の活用が広がっています。とりわけ人間拡張の技術実装が期待される分野の1つが、障がい者スポーツです。
競技における義手や義足の機能はさらに向上していくと考えられますが、義手や義足と脳との関係について、研究はどこまで進んでいるのでしょうか。
紺野:
例えば、事故などで手や足を失った人が、欠損した部位に痛みを感じる「幻肢痛」に関する研究は比較的進んでいます。他方、東京大学の中澤公孝教授の研究のように、義手や義足を装着したスポーツ選手のパフォーマンスについて、脳からアプローチする研究もあります。
個人的には後者のような研究もさらに広がってほしいと思いますが、現状では取り組んでいる人がまだ少ない印象です。
三治:
そうなんですね。四肢などの機能を補助するパーツが整ってくれば、最終的には人間拡張の感覚を総合的に管理するテクノロジーが必要になります。そのようなアプローチにおいても、脳の研究は重要ですね。
紺野:
物理的なパーツと脳の関係に加えて、今後は仮想空間における脳の研究が進展するかもしれません。例えばメタバースの中で「翼のあるアバター」を使うようになったとき、脳に「翼」に対応する感覚領域が出現し、発達するのかなど、興味を持っている研究者は多そうです。
三治:
私が所長を務めるPwCコンサルティングの「Technology Laboratory」でも、メタバースの研究を進めています。
メタバースに慣れないうちは、多くの人が仮想3次元(3D)空間の操作に戸惑いますが、その世界の「住人」であることに慣れてくると、仮想空間でのリアルな感覚が身に付き始めます。
例えば、家にこもりがちな人は外部環境を認識しづらい場合があり得ます。しかし、家の外に出て活動することで方向感覚が研ぎ澄まされ、道順や建物の位置関係を覚えるという感覚を体得していきます。
同様に、3Dの仮想空間で動き回ることに習熟すると、ゲームも含めて3D全般の操作が得意になってくる現象が見られます。紺野先生ご自身は、人間拡張という観点でメタバースをどのようにとらえていらっしゃいますか。
紺野:
メタバースが“強制的に人類を進化させる”可能性はあるかもしれません。例えば「LとRの音の違いを聞き分けられないと何のプレーもできないメタバース空間」があったとしましょう。
日本人は英語のLとRを聞き分けるのが苦手とされますが、そんな空間に放り込まれれば、脳の仕組みから考えて、しばらくたてば多くの人がLとRを聞き分けられるようになるかもしれません。
三治:
メタバースの中でロールプレイング的に活動することで、例えば職業上のスキルの向上につながったり、フィジカルやメンタルのトレーニングになったりする。そして結果的に人間のウェルビーイングが向上する、というのが望ましいですね。
三治:
視点を少し変えて、「新しいテクノロジーの産業化」にフォーカスして伺います。ご承知のように、日本は欧米に比べてニューロテックやブレインテック関連のスタートアップが極端に少ない状況です。
脳に関する国家プロジェクトにしても、3~5年といった短いスパンのものがほとんどで、財源も一過性になりがちです。「金の切れ目が縁の切れ目」で、ここでも研究者が海外に流出してしまう。これを転じて、望ましい循環を生むには何が必要でしょうか。
紺野:
私の周りにはニューロテックやブレインテック関連で起業した人もいるのですが、アカデミア全体では、産業化に関心の高い人は圧倒的に少ないのが現状です。人間拡張や脳利用の研究・技術開発を推進して社会実装するには、やはり産学の連携が不可欠だと考えます。
三治:
PwCコンサルティングは、デジタル空間と物理的な空間をつなげる研究で東京大学生産技術研究所と協力しており、こうした産学連携は今後さらに強化したいと考えています。
ただ、連携のためのルールや基盤の整備は、アカデミアの役割と言ってよいでしょう。産業を創造する過程では、「知の共有化」の仕組みがとても重要だからです。
アカデミアの「知」の“サイロ化”(他部門との連携を欠いた状態)を避け、その知が広がるように、アカデミアサイドが自ら努めてくださらないと、イノベーションは起こりません。ビジネスがさまざまな垣根を越えて展開することもありません。
私たちビジネスサイドとしても意識的に、「互いに歩み寄りましょう」とアカデミアサイドに働きかけています。
紺野:
希望はあります。アカデミアでは、大学や病院がシーズ(seeds)を提供してアドバイザーに入り、経営トップを産業界から出してもらうといったプロジェクトも増えています。脳神経科学界隈でも、お堅いとされてきた“大御所”の先生方が産学連携に取り組むケースが見られ、良い流れができつつあると感じています。
そしてイノベーションを起こす潜在力、これも日本にはあるはずです。例えば、日本はMRI(核磁気共鳴画像診断)やCT(コンピュータ断層撮影)の人口当たりの台数が世界一で、脳や健康に関するビッグデータが潤沢にあります。
ただ、それぞれのシステムはバラバラであるため、カルテなどデータのフォーマットの統一が進んでおらず、十分に活用できていないのです。DX(デジタルトランスフォーメーション)が進めば、こうした眠れるビッグデータを活用した新たなビジネスの創出が期待できるはずです。
三治:
そのような意欲的な取り組みが先鞭となれば、紺野先生をはじめ次世代を担う研究者にとって良い刺激になりそうですね。
紺野:
そのためにも、研究の継続と進化に向けて、アカデミアにおける就業環境の改善が急務です。
例えば、キャリアパスの整備が不十分な問題。私は医師なので病院に勤務できていますが、博士課程を修了した後にアカデミアで働くとなると、まずはポストドクターとして業務に従事することが大半です。その間、大学や病院と本人の間に雇用関係はなく、健康診断さえ自費で受けなければならないケースすらあります。
そんな労働環境では、優秀な若者がアカデミアに残ることなど期待できないでしょう。私が所属する池谷研究室でも、卒業生でアカデミアに残るのは1~2割程度で、残りの多くは産業界へと進みます。
三治:
まさに社会問題ですね。「知」の拠点たるアカデミアのすそ野を拡大するためには、産業界がアカデミアを応援する必要があります。
産業界はこれまでアカデミアに何を還元してきたか、ともに成長してこなかったのではないか。個人的にはそんな問題意識を感じざるを得ません。産業界とアカデミアが互いに共創力を高め合わないと、せっかくの「知」をうまく生かすことはできないのですから。
産業界としても、国に頼りすぎることなく、しっかりと投資して目指すべき方向感を共有しながら、産学連携を推し進める必要があるのではないでしょうか。
紺野:
ご指摘の通りです。ただ産業界としては、直ちに価値を生むわけではない脳神経科学には、投資しにくい面もあるのでしょう。
とはいえ、データサイエンティストに向けられる現在の高評価と同様に、「生体データを使ったことがある、使える」人材の価値が、10年後、20年後には格段に高まっている可能性もあります。
脳神経科学の研究成果は、すぐには産業界に還元できないかもしれませんが、人材としての貢献ならば、より幅広く期待できるのではと感じます。そんな認識が浸透すれば、産学連携はもっと進むはずだと思います。
三治:
研究、そして人材育成の方向感をより明確化するためにも、今は産と学がコラボレーションをスタートさせる良いタイミングですね。
(※後編に続く)
産業界とアカデミアが互いに共創力を高め合わないと、せっかくの「知」をうまく生かすことはできない
1991年生まれ。東京大学医学部卒。医師、神経科学者。脳や人工知能(AI)の研究を通じ、「脳の限界はどこにあり、テクノロジーによりその限界をどこまで拡張できるのか」を探究。書籍やSNSを通じ、積極的な情報発信にも努めている。
日系シンクタンク、コンサルティングファームを経て現職。産官学それぞれの特長を生かしたコンサルティングに強みを持つ。社会実装に向けた構想策定、コンソーシアム立ち上げ支援、技術戦略策定、技術ロードマップ策定支援コンサルティングに従事。
政策立案支援から、研究機関の技術力評価、企業の新規事業の実行支援などまで、幅広く視座の高いコンサルティングを提供する。
※ 法人名、役職、本文の内容などは掲載当時のものです。

先端技術に関する幅広い情報を集約し、企業の事業変革、大学・研究機関の技術イノベーション、政府の産業政策を総合的に支援します。

PwCは、企業のメタバース活用を事業構想から新規事業のデザイン、マネタイズモデルの設計、データ活用、システム開発に至るまで一貫して支援します。

脳科学の分野で活躍するさまざまな研究者と連携し、脳科学に関する最新の知見をもとに、顧客や従業員の脳や心の健康を支える新商品や新サービス、新事業の創出を支援します。

AI・VR・AR・MR・ロボティクス・ドローン・ブロックチェーン・3Dプリンターなど破壊的技術を核にビジネスのゲームチェンジを実現するサービスを提供しています。




